医療関係者
抗微生物薬適正使用の手引き 第三版
目次
用語集
【抗菌薬の種類】
| 分類 | 区分 | 抗菌薬名 | 一般名 | 略語 | |
|---|---|---|---|---|---|
| β-ラクタム系 | ペニシリン系 | 注射 | アンピシリン | アンピシリンナトリウム | ABPC |
| 注射 | スルバクタム/アンピシリン | スルバクタムナトリウム/アンピシリンナトリウム | SBT/ABPC | ||
| 注射 | ピペラシリン | ピペラシリン水和物 | PIPC | ||
| 注射 | タゾバクタム/ピペラシリン | タゾバクタム/ピペラシリン水和物 | TAZ/PIPC | ||
| 第1世代セファロスポリン系 | 注射 | セファゾリン | セファゾリンナトリウム水和物 | CEZ | |
| 第3世代セファロスポリン系 | 注射 | セフォタキシム | セフォタキシムナトリウム | CTX | |
| 注射 | セフタジジム | セフタジジム水和物 | CAZ | ||
| 注射 | セフトリアキソン | セフトリアキソンナトリウム水和物 | CTRX | ||
| 第4世代セファロスポリン系 | 注射 | セフェピム | セフェピム塩酸塩水和物 | CFPM | |
| オキサセフェム系 | 注射 | フロモキセフ | フロモキセフナトリウム | FMOX | |
| セファマイシン系 | 注射 | セフメタゾール | セフメタゾールナトリウム | CMZ | |
| β-ラクタマーゼ阻害剤配合セファロスポリン系 | 注射 | タゾバクタム/ セフトロザン | タゾバクタムナトリウム/ セフトロザン硫酸塩 | TAZ/CTLZ | |
| カルバペネム系 | 注射 | メロペネム | メロペネム水和物 | MEPM | |
| 注射 | イミペネム/ シラスタチン | イミペネム水和物/ シラスタチンナトリウム | IPM/CS | ||
| 注射 | レレバクタム/イミペネム/ シラスタチン | レレバクタム水和物/イミペネム水和物/シラスタチンナトリウム | REL/IPM/CS | ||
| モノバクタム系 | 注射 | アズトレオナム | アズトレオナム | AZT | |
| グリコペプチド系 | 注射 | テイコプラニン | テイコプラニン | TEIC | |
| 注射 | バンコマイシン | バンコマイシン塩酸塩 | VCM | ||
| オキサゾリジノン系 | 注射 | リネゾリド | リネゾリド | LZD | |
| リポペプチド系 | 注射 | ダプトマイシン | ダプトマイシン | DAP | |
| キノロン系(フルオロキノロン系) | 注射 | シプロフロキサシン | シプロフロキサシン | CPFX | |
| 注射 | レボフロキサシン | レボフロキサシン水和物 | LVFX | ||
| アミノグリコシド系 | 注射 | アミカシン | アミカシン硫酸塩 | AMK | |
| 注射 | ゲンタマイシン | ゲンタマイシン硫酸塩 | GM | ||
| 注射 | トブラマイシン | トブラマイシン | TOB | ||
| テトラサイクリン系 | 注射 | チゲサイクリン | チゲサイクリン | TGC | |
| 注射 | ミノサイクリン | ミノサイクリン塩酸塩 | MINO | ||
| リンコマイシン系 | 注射 | クリンダマイシン | クリンダマイシンリン酸エステル | CLDM | |
| ポリペプチド系 | 注射 | コリスチン | コリスチンメタンスルホン酸 ナトリウム |
CL | |
| その他抗菌薬 | サルファ剤 | 注射 | スルファメト/キサゾール/トリメトプリム | スルファメトキサゾール/トリメトプリム | ST |
| ニトロイミダゾール系 | 注射 | メトロニダゾール | メトロニダゾール | MNZ | |
| ホスホマイシン系 | 注射 | ホスホマイシン | ホスホマイシンナトリウム | FOM | |
| 抗真菌薬 | ポリエンマクロライド系 | 注射 | アムホテリシンB | アムホテリシンB | AMPH-B |
| 注射 | リポソーマルアムホテリシンB | アムホテリシンB | L-AMB | ||
| トリアゾール系 | 注射 | フルコナゾール | フルコナゾール | FLCZ | |
| 注射 | ホスフルコナゾール | ホスフルコナゾール | F-FLCZ | ||
| 注射 | ボリコナゾール | ボリコナゾール | VRCZ | ||
| エキノキャンディン系 | 注射 | カスポファンギン | カスポファンギン酢酸塩 | CPFG | |
| 注射 | ミカファンギン | ミカファンギンナトリウム水和物 | MCFG | ||
| β-ラクタム系 | ペニシリン系 | 経口 | ベンジルペニシリンベンザチン | ベンジルペニシリンベンザチン 水和物 |
PCG |
| 経口 | アモキシシリン | アモキシシリン水和物 | AMPC | ||
| 経口 | クラブラン酸/ アモキシシリン | クラブラン酸カリウム/アモキシシリン水和物 | CVA/AMPC | ||
| 第1世代セファロスポリン系 | 経口 | セファレキシン | セファレキシン | CEX | |
| 第3世代セファロスポリン系 | 経口 | セフカペン | セフカペン ピボキシル塩酸塩 水和物 |
CFPN-PI | |
| 経口 | セフジトレン | セフジトレン ピボキシル | CDTR-PI | ||
| 経口 | セフテラム | セフテラム ピボキシル | CFTM-PI | ||
| 経口 | セフポドキシム | セフポドキシム プロキセチル | CPDX-PR | ||
| カルバペネム系 | 経口 | テビペネム | テビペネム ピボキシル | TBPM-PI | |
| ペネム系 | 経口 | ファロペネム | ファロペネムナトリウム水和物 | FRPM | |
| オキサゾリジノン系 | 経口 | リネゾリド | リネゾリド | LZD | |
| キノロン系(フルオロキノロン系) | 経口 | ガレノキサシン | メシル酸ガレノキサシン水和物 | GRNX | |
| 経口 | シプロフロキサシン | シプロフロキサシン塩酸塩水和物 | CPFX | ||
| 経口 | モキシフロキサシン | モキシフロキサシン塩酸塩 | MFLX | ||
| 経口 | レボフロキサシン | レボフロキサシン水和物 | LVFX | ||
| テトラサイクリン系 | 経口 | ドキシサイクリン | ドキシサイクリン塩酸塩水和物 | DOXY | |
| 経口 | ミノサイクリン | ミノサイクリン塩酸塩 | MINO | ||
| 経口 | テトラサイクリン | テトラサイクリン塩酸塩 | TC | ||
| リンコマイシン系 | 経口 | クリンダマイシン | クリンダマイシン塩酸塩 | CLDM | |
| マクロライド系 | 経口 | アジスロマイシン | アジスロマイシン水和物 | AZM | |
| 経口 | エリスロマイシン | エリスロマイシンエチルコハク酸 エステル |
EM | ||
| 経口 | クラリスロマイシン | クラリスロマイシン | CAM | ||
| 経口 | フィダキソマイシン | フィダキソマイシン | FDX | ||
| グリコペプチド系 | 経口 | バンコマイシン | バンコマイシン塩酸塩 | VCM | |
| その他抗菌薬 | サルファ剤 | 経口 | スルファメト キサゾール/トリメトプリム |
スルファメトキサゾール/トリメトプリム | ST |
| ニトロイミダゾール系 | 経口 | メトロニダゾール | メトロニダゾール | MNZ | |
| ホスホマイシン系 | 経口 | ホスホマイシン | ホスホマイシンカルシウム水和物 | FOM | |
| 抗真菌薬 | トリアゾール系 | 経口 | フルコナゾール | フルコナゾール | FLCZ |
| 経口 | ボリコナゾール | ボリコナゾール | VRCZ | ||
【細菌・ウイルスの種類】
| 和名 | 学名 |
|---|---|
| グラム陰性桿菌 | |
| アシネトバクター・バウマニ | Acinetobacter baumannii |
| インフルエンザ菌 | Haemophilus influenzae |
| 腸管出血性大腸菌 | Enterohemorrhagic E. coli: EHEC |
| 腸管毒素原性大腸菌 | Enterotoxigenic E. coli: ETEC |
| 大腸菌 | Escherichia coli |
| クレブシエラ・ニューモニエ(肺炎桿菌) | Klebsiella pneumoniae |
| クレブシエラ・オキシトカ | Klebsiella oxytoca |
| エルシニア属菌 | Yersinia enterocolitica |
| エンテロバクター属菌 | Enterobacter spp. |
| 赤痢菌 | Shigella spp. |
| 腸炎ビブリオ | Vibrio parahaemolyticus |
| コレラ菌 | Vibrio cholerae |
| カンピロバクター・ジェジュニ | Campylobacter jejuni |
| 百日咳菌 | Bordetella pertussis |
| サルモネラ属菌 | Salmonella spp. |
| フソバクテリウム属菌 | Fusobacterium spp. |
| バクテロイデス属菌 | Bacteroides spp. |
| プロビデンシア属菌 | Providencia spp. |
| プロテウス・ミラビリス | Proteus mirabilis |
| セラチア・マルセッセンス | Serratia marcescens |
| シトロバクター・フロインディー | Citrobacter freundii |
| ステノトロフォモナス・マルトフィリア | Stenotrophomonas maltophilia |
| チフス菌 | Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi |
| パラチフスA菌 | Salmonella enterica subsp. enterica serovarParatyphi A |
| グラム陽性桿菌 | |
| ウェルシュ菌 | Clostridium perfringens |
| ボツリヌス菌 | Clostridium botulinum |
| クロストリディオイデス・ディフィシル | Clostridioides difficile |
| セレウス菌 | Bacillus cereus |
| バチルス属菌 | Bacillus spp. |
| プロピオニバクテリウム属菌 | Propionibacterium spp. |
| コリネバクテリウム属菌 | Corynebacterium spp. |
| グラム陰性球菌 | |
| モラクセラ・カタラーリス | Moraxella catarrhalis |
| グラム陽性球菌 | |
| 腸球菌(エンテロコッカス属菌) | Enterococcus spp. |
| 肺炎球菌 | Streptococcus pneumoniae |
| A群β溶血性連鎖球菌 | Group A β-hemolytic Streptococcus spp.: GAS |
| 黄色ブドウ球菌 | Staphylococcus aureus |
| 表皮ブドウ球菌 | Staphylococcus epidermidis |
| スタフィロコッカス・ルグドゥネンシス | Staphylococcus lugdunensis |
| コアグラーゼ陰性ブドウ球菌 | Coagulase negative Staphylococci: CNS |
| 真菌 | |
| カンジダ属菌 | Candida spp. |
| 非定型菌、その他の細菌 | |
| マイコプラズマ | Mycoplasma spp. |
| クラミジア・ニューモニエ | Chlamydophila pneumoniae |
| クラミジア属菌 | Chlamydia spp. |
| レジオネラ | Legionella spp. |
| 赤痢アメーバ | Entamoeba histolytica |
| 薬剤耐性菌 | |
| カルバペネム耐性A. baumannii | Carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii: CRAB |
| 多剤耐性アシネトバクター | Multidrug-resistant Acinetobacter spp.: MDRA |
| AmpC産生腸内細菌目細菌 | AmpC producing Enterobacterales |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌 | Carbapenem-resistant Enterobacterales: CRE |
| 難治耐性緑膿菌 | Difficult-to-treat resistance P. aeruginosa: DTR-PA |
| 基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ産生 | Extended-spectrum β-lactamase: ESBL |
| メチシリン耐性(感受性)黄色ブドウ球菌 | Methicillin-Resistant[Susceptible] Staphylococcus aureus: MRSA [MSSA] |
| 多剤耐性緑膿菌 | Multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa: MDRP |
| バンコマイシン耐性腸球菌 | Vancomycin-resistant Enterococci: VRE |
【略語一覧】
| 略語 | 英名 | 和名 |
|---|---|---|
| 組織名 | ||
| ACP | American College of Physicians | 米国内科学会 |
| CDC | Centers for Disease Control and Prevention | 米国疾病予防管理センター |
| CLSI | Clinical and Laboratory Standards Institute | 臨床・検査標準協会 |
| ESCMID | European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases | 欧州臨床微生物・感染症学会 |
| EUCAST | European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing | 欧州抗菌薬感受性試験法検討委員会 |
| FDA | Food and Drug Administration | 米国食品医薬品局 |
| IDSA | Infectious Diseases Society of America | 米国感染症学会 |
| JAID | Japanese Association for Infectious Diseases | 日本感染症学会 |
| 用語名 | ||
| AST | Antimicrobial Stewardship Team | 抗菌薬適正使用支援チーム |
| CAUTI | Catheter-associated urinary tract infections | カテーテル関連尿路感染症 |
| CDI | Clostridioides difficile Infection | クロストリディオイデス・ディフィシル感染症 |
| CLABSI | Central line-associated bloodstream infection | 中心静脈カテーテル関連血流感染症 |
| CRBSI | Catheter-related blood stream infection | カテーテル関連血流感染症 |
| SSI | Surgical site infection | 手術部位感染症 |
| TDM | Therapeutic Drug Monitoring | 治療薬物モニタリング |
1. はじめに
(1) 策定の経緯
抗微生物薬注 は現代の医療において重要な役割を果たしており、感染症の治癒、患者の予後の改善に大きく寄与してきた1。その一方で、抗微生物薬には、その使用に伴う有害事象や副作用が存在することから、抗微生物薬を適切な場面で適切に使用することが求められている1。近年、そのような不適正な抗微生物薬使用に伴う有害事象として、薬剤耐性菌とそれに伴う感染症の増加が国際社会でも大きな課題の一つに挙げられるようになってきている1。不適正な抗微生物薬使用に対してこのまま何も対策が講じられなければ、2050年には全世界で年間1,000万人が薬剤耐性菌により死亡することが推定されており、2019年時点で既に薬剤耐性菌が関連した死亡者が年間約490万人、薬剤耐性菌が原因による死亡者数が約120万人と推計されている2-4。また、1980年代以降、新たな抗微生物薬の開発は減少する一方で、病院内を中心に新たな薬剤耐性菌の脅威が増加していること1から、抗微生物薬を適正に使用しなければ、将来的に感染症を治療する際に有効な抗菌薬が存在しないという事態になることが憂慮されている5。今の段階で限りある資源である抗菌薬を適正に使用することで上記の事態を回避することが重要であり、薬剤耐性(Antimicrobial Resistance: AMR)対策として抗微生物薬の適正使用が必要である。
2015年5月に開催された世界保健総会では、薬剤耐性対策に関するグローバルアクションプランが採択され、それを受けて日本でも2016年4月に薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2016-2020)を策定し、2023年4月に薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2023-2027)を更新した1。その中でも、抗微生物薬の適正使用は、薬剤耐性対策として、日頃の臨床の現場で医療従事者及び患者を含む医療に関わるすべての者が対応すべき最重要の分野の一つとしている1。
日本における抗微生物薬使用量については、処方販売量を基にした研究において、人口千人あたりの抗菌薬の1日使用量が10.22DID(DDDs: Defined Daily Doses/1,000 inhabitants/day)注 との試算が示されており、そのうち90.1%が経口抗菌薬と報告されている6。また、諸外国との比較から、日本では、経口の第3世代セファロスポリン系抗菌薬、フルオロキノロン系抗菌薬、マクロライド系抗菌薬の使用量が多いことが指摘されている1。日本の医療現場における抗微生物薬の不適正使用の頻度・割合は現状として判然としないものの、米国では処方された抗微生物薬の少なくとも30%程度は不適正使用であることが示されており7、日本においても、65歳以下の患者の下痢症で過剰に抗菌薬が処方され8、小児の肺炎でガイドラインを遵守して抗菌薬を処方している施設が4分の1しかない9。一方で、小児抗菌薬適正使用加算導入により対象年齢の抗菌薬処方が減少し、加えて医療提供者に対する教育効果により全年齢で抗菌薬処方を減少させていた10。そのため、日本でも引き続き抗微生物薬の適正使用を推進していくことが必要である。 このような経緯のもと、本手引きでは、適正な感染症診療に係る指針を明確にすることで、抗微生物薬の適正使用を推進していくことを目指している。
注1 抗微生物薬等については、以下の様な詳細な定義があるものの、実際の医療では、抗菌薬、抗生物質、抗生剤の三つの用語は細菌に対して作用する薬剤の総称として互換性をもって使用されている。(以下、日本化学療法学会抗菌化学療法用語集、薬剤耐性[AMR]対策アクションプラン等を参照した。)
抗微生物薬(antimicrobial agents, antimicrobials):微生物(一般に細菌、真菌、ウイルス、寄生虫に大別される)に対する抗微生物活性を持ち、感染症の治療、予防に使用されている薬剤の総称。ヒトで用いられる抗微生物薬は抗菌薬(細菌に対する抗微生物活性を持つもの)、抗真菌薬、抗ウイルス薬、抗寄生虫薬を含む。
抗菌薬(antibacterial agents):抗微生物薬の中で細菌に対して作用する薬剤の総称として用いられる。
抗生物質(antibiotics):微生物、その他の生活細胞の機能阻止又は抑制する作用(抗菌作用と言われる)を持つ物質であり、厳密には微生物が産出する化学物質を指す。
抗生剤:抗生物質の抗菌作用を利用した薬剤を指す通称。
注2 DDD:Defined Daily Doseの略称。成人患者(体重70kg)においてその薬剤が主な適応として使用される時の平均的な投与量のことであり、世界保健機関は各薬剤のDDDの値を提供している。
物薬の不適正使用の頻度・割合は現状として判然としないものの、米国では処方された抗微生物薬の少なくとも30%程度は不適正使用であることが示されており7、日本においても、65歳以下の患者の下痢症で過剰に抗菌薬が処方され8、小児の肺炎でガイドラインを遵守して抗菌薬を処方している施設が4分の1しかない9。一方で、小児抗菌薬適正使用加算導入により対象年齢の抗菌薬処方が減少し、加えて医療提供者に対する教育効果により全年齢で抗菌薬処方を減少させていた10。そのため、日本でも引き続き抗微生物薬の適正使用を推進していくことが必要である。
このような経緯のもと、本手引きでは、適正な感染症診療に係る指針を明確にすることで、抗微生物薬の適正使用を推進していくことを目指している。
(2) 策定の目的
本手引きの策定の主たる目的は、適正な感染症診療が広がることで、患者に有害事象をもたらすことなく、抗微生物薬の不適正使用を減少させることにある。日本の薬剤耐性(AMR)アクションプラン(2023-2027)の成果指標では「2027年までに人口千人あたりの一日抗菌薬使用量を2020年の水準から15%減少させる」、「2027年までに人口千人あたりのカルバペネム系の一日静注抗菌薬使用量を2020年の水準から20%削減する」こと等が設定されている1が、これらは適正な感染症診療の普及を進めた結果としての成果と考えるべきである。
(3) 手引きの対象
本手引きの第二版においては、主に外来診療を行う医療従事者を対象として作成していた。しかし、今回第三版に改訂するにあたり、入院患者における抗微生物薬適正使用に関する項も追加し、より幅広い患者を対象としたものとなるよう、内容のさらなる充実を図った。なお、推奨事項の内容は、抗微生物薬の適正使用の概念の普及、推進を遂行するために欠かせない、処方を行わない医療従事者や患者も対象とした内容としていることから、すべての医療従事者や患者にご一読頂きたい。
(i) 一般外来編
外来診療を行う医療従事者の中でも、特に診察や処方、保健指導を行う医師を対象として作成した。上述の通り、日本の抗微生物薬使用の多くは経口抗菌薬であること、さらに使用量が多い経口抗菌薬である第3世代セファロスポリン系抗菌薬、フルオロキノロン系抗菌薬、マクロライド系抗菌薬の処方の多くは外来診療で処方されていることが推測されるため、各論の前半部分では、外来診療で各医療従事者が主に抗微生物薬の必要な状況と必要でない状況を判別できるよう支援することを念頭に置いた内容とした。
(ii) 入院患者における抗微生物薬適正使用編
「入院患者の感染症に対する基本的な考え方」では外来患者と比較してより複雑な病態が想定される入院患者に対して適切に抗微生物薬を使用するための基本的な考え方について解説した。医療機関で入院患者の診療に関わる様々な医療従事者を対象としている。別冊の「入院患者の感染症で問題となる微生物」では、各医療機関で実際に入院患者の感染症の治療にあたる医療従事者(感染症診療を専門とする医療従事者や院内の抗菌薬適正使用支援チーム[Antimicrobial Stewardship Team: AST]を含む)を対象に、薬剤耐性菌を含む入院患者の感染症に対する具体的な治療につき解説した。
(4) 想定する患者群
本手引きでは、外来患者・入院患者に関しそれぞれ以下のような患者群を想定している。例えば、ペニシリンアレルギーを有している症例に対する処方等、本手引きの範囲を超える内容については、専門医に相談することや成書を参照することをご検討頂きたい。入院患者の抗微生物薬適正使用に関しては、院内のASTや感染症専門医等へのコンサルテーションも積極的に活用することが推奨される。
(i) 外来患者
後述のように、患者数が多い急性気道感染症や急性下痢症では、外来診療において抗菌薬をはじめとする抗微生物薬が必要な状況は限定されている。本手引きの各論では、薬剤耐性対策の中でも特に重要な抗菌薬の適正使用を推進するため、諸外国での現状及び日本において過剰な処方が指摘されている抗菌薬の種類6,7から総合的に判断し、不必要に抗菌薬が処方されていることが多いと考えられる急性気道感染症及び急性下痢症の患者に焦点を当てて記載している。本手引きでは、基礎疾患のない患者を対象とし、成人及び学童期以上の小児編、及び乳幼児編と分けて記載している。
(ii) 入院患者
医療機関においては、感染症の治療のために入院する患者のみでなく、他疾患の治療のための入院中に感染症を発症する場合や、感染症疾患の治療中に別の感染症を併発する場合もある。その大半は医療関連感染症であり、医療デバイス挿入や手術に関連したものは国内でもサーベイランスの対象になっている11-13。医療関連感染症は患者の在院日数の延長や合併症発生率・致命率の上昇、医療費の増加等への影響が甚大でその予防は極めて重要である14。しかし、本稿の内容は抗微生物薬適正使用に焦点を絞っているため予防に関する記載は含まず、医療関連感染症を含む「入院患者の感染症」に対する抗菌薬の適正使用の基本的な考え方について概説し、その具体的な治療法に関して別冊に記した。
医療施設は、薬剤耐性の発生やその伝播に重要な役割を果たしており、医療施設における感染症に対する抗菌薬の適正使用は薬剤耐性対策において不可欠である15。なお、適正使用の考え方の原則に関しては小児にも適応可能な内容であるが、特に具体的な処方例に関しては腎機能正常な成人患者を対象にして記載されている。このため、小児への使用や腎機能障害時の用法用量調整に関しては、成書の参照や専門医へのコンサルテーション等、個別のアプローチを行うことを推奨する。
本編の中における重症患者や免疫不全患者については、それぞれ臓器機能不全や敗血症性ショックを呈しているもの16、免疫抑制剤や化学療法の投与を受けているものや原発性・後天性免疫不全症候群等17を主な対象としているが、個々の患者における経過や現状を加味して判断することが望ましい。
なお、抗微生物薬等の処方については、添付文書に記載された内容を確認の上、適切に行うことが重要である。また、参考資料として、本手引きの推奨事項に沿って診療を行う上で確認すべき項目をまとめた資料を掲載しているので適宜利用頂きたい。
(5) 科学的根拠の採用方針
急性気道感染症に関して、日本感染症学会(Japanese Association for Infectious Diseases: JAID)、日本化学療法学会(Japanese Society of Chemotherapy: JSC)、日本小児感染症学会、日本小児呼吸器学会、日本耳鼻咽喉科学会、日本鼻科学会、米国疾病予防管理センター(Centers for Disease Control and Prevention: CDC)、米国内科学会(American College of Physicians: ACP)、米国感染症学会(Infectious Diseases Society of America: IDSA)、米国小児科学会(American Academy of Pediatrics: AAP)、欧州臨床微生物・感染症学会(European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases: ESCMID)、英国国立医療技術評価機構(National Institute for Health and Care Excellence: NICE)等の専門家集団による現在の診療ガイドラインの推奨を踏まえつつ、最新の科学的根拠を反映させるために統合解析(メタアナリシス:Meta-analysis)、系統的レビュー(Systematic Review)、無作為化比較試験(Randomized Clinical Trial)に関する文献検索を行った。文献検索はCochrane Library、PubMed及び医中誌において2017年1月1日-2023年1月31日まで行った。英語論文では、“acute bronchitis” OR “respiratory tract infection” OR “pharyngitis” OR “rhinosinusitis” OR “the common cold” OR “bronchiolitis” OR “croup”をMedical Subject Headings (MeSH) termsとして、日本語論文では、「急性気管支炎」OR「気道感染症」OR「咽頭炎」OR「鼻副鼻腔炎」OR「普通感冒」をキーワードとして検索を行った。
急性下痢症に関しては、JAID/JSC、IDSA、米国消化器病学会(American College Of Gastroenterology: ACG)、世界消化器病学会(World Gastroenterology Organisation: WGO)等の専門家集団による現在の診療ガイドラインの推奨を踏まえつつ、英語論文では、“diarrhea”AND (“acute disease” OR “infectious diarrhea” OR “dysentery” OR “acute gastroenteritis”) をMeSH termsとして、日本語論文では、「胃腸炎」OR「急性下痢」をキーワードとして検索を行った。
なお、急性気道感染症に関しては、慢性の肺疾患や免疫不全のない健康な成人及び小児に、急性下痢症に関しては、慢性の腸疾患や免疫不全のない健康な成人及び小児に対象を限定して検索を行った。
入院患者に関して、JAID/JSC、CDC、IDSA、ESCMID、NICE等の専門家集団による現在の診療ガイドラインの推奨を踏まえつつ、各項専門家の文献を追加した。なお、入院編については、添付文書の適応症に含まれていない場合や添付文書推奨量の上限を超える場合、社会保険診療報酬支払基金審査情報提供事例に記載のある場合は、用法用量の末尾に「¶」を挿入し補遺に注釈を記載した。
2. 総論
(1) 抗微生物薬適正使用とは
抗微生物薬適正使用注 とは、文字通り抗微生物薬を適正に使用するための取組(介入)に係る全般的な概念である。抗微生物薬適正使用では、主に抗微生物薬使用の適応を判断し、治療選択、使用量、使用期間等を明確に評価して、抗微生物薬が投与される患者のアウトカムを改善し、有害事象を最小限にすることを主目的としている18。 これまでの研究では、抗微生物薬適正使用の方法として、処方後監査と直接の処方者への情報提供、特定の抗微生物薬の採用の制限や処方前許可制の仕組み、抗微生物薬使用の教育・普及啓発、より狭域な抗微生物薬への変更、治療指針の導入、静注抗微生物薬から経口抗微生物薬への変更、迅速診断の導入、処方を遅らせるような介入(抗菌薬の延期処方等)等が挙げられており、日常診療では、これらの介入を単独又は複数組み合わせて、抗微生物薬適正使用を進めていくことになる。なお、どの介入が適しているかに関しては、抗微生物薬適正使用を行う診療の状況(入院診療、外来診療)や、実際に適正使用を行う医療機関の資源の充実度により異なると考えられている19。
(2) 抗微生物薬使用の適応病態
抗微生物薬使用の適応となる病態は、原則として抗微生物薬の投与が標準治療として確立している感染症と診断されている、又は強く疑われる病態である。その適応以外での抗微生物薬使用は最小限に止めるべきであり、また、細菌感染症であっても、抗菌薬を使用しなくても自然軽快する感染症も存在するため、各医師は、抗菌薬の適応病態を自らが関わる診療の状況ごとに把握しておくべきである。
患者は、適切に処方された抗菌薬については、症状が改善したからといって途中でやめるのではなく、医師の指示通り最後まで服用すべきである。また、医師から抗菌薬の服用中止の指示が出され、抗菌薬が余る状況になった際には、それらの抗菌薬は適切に廃棄すべきである。
なお、外来診療における対応が困難な患者が受診した場合は、速やかに適切な医療機関に搬送すべきである。その際、その後の培養検査の感度を損なうことのないよう、抗菌薬を投与する前に適切な培養検査(血液培養の複数セット採取、喀痰や尿のグラム染色・培養)を実施することが望ましい。
(3) 抗微生物薬の不適正使用とは
本手引きでは、抗微生物薬が適正使用されていない状況を「不必要使用」と「不適切使用」に大別して記載する。「不必要使用」とは、抗微生物薬が必要でない病態において抗微生物薬が使用されている状態を指す。また、「不適切使用」とは抗微生物薬が投与されるべき病態であるが、その状況における抗微生物薬の選択、使用量、使用期間が標準的な治療から逸脱した状態を指す。
以前に処方された抗菌薬を保存しておき、発熱等の際に患者が自らの判断で服用することは、「不必要使用」又は「不適切使用」のいずれかになる可能性が考えられるが、このような抗微生物薬の使用は、感染症の診断を困難にするばかりではなく、安全性の側面(薬剤の副作用、必要量以上の投与等)からも問題がある。特殊な状況を除いて、患者はこのような行為は慎み、医療従事者は上記のような使用をしないように患者に伝えることが重要である。
(4) その他
感染症を予防することは、抗微生物薬が必要な病態を減らし、抗微生物薬の使用を減らすことにつながる。そのような急性気道感染症及び急性下痢症の予防に関しても配慮されるべき事項について要点を記載する。
(i) 手指衛生(手洗い)
手指衛生は、急性気道感染症及び急性下痢症を起こしうる微生物(主にウイルス)の伝播を防ぐことが知られており、特に小児からの急性気道感染症の伝播に対して効果が高いこと20や、急性下痢症の発生を減少させること21が報告されている。手指衛生の方法はいくつかあるが、主に①アルコール含有擦式消毒薬の使用と、②石鹸と流水の使用が挙げられるが、鼻汁、痰、吐物等が手に付着した場合(目で見える汚れがある場合)には流水と石鹸での手指衛生が推奨されている22。特に、ノロウイルスによる急性下痢症では、アルコール含有擦式消毒薬による手指衛生は十分でなく、石鹸と流水が好ましい旨を示している23。
(ii) ワクチン接種
急性気道感染症及び急性下痢症の一部には予防効果が期待されるワクチンが存在する。すなわち、気道感染症においてはインフルエンザワクチンや百日咳ワクチン(ジフテリア、破傷風、不活化ポリオとの四種混合ワクチン[DPT-IPV]、又はジフテリア、破傷風との三種混合ワクチン[DPT]に含まれる)、麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)、新型コロナウイルスワクチン、細菌性肺炎の原因となる肺炎球菌に対するワクチン、Haemophilus influenzae b型に対するワクチン(ヒブワクチン)、急性下痢症においてはロタウイルスワクチンである。日本では、四種混合DPT-IPVワクチン、MRワクチン、沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン、ヒブワクチン、ロタウイルスワクチンは小児の定期接種、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン、インフルエンザワクチンは高齢者の定期接種、またインフルエンザワクチン(高齢者を除く)、三種混合DPTワクチンは任意接種で接種が可能である24。2023年10月現在、新型コロナウイルスワクチンは月齢6か月以上で公費助成される。
(iii) 咳エチケット
咳エチケットは、人から人への微生物の伝播を防ぎ、急性気道感染症の予防につながることから、推奨されている
- 咳やくしゃみが出る時は、できるだけマスクをすること
- とっさの咳やくしゃみの際にマスクがない場合は、ティッシュや上腕の内側等で口と鼻を覆い、顔を他の人に向けないこと
- 鼻汁・痰等を含んだティッシュはすぐにゴミ箱に捨て、すぐに手を洗うこと等
(iv) マスク
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行に伴い、マスクの有効性に関する研究が世界各地で行われた。研究によって流行状況等も異なるため、解釈には注意が必要だが、マスクによる感染予防効果を示唆する研究も複数認められている25。
また、成人およびマスクができる年齢の小児では、室内で人が多い混雑した場所等でのマスク着用は、咳やくしゃみによる飛沫の拡散を抑えることができる26。
(v) うがい
うがいによる急性気道感染症の予防効果の検証は、ほとんど行われていない。日本で行われた無作為化比較試験では、一般的なケア群、水によるうがい群、ヨードによるうがい群の3群に分けて比較が行われ、水によるうがい群の参加者の方が一般的なケア群に比べて急性気道感染症の発生率が低く、うがいが有効であることが報告されている27。しかしながら、この研究が非盲検化試験であることや結果の妥当性の検証が難しいこと、さらに、ビタミンDとうがいの急性気道感染症に対する予防効果を検証した無作為化比較試験では、うがいの有効性が証明できなかったこと28等から、うがいの急性気道感染症に対する予防効果については未だに議論がある。
3. 引用文献
- 国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議. 薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン 2023-2027. 東京: 内閣官房; 2023.
- Ardal C, Outterson K, Hoffman SJ, et al. International cooperation to improve access to and sustain effectiveness of antimicrobials. Lancet. 2016;387(10015):296-307.
- The Review on Antimicrobial Resistance. Tackling Drug-Resistant Infections Globally: Final Report and Recommendations. https://amr-review.org/Publications.html. 最終閲覧日2023年3月24日.
- Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis, Antimicrobial Resistance Collaborators, Lancet. 2022;399(10325):629-655.
- Arias CA, Murray BE. Antibiotic-resistant bugs in the 21st century - a clinical super-challenge. N Engl J Med. 2009;360(5):439-443.
- 全国抗菌薬販売量2022年調査データ. AMRCRC. https://amrcrc.ncgm.go.jp/surveillance/020/file/Sales_2013-2022_1.pdf
- Fleming-Dutra KE, Hersh AL, Shapiro DJ, et al. Prevalence of Inappropriate Antibiotic Prescriptions Among US Ambulatory Care Visits, 2010-2011. JAMA. 2016;315(17):1864-1873.
- Akane Ono, Kensuke Aoyagi, et al. Trends in healthcare visits and antimicrobial prescriptions for acute infectious diarrhea in individuals aged 65 years or younger in Japan from 2013 to 2018 based on administrative claims database: a retrospective observational study, BMC Infect Dis. 2021 Sep 21;21(1):983.
- Yusuke Okubo, Kazuhiro Uda, et al. National trends in appropriate antibiotics use among pediatric inpatients with uncomplicated lower respiratory tract infections in Japan, J Infect Chemother. 2020 Nov;26(11):1122-1128.
- Jindai K, Itaya T, Ogawa Y, Kamitani T, Fukuhara S, Goto M, Yamamoto Y. Decline in oral antimicrobial prescription in the outpatient setting after nationwide implementation of financial incentives and provider education: An interrupted time-series analysis. Infect Control Hosp Epidemiol. 2023 Feb;44(2):253-259.
- JANIS 厚生労働省 院内感染対策サーベイランス事業https://janis.mhlw.go.jp/about/index.html. 最終閲覧日2023年6月19日.
- 日本環境感染学会 JHAIS委員会http://www.kankyokansen.org/modules/iinkai/index.php?content_id=4. 最終閲覧日2023年6月19日.
- J-SIPHE 感染対策連携共通プラットフォーム https://j-siphe.ncgm.go.jp/. 最終閲覧日2023年6月19日.
- WHO. report on the burden of endemic health care-associated infection worldwide http://apps.who.int/iris/handle/10665/80135. 最終閲覧日2023年6月19日.
- National Action Plan to Prevent Health Care-Associated Infections: Road Map to Elimination Phase Four: Coordination among Federal Partners to Leverage HAI Prevention and Antibiotic Stewardship, February 5th, 2018. https://health.gov/sites/default/files/2019-09/National_Action_Plan_to_Prevent_HAIs_Phase_IV_2018.pdf. 最終閲覧日2023年6月19日.
- Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2021. Crit Care Med. Nov 1 2021;49(11):e1063-e1143
- Poutsiaka DD, et al. Risk factors for death after sepsis in patients immunosuppressed before the onset of sepsis, Scand J Infect Dis, 2009;41(6-7):469-479.
- Barlam TF, Cosgrove SE, Abbo LM, et al. Implementing an Antibiotic Stewardship Program: Guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the Society for Healthcare Epidemiology of America. Clin Infect Dis. 2016;62(10):e51-77. Drekonja DM, Filice GA, Greer N, et al. Antimicrobial stewardship in outpatient settings: a systematic review. Infect Control Hosp Epidemiol. 2015;36(2):142-152.
- Arnold SR, Straus SE. Interventions to improve antibiotic prescribing practices in ambulatory care. Cochrane Database Syst Rev. 2005;(4):CD003539.
- Jefferson T, Del Mar CB, Dooley L, et al. Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(7):CD006207.
- Ejemot-Nwadiaro RI, Ehiri JE, Arikpo D, Meremikwu MM, Critchley JA. Hand washing promotion for preventing diarrhoea. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(9):CD004265.
- Mayo Clinic. Norovirus Infection.
- 厚生労働省健康局結核感染症課. ノロウイルスに関するQ&A. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html. 最終閲覧日2023年3月24日.
- 国立感染症研究所. 日本の定期/任意予防接種スケジュール. http://www.nih.go.jp/niid/images/vaccine/schedule/2016/JP20161001.png. Published 2016. 最終閲覧日2023年3月24日.
- 厚生労働省健康局結核感染症課. インフルエンザQ&A. http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html. Published 2016. 最終閲覧日2023年3月24日.
- 厚生労働省第116回(令和5年2月8日)新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード.資料3-3-②, マスク着用の有効性に関する科学的知見. https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001055263.pdf
- Satomura K, Kitamura T, Kawamura T, et al. Prevention of upper respiratory tract infections by gargling: a randomized trial. Am J Prev Med. 2005;29(4):302-307.
- Goodall EC, Granados AC, Luinstra K, et al. Vitamin D3 and gargling for the prevention of upper respiratory tract infections: a randomized controlled trial. BMC Infect Dis. 2014;14:273.
一般外来における成人・学童期以降の小児編
4. 急性気道感染症
(1) 急性気道感染症とは
急性気道感染症は、急性上気道感染症(急性上気道炎)及び急性下気道感染症(急性気管支炎)を含む概念であり、一般的には「風邪」、「風邪症候群」、「感冒」等の言葉が用いられている1,2。
「風邪」は、狭義の「急性上気道感染症」という意味から、「上気道から下気道感染症」を含めた広義の意味まで、様々な意味で用いられることがあり3、気道症状だけでなく、急性(あるいは時に亜急性)の発熱や倦怠感、種々の体調不良を「風邪」と認識する患者が少なくないことが報告されている4。患者が「風邪をひいた」と言って受診する場合、その病態が急性気道感染症を指しているのかを区別することが鑑別診断のためには重要である。
(2) 急性気道感染症の疫学
厚生労働省の患者調査(2020年10月実施)では、急性上気道感染症注 による1日あたりの外来受療率は128(人口10万対)と報告されている5。また、1960年代に米国で行われた研究では、急性気道感染症の年間平均罹患回数は、10歳未満で3-7回、10-39歳で2-3回、40歳以上で1-2回6、オーストラリアで行われた全国調査でも、気道感染症罹患の予測確率は年齢とほぼ線形の関連があり、年齢が高くなればなるほど罹患する確率が低いこと7が報告されている。
一方で、在宅医療を受けている419人の65歳以上の高齢者を対象とした日本で行われたコホート研究によると、年間229件の発熱例のうち普通感冒はわずかに13件であったことが示されている8。このことから、高齢者が「風邪をひいた」として受診してきた場合、「その病態は本当に急性気道感染症を指しているのか?」について疑問に持って診療にあたる必要がある。
急性気道感染症の原因微生物の約9割はライノウイルスやコロナウイルスといったウイルスであることが報告されている6,9。急性気道感染症において、細菌が関与する症例はごく一部であり、急性咽頭炎におけるA群β溶血性連鎖球菌(Group A β-hemolytic Streptococcus spp.: GAS)、急性気管支炎におけるマイコプラズマやクラミジアが代表的な原因微生物であることが報告されている6,9。
これらの急性気道感染症の原因微生物であるウイルスに、慢性心疾患や慢性肺疾患がある高齢者が罹患した場合には、ウイルス性気道感染症であっても呼吸困難を伴いやすく、入院が必要になることも稀ではないことが示唆されている10,11。
注3 国際疾病分類第10版(ICD10)においてJ00~J06に分類される疾病。
なお、乳幼児における急性気道感染症は、訴えや所見を正確に評価することが難しく、また、特殊な病型としてクループ症候群や細気管支炎等が含まれるため、成人と同様に分類することは難しく、さらに、発熱を認めた場合には菌血症や尿路感染症等に対する配慮が必要と指摘されていること12から、本手引きでは、小児の急性気道感染症に係る記載に関しては、学童期以降の小児を対象とする。
学童期以降の小児における急性気道感染症の疫学は成人に類する13,14が、感冒後の二次性細菌性感染症やマイコプラズマ肺炎の危険性15,16、GASによる感染症の所見17、小児特有の薬剤における危険性18等に配慮が必要と指摘されている。
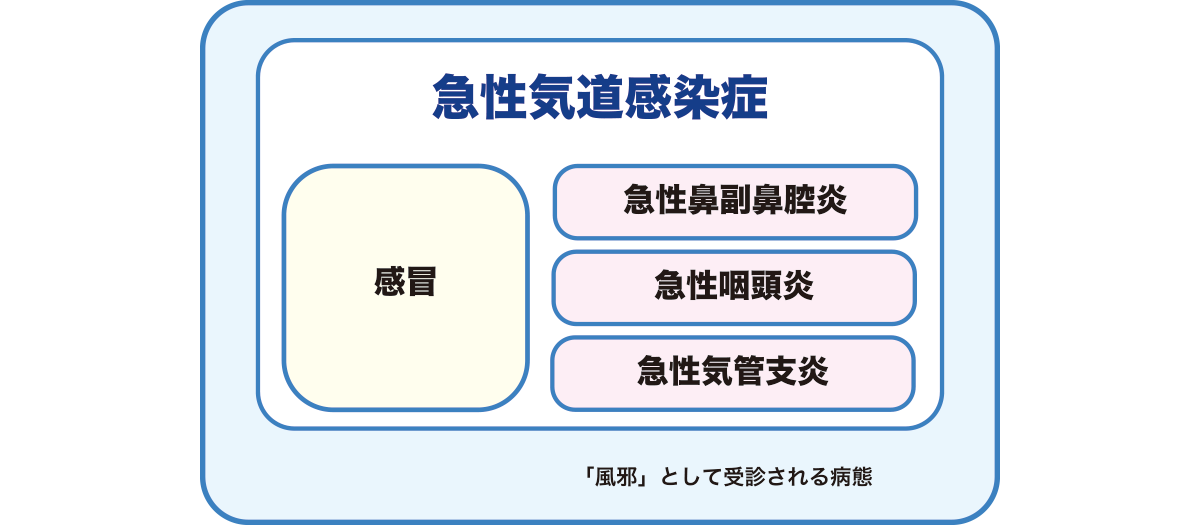
図1. 本手引きで扱う急性気道感染症の概念と区分注5
(3) 急性気道感染症の診断方法及び鑑別疾患
急性気道感染症において、抗菌薬が必要な症例と不必要な症例を見極めるために有用な分類として、ACPによる分類が知られている3,19-21。これは急性気道感染症を鼻症状(鼻汁、鼻閉)、咽頭症状(咽頭痛)、下気道症状(咳、痰)の3系統の症状によって、感冒(非特異的上気道炎、普通感冒)、急性鼻副鼻腔炎、急性咽頭炎、急性気管支炎の4つの病型に分類するものである(表1)。本手引きでも、この分類に基づいて解説を行う。なお、肺炎に関しては、本手引きの範囲を超えているため成書を参照頂きたい。
注5 「急性気道感染症」内の4つの語句の定義としては、Ann Intern Med. 2016;164:425-34.におけるAcute Bronchitis、Pharyngitis、Acute Rhinosinusitis、Common Coldの定義を準用した。
表1. 急性気道感染症の病型分類 文献3, 20より改変
| 病型 | 鼻汁・鼻閉 | 咽頭痛 | 咳・痰 |
|---|---|---|---|
| 感冒 | △ | △ | △ |
| 急性鼻副鼻腔炎 | ◎ | × | × |
| 急性咽頭炎 | × | ◎ | × |
| 急性気管支炎 | × | × | ◎ |
◎:主要症状、△:際立っていない程度で他症状と併存、×:症状なし~軽度
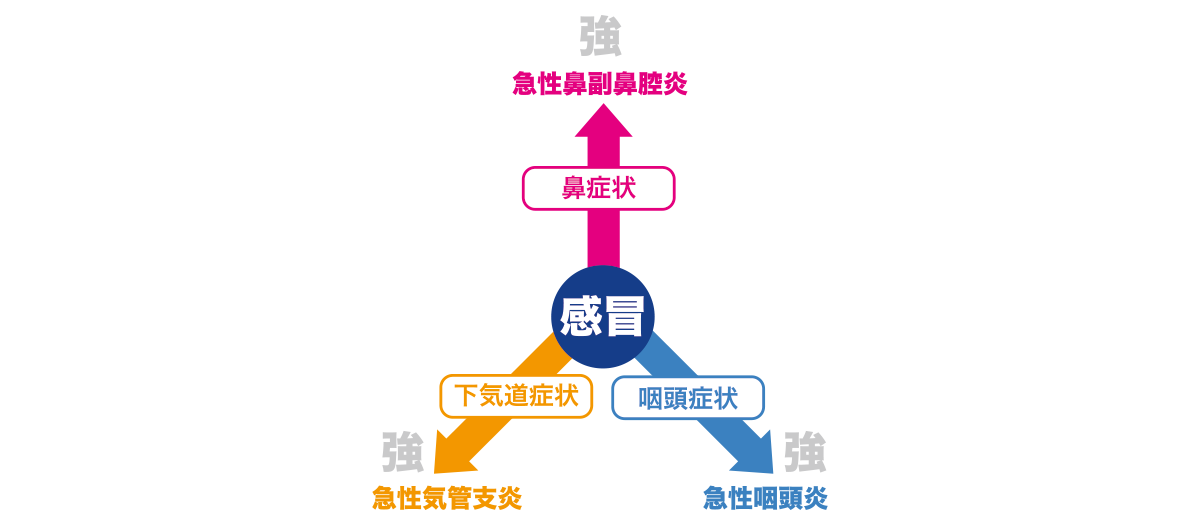 図2. 急性気道感染症の病型分類のイメージ
図2. 急性気道感染症の病型分類のイメージ
(i) 感冒
発熱の有無は問わず、鼻症状(鼻汁、鼻閉)、咽頭症状(咽頭痛)、下気道症状(咳、痰)の3系統の症状が「同時に」、「同程度」存在する病態(表1)を有するウイルス性の急性気道感染症を、本手引きでは感冒に分類する。すなわち、非特異的上気道炎や普通感冒と表記される病態についても、本手引きでは、感冒と分類する。
感冒の自然経過は、典型的には、まず微熱や倦怠感、咽頭痛を生じ、続いて鼻汁や鼻閉、その後に咳や痰が出てくるようになり、発症から3日目前後を症状のピークとして、7-10日間で軽快していくと指摘されている23。感冒では、咳は3週間ほど続くこともあるが、持続する咳が必ずしも抗菌薬を要するような細菌感染の合併を示唆するとは限らないことが指摘されている23。一方、通常の自然経過から外れて症状が進行性に悪化する場合や、一旦軽快傾向にあった症状が再増悪した場合には、二次的な細菌感染症が合併している場合があるとも指摘されている21。
なお、抗ウイルス薬の適応がありうるインフルエンザについては、高熱、筋肉痛、関節痛といった全身症状が比較的強く、咳が出る頻度が高いことに加えて、感冒と比較して発症後早期から咳が出ることが多く、また、鑑別に迷う場合には検査として迅速診断キットも使用可能となっている22,24,25。
COVID-19に関しては、咽頭痛、鼻汁・鼻閉といった上気道症状に加え、倦怠感、発熱、筋肉痛といった全身症状を生じることが多い。インフルエンザに類似しており、臨床症状のみから両者を鑑別することは困難であることから、地域の流行状況によっては、発熱や呼吸器症状を呈する患者を診る場合、インフルエンザと両方の可能性を考慮し、同時に検査する場合もあると考えられる。COVID-19を疑う患者、もしくはCOVID-19と診断した患者の診療の詳細については、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部が発出している「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」の最新版を参考にされたい。
(ii) 急性鼻副鼻腔炎
発熱の有無を問わず、くしゃみ、鼻汁、鼻閉を主症状とする病態を有する急性気道感染症を、本手引きでは、急性鼻副鼻腔炎に分類する。副鼻腔炎はほとんどの場合、鼻腔内の炎症を伴っていること、また、鼻炎症状が先行することから、最近では副鼻腔炎の代わりに鼻副鼻腔炎と呼ぶことが多いとされている26。
急性ウイルス性上気道感染症のうち、急性細菌性鼻副鼻腔炎を合併する症例は2%未満と報告されている27,28。鼻汁の色だけではウイルス感染症と細菌感染症との区別はできないとされる29が、症状が二峰性に悪化する場合には細菌感染症を疑う必要があるとも指摘されている22,30。
(iii) 急性咽頭炎
喉の痛みを主症状とする病態を有する急性気道感染症を、本手引きでは、急性咽頭炎に分類する。なお、本手引きでは、急性扁桃炎は、急性咽頭炎に含まれることとする。このような病態を有する症例の大部分の原因微生物はウイルスであり、抗菌薬の適応のあるA群β溶血性連鎖球菌(GAS)による症例は成人においては全体の10%程度と報告されている17,31,32が、その一方で、日本で行われた研究では、20-59歳の急性扁桃炎患者の約30%33、小児の急性咽頭炎患者の約17%34がGAS陽性であったとも報告されている。一般的にGASによる急性咽頭炎は、学童期の小児で頻度が高く、乳幼児では比較的稀であるとされる17,31,35が、咽頭培養から検出されるGASのすべてが急性咽頭炎の原因微生物ではなく、無症状の小児の20%以上にGAS保菌が認められうるとも報告されている36。近年、GAS以外のC群やG群β溶血性連鎖球菌やFusobacterium属も急性咽頭炎・扁桃炎の原因になる可能性が欧米の調査では指摘されているが、日本での疫学的な調査は少ないとされている37-45。
GASによる咽頭炎の可能性を判断する基準としては、Centorの基準又はその基準に年齢補正を追加したMcIsaacの基準(表2)が知られている46,47。Centorの基準及びMcIsaacの基準の点数に応じた迅速抗原検査や抗菌薬投与の推奨は様々17,21,48,49であるが、ACP/CDC及びESCMIDの指針では、Centorの基準2点以下ではGAS迅速抗原検査は不要と指摘されている21,48。ただし、GASを原因とする咽頭炎患者への最近の曝露歴がある50等、他にGASによる感染を疑う根拠があれば、合計点が2点以下でも迅速抗原検査を考慮してもよいと考えられている。抗菌薬処方を迅速抗原検査又は培養検査でGASが検出された場合のみに限ると、不要な抗菌薬使用を減らすことができ46、費用対効果も高いこと51が報告されている。
一方、小児ではCentorの基準で最も高い4点の陽性率ですら68%であったと報告されており52、Centorの基準やMcIsaacの基準の点数のみで小児の急性咽頭炎の原因微生物がGASであると判断した場合には過剰診断につながる可能性があることから、より正確な診断のために検査診断が必要になる。
表2. McIsaacの基準 文献46, 47より作成
| 発熱 38℃以上 | 1点 | |
|---|---|---|
| 咳がない | 1点 | |
| 圧痛を伴う前頚部リンパ節腫脹 | 1点 | |
| 白苔を伴う扁桃腺炎 | 1点 | |
| 年齢 | 3-14歳 | 1点 |
| 15-44歳 | 0点 | |
| 45歳- | -1点 | |
急性咽頭炎の鑑別診断としては、EBウイルス(EBV)、サイトメガロウイルス(CMV)、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)、風疹ウイルス、トキソプラズマを原因微生物とする伝染性単核症があるが、伝染性単核症の患者では、前述のCentorの基準やMcIsaacの基準で容易に高得点になるため、これらの基準を用いても伝染性単核症の鑑別ができないと指摘されている53。ただし、GASによる咽頭炎では前頸部リンパ節が腫脹するが、伝染性単核症では耳介後部や後頸部リンパ節の腫脹や脾腫が比較的特異性の高い所見であり54、また、血液検査でリンパ球分画が35%以上あれば、伝染性単核症の可能性が高くなることも報告されている55。
咽頭痛を訴える患者では、急性喉頭蓋炎、深頸部膿瘍(扁桃周囲膿瘍、咽後膿瘍、Ludwigアンギーナ等)、Lemierre症候群等の命に関わる疾病が原因である可能性もあることから、人生最悪の喉の痛み、開口障害、唾を飲み込めない(流涎)、Tripod Position(三脚のような姿勢)、吸気性喘鳴(Stridor)といったRed Flag(危険症候)注 があればこれらの疾病を疑い、緊急気道確保ができる体制を整えるべきと指摘されている56,57。特に小児の場合は、口腔内の診察や、採血、レントゲン撮影等により啼泣させることによって気道閉塞症状が急速に増悪する可能性があることから、これらの疾病を疑った場合には、患者を刺激するような診察、検査は避け、楽な姿勢のままで、安全に気道確保できる施設へと速やかに搬送することが重要と考えられている49。さらに、嚥下痛が乏しい場合や、咽頭や扁桃の炎症所見を伴っていないにもかかわらず咽頭痛を訴える場合は、頸部への放散痛としての「喉の痛み」の可能性があり、急性心筋梗塞、くも膜下出血、頸動脈解離、椎骨動脈解離等を考慮する必要があると指摘されている56,57。
注6 Red Flag(レッドフラッグ、危険症候)とは、診療を進める上において見過ごしてはならない症候をいう。
(iv) 急性気管支炎
発熱や痰の有無を問わず、咳を主症状とする病態を有する急性気道感染症を、本手引きでは急性気管支炎に分類する。急性気道感染症による咳は2-3週間続くことも少なくなく、平均17.8日間注 持続すると報告されている58。
急性気管支炎の原因微生物は、ウイルスが90%以上を占め、残りの5-10%は百日咳菌、マイコプラズマ、クラミジア・ニューモニエであると指摘されている21,59が、膿性喀痰や喀痰の色の変化では、細菌性であるかの判断はできないと指摘されている21。なお、基礎疾患がない70歳未満の成人では、バイタルサイン(生命兆候)の異常(体温38℃以上、脈拍100回/分以上、呼吸数24回/分以上)及び胸部聴診所見の異常がなければ、通常、胸部レントゲン撮影は不要と指摘されている21。
百日咳については、特異的な臨床症状はないことから、臨床症状のみで診断することは困難とされる60が、咳の後の嘔吐や吸気時の笛声(inspiratory whoop)があれば百日咳の可能性が若干高くなることが報告されている60。また、百日咳の血清診断(抗PT抗体)は、迅速性に欠けるため、臨床現場では使いにくいとされる61,62が、2016年11月に保険収載された後鼻腔ぬぐい液のLAMP(Loop−mediated isothermal amplification)法による百日咳菌の核酸検出法では、リアルタイムPCR法を参照基準にした場合の感度は76.2-96.6%、特異度は94.1-99.5%であることが報告されている63,64。これらのことから、流行状況に応じて、強い咳が長引く場合や、百日咳の患者への接触後に感冒症状が生じた場合には、百日咳に対する臨床検査を考慮する必要がある。
その他に鑑別が必要な疾患としては、結核が挙げられる。咳が2-3週間以上続く場合、日本では未だ罹患率の高い結核の可能性を考慮する必要がある。
なお、小児の場合、2週間以上湿性咳が遷延し改善しない症例については、抗菌薬の適応のある急性鼻副鼻腔炎の可能性があること30、また、マイコプラズマに感染した学童期の小児のうち10%は肺炎に移行する可能性があることが指摘されている16。さらに、日本小児呼吸器学会・日本小児感染症学会の指針では、1歳以上の小児において1週間以上続く咳の鑑別として、特徴的な「吸気性笛声」「発作性の連続性の咳こみ」「咳こみ後の嘔吐」「息詰まり感、呼吸困難」のうち1つ以上を有する症例を臨床的百日咳と定義されており65、患者を経時的に診るという視点が重要である。
以上の急性気道感染症の診断の流れをまとめると図3のようになる。
注7 研究によって15.3~28.6日間と幅がある。
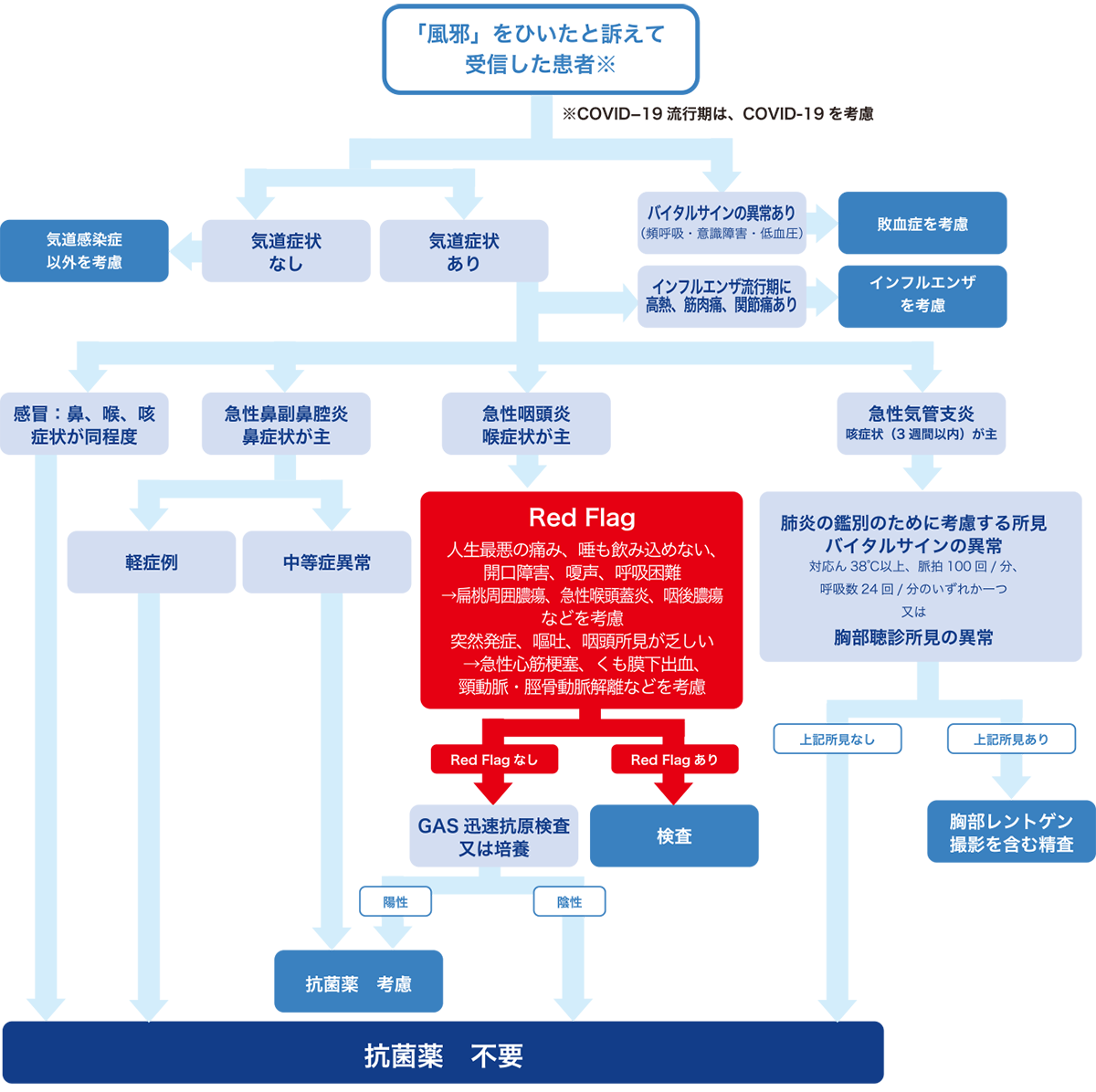
図3. 急性気道感染症の診断及び治療の手順
※ 本図は診療手順の目安として作成されたものであり、実際の診療では診察した医師の判断が優先される。
(4) 治療方法
(i) 感冒
- 感冒に対しては、抗菌薬投与を行わないことを推奨する。
日本呼吸器学会、日本小児呼吸器学会・日本小児感染症学会及びACP/CDCの指針では、感冒はウイルスによって引き起こされる病態であることから、抗菌薬投与は推奨しないとされている2,21,65。また、感冒に抗菌薬を処方しても治癒が早くなることはなく、成人では抗菌薬による副作用(嘔吐、下痢、皮疹等)が偽薬群(プラセボ群)と比べて2.62倍(95%信頼区間 1.32-5.18倍)多く発生することが報告されている66。
このようなことから、本手引きでは、感冒に対しては、抗菌薬投与を行わないことを推奨する。
(ii) 急性鼻副鼻腔炎
- 成人では、軽症※の急性鼻副鼻腔炎に対しては、抗菌薬投与を行わないことを推奨する。
- 成人では、中等症又は重症※の急性鼻副鼻腔炎に対してのみ、以下の抗菌薬投与を検討することを推奨する。
(成人における基本) アモキシシリン5-7日間経口投与- 学童期以降の小児では、急性鼻副鼻腔炎に対しては、遷延性又は重症の場合※※を除き、抗菌薬投与を行わないことを推奨する。
- 学童期以降の小児の急性鼻副鼻腔炎に対して、遷延性又は重症の場合※※には、抗菌薬投与を検討することを推奨する。
(小児における基本) アモキシシリン7-10日間経口投与
※ 重症度については、表3を元に分類を行うこととする。
※※ 具体的には表4を参照。
表3. 急性鼻副鼻腔炎の重症度分類 文献67, 68より作成
| なし | 軽度/少量 | 中等以上 | ||
|---|---|---|---|---|
| 臨床症状 | 鼻漏 | 0 | 1 | 2 |
| 顔面痛・前頭部痛 | 0 | 1 | 2 | |
| 鼻腔所見 | 鼻汁・後鼻漏 | 0 (漿液性) |
2 (粘膿性少量) |
4 (粘液性中等量以上) |
軽症:1-3点、中等症:4-6点、重症:7-8点
表4. 小児の急性鼻副鼻腔炎に係る判定基準 文献69より作成
以下のいずれかに当てはまる場合、遷延性又は重症と判定する。
- 10日間以上続く鼻汁・後鼻漏や日中の咳を認めるもの。
- 39℃以上の発熱と膿性鼻汁が少なくとも3日以上続き重症感のあるもの。
- 感冒に引き続き、1週間後に再度の発熱や日中の鼻汁・咳の増悪が見られるもの。
急性鼻副鼻腔炎に関しては、細菌性鼻副鼻腔炎が疑わしい場合でも、抗菌薬投与の有無に関わらず、1週間後には約半数が、2週間後には約7割の患者が治癒することが報告されている70。また、抗菌薬投与群では偽薬群(プラセボ群)に比べて7-14日目に治癒する割合は高くなるものの、副作用(嘔吐、下痢、腹痛)の発生割合も高く、抗菌薬投与は欠点が利点を上回る可能性があることが報告されている70。同様に、鼻炎症状が10日間未満の急性鼻炎では、鼻汁が膿性であるか否かに関わらず、抗菌薬の効果は偽薬群(プラセボ群)よりも優れているとは言えず、副作用の発生は1.46倍(95%信頼区間 1.10-1.94倍)多くなると報告されている66。
ACP/CDCの指針では、急性鼻副鼻腔炎に対する抗菌薬の適応は、症状が10日間を超える場合や重症例の場合(39℃以上の発熱がある場合、膿性鼻汁や顔面痛が3日間以上続く場合)、典型的なウイルス性疾患で症状が5日間以上続き、一度軽快してから悪化した場合に限定されている21。日本鼻科学会やJAID/JSCの指針でも、表2に示す軽症例(1-3点の症例)では抗菌薬を投与せずに経過観察することが推奨されている49,67,68。
このようなことから、本手引きでは、成人では、軽症の急性鼻副鼻腔炎に対しては、抗菌薬投与を行わないことを推奨する。
また、米国小児科学会の指針では、小児の急性鼻副鼻腔炎に対する抗菌薬の適応を、表4に示す①10日間以上続く鼻汁・後鼻漏や日中の咳を認めるもの、②39℃以上の発熱と膿性鼻汁が少なくとも3日以上続き重症感のあるもの、③感冒に引き続き、約1週間後に再度の発熱や日中の鼻汁・咳の増悪が見られるものと定められており、それ以外の状況では抗菌薬投与を行わずに経過観察することが推奨されている69。
このことから、本手引きでは、小児では、急性鼻副鼻腔炎に対しては、原則抗菌薬投与を行わないことを推奨する。
急性鼻副鼻腔炎の抗菌薬治療において、アモキシシリン及びクラブラン酸/アモキシシリンより、セファロスポリン系抗菌薬、マクロライド系抗菌薬の方が、治療効果が上回ることを示した系統的レビューや無作為化比較試験は存在しないとされる71,72が、米国耳鼻咽喉科・頭頸部外科学会やACP/CDCの指針では、中等症以上の急性鼻副鼻腔炎で抗菌薬の適応がある場合には、安全性や有効性、費用、対象とする細菌の種類の狭さからアモキシシリンが第一選択薬として推奨されており21,72、同指針では、その時の用量等は、アモキシシリン 1回500 mg注 を1日3回5-7日間経口投与とされている21。また、同指針では、耐性菌である危険性が高い症例や一次治療不応例ではクラブラン酸/アモキシシリンを選択することとされており、この時の用量等は、クラブラン酸/アモキシシリン1回375 mgとアモキシシリン1回250 mgを、1日3回5-7日間経口投与することが示されている21。
抗菌薬を用いる治療期間については、従来は10-14日間が推奨されてきた64が、近年の研究では、短期間(3-7日間)の治療は長期間(6-10日間)の治療に対して有効性は劣らず、さらに、5日間治療と10日間治療を比較した場合、有効性は同等で、副作用は5日間治療の方が少ないことが報告されている73。
日本では、アモキシシリンの鼻副鼻腔炎に対する効能・効果は薬事承認されていないが、社会保険診療報酬支払基金の審査情報提供事例において、原則として、「アモキシシリン水和物【経口】を「急性副鼻腔炎」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める」ことが示されている。また、添付文書では、急性副鼻腔炎に対して設定されたものではないが、アモキシシリンの用法・用量は、ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症に対して、成人では、「アモキシシリン水和物として、通常1回250 mg(力価)を1日3-4回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。」とされている。
注8 本手引きでは、薬剤の用量について、製剤量ではなく成分量(力価)で示した。
このようなことから、本手引きでは、成人に関して、表3に示す中等症又は重症の急性鼻副鼻腔炎に対してのみ、抗菌薬投与を検討することを推奨することとし、その際には、アモキシシリンを第一選択薬として5-7日間経口投与することとする。
海外の指針では、成人でβ-ラクタム系抗菌薬(ペニシリン系抗菌薬、セファロスポリン系抗菌薬、カルバペネム系抗菌薬及びペネム系抗菌薬)にアレルギーがある場合には、テトラサイクリン系抗菌薬やフルオロキノロン系抗菌薬を投与することが推奨されている30,72が、日本では、細菌性鼻副鼻腔炎の主要な原因微生物である肺炎球菌のテトラサイクリン系抗菌薬に対する耐性率が高いことが報告されており74、このような症例については専門医に相談することも考慮する必要がある。
小児の用法・用量については、添付文書では「アモキシシリン水和物として、通常1日20-40 mg(力価)/kgを3-4回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日量として最大90 mg(力価)/kgを超えないこと。」と記載されている。また、各学会の指針では、急性鼻副鼻腔炎に対して抗菌薬を用いる場合、アモキシシリンが第一選択薬として推奨されている49,67,69。
このようなことから、本手引きでは、小児の急性鼻副鼻腔炎に対して、表4に示す遷延性又は重症の場合には、抗菌薬投与を検討することを推奨することとし、その際には、アモキシシリンを第一選択薬として7-10日間経口投与することとする。
(iii) 急性咽頭炎
- 迅速抗原検査又は培養検査でA群β溶血性連鎖球菌(GAS)が検出されていない急性咽頭炎に対しては、抗菌薬投与を行わないことを推奨する。
- 迅速抗原検査又は培養検査でGASが検出された急性咽頭炎に対して抗菌薬を投与する場合には、以下の抗菌薬投与を検討することを推奨する。
(成人・小児における基本)アモキシシリン10日間経口投与
急性咽頭炎に関しては、ACP/CDC及びIDSAの指針では、急性咽頭炎の多くはウイルスによって引き起こされる病態であることから、迅速抗原検査又は培養検査でA群β溶血性連鎖球菌(GAS)が検出されていない急性咽頭炎に対しては、抗菌薬投与は推奨しないとされている17,21。なおFusobacterium属等の嫌気性菌、C群又はG群β溶血性連鎖球菌の関与する急性咽頭炎に対して抗菌薬を投与すべきか否かについては一致した見解がない注 とされている57,75。
これらのことから、本手引きでは、迅速抗原検査又は培養検査でGASが検出されていない急性咽頭炎に対しては、抗菌薬投与を行わないことを推奨する。
成人のGASによる急性咽頭炎に対する治療として、セファロスポリン系抗菌薬投与群とペニシリン系抗菌薬投与群とを比較した研究では、症状軽快について統計学的有意差はないこと(オッズ比 0.78倍 95%信頼区間 0.60-1.01倍)が報告されている76。また、臨床的に再度増悪する症例については、セファロスポリン系抗菌薬投与群の方が統計的に有意に少なかった(オッズ比0.42倍 95%信頼区間 0.20-0.88倍)ものの、治療必要数(NNT)注 は33と絶対リスク差は大きくないことが報告されている76。これらの安全性、有効性及び抗菌薬としての狭域性等も踏まえ、各学会の指針ではペニシリン系抗菌薬が第一選択薬として推奨されている17,21,49。アモキシシリンの添付文書では「1回250 mgを1日3-4回経口投与する。ただし、年齢、体重、症状等に応じて適宜増減する。」と記載されている。なお、各学会の指針では、GASによる急性咽頭炎の場合の用量はアモキシシリン1回1,000 mgを1日1回又は1回500 mgを1日2回とされている17,21。治療期間については、短期間治療の有効性を支持する科学的知見は乏しく、欧米の学会の指針では10日間の治療が推奨されている17,48。
IDSAの指針では、軽症のペニシリンアレルギーがある場合には、経口第1世代セファロスポリン系抗菌薬のセファレキシンが、重症のペニシリンアレルギー(アナフィラキシーや重症薬疹の既往)がある場合には、クリンダマイシンが推奨されている17。日本では、セファレキシン及びクリンダマイシンは咽頭炎を適応症として薬事承認されており、それぞれの薬剤について、「通常、成人及び体重20 kg以上の小児にはセファレキシンとして 1 回250 mg(力価)を6時間ごとに経口投与する。重症の場合や分離菌の感受性が比較的低い症例には1回500 mg(力価)を6時間ごとに経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。」、また、「通常、成人はクリンダマイシン塩酸塩として1回150 mg(力価)を6時間ごとに経口投与、重症感染症には1回300 mg(力価)を8時間ごとに経口投与する。小児には体重1 kgにつき、1日量15 mg(力価)を3-4回に分けて経口投与、重症感染症には体重1 kgにつき1日量20 mg(力価)を3-4回に分けて経口投与する。ただし、年齢、体重、症状等に応じて適宜増減する。」とされている。なお、IDSAの指針では、軽症のペニシリンアレルギーがある場合にセファレキシンは1回500 mgを1日2回が、重症のペニシリンアレルギーがある場合にクリンダマイシンは1回300 mg 1日3回が推奨されている17。
このようなことから、本手引きでは、迅速抗原検査又は培養検査でGASが検出された急性咽頭炎に対して抗菌薬投与を検討することを推奨することとし、その際には、アモキシシリンを10日間経口投与することとする。
小児についても、日本小児呼吸器学会・日本小児感染症学会の指針では、GASによる急性咽頭炎に対してはアモキシシリンが第一選択抗菌薬とされており、10日間の治療期間が推奨されている65。小児のGAS咽頭炎に対する抗菌薬として、ペニシリン系抗菌薬10日間(対照群)とペニシリン系抗菌薬以外の抗菌薬4-6日(短期治療群)の治療を比較した研究によると、短期治療群で症状消失は有意に早いものの再燃率は高かったことが報告されている77。また、この研究では、副作用についてはペニシリン系抗菌薬群の方が少なく、リウマチ熱・腎炎の合併率については有意な差はなかったと報告されている77。アモキシシリン10日間及びセファロスポリン系抗菌薬5日間を用いた、GASによる急性咽頭炎後の除菌率及び再発率を比較した日本における研究によると、除菌率は有意にアモキシシリン治療群で高く(アモキシシリン治療群91.7%、セファロスポリン系抗菌薬治療群82.0%、p=0.01)、再発率に差はなかったことが報告されている78。
このようなことから、本手引きでは、小児においても、迅速抗原検査又は培養検査でGASが検出された急性咽頭炎に対して抗菌薬投与を検討することを推奨することとし、その際には、アモキシシリンを10日間経口投与することとする。
なお、前述のように、急性咽頭炎の鑑別診断については、緊急度・重症度が高い疾患を含めて多岐に渡るため、急性咽頭炎を疑った時にはGASによる急性咽頭炎のみを念頭に置かないように注意する必要があり、また、遷延する咽頭炎の症例については専門医への相談も考慮する必要があると考えられる。
注9 C群又はG群β溶血性連鎖球菌による劇症型溶血性レンサ球菌感染症(疑いを含む)についてはこの限りではないとされている。
注10 治療必要数(NNT)とは:一つの結果が起こるのを防ぐために必要な治療を受ける患者数のこと。
(iv) 急性気管支炎
- 慢性呼吸器疾患等の基礎疾患や合併症のない成人の急性気管支炎(百日咳を除く)に対しては、抗菌薬投与を行わないことを推奨する
急性気管支炎に関しては、一律の抗菌薬使用には利点が少なく、利点よりも副作用の危険性が上回ることが報告されており79、JAID/JSC及びACP/CDCの指針でも、慢性呼吸器疾患等の基礎疾患や合併症のない急性気管支炎の患者に対する抗菌薬投与は基本的には推奨されていない21,59。また、成人の肺炎を伴わないマイコプラズマによる急性気管支炎に対する抗菌薬治療については、その必要性を支持する根拠に乏しいと指摘されている21,59。
このようなことから、本手引きでは、成人の百日咳を除く急性気管支炎に対しては、抗菌薬投与を行わないことを推奨する。ただし、前述のように、学童期の小児については、肺炎への移行の可能性も考慮して、患者を経時的に診るという視点が重要である。特に、小児のマイコプラズマに対するマクロライド系抗菌薬投与については各指針で推奨されており14,65,80、マイコプラズマやクラミジア・ニューモニエに関連して数週間遷延する咳又は難治性の咳についてはマクロライド系抗菌薬の有用性が報告されている81,82。ただし、慢性呼吸器疾患や合併症のある成人で、発熱、膿性痰を認める場合は、喀痰のグラム染色を実施して細菌感染の有無を確認し、グラム染色所見で細菌感染が疑われる場合には抗菌薬を投与することが望ましい。
百日咳については、カタル期(発症から2週間程度)を過ぎてからの治療は自覚症状の改善には寄与しないが、1歳以上では発症から3週間以内の治療は周囲への感染の防止には寄与しうることが指摘されている59,83。JAID/JSC及びCDCの指針では、百日咳に対してはマクロライド系抗菌薬が第一選択薬とされており、成人に対する治療期間については、アジスロマイシンは初日500 mg、2日目以降250 mg/日で計5日間の投薬、又はアジスロマイシン1回500 mgを1日1回経口投与、計3日間が標準的とされている59,83,84。ただし、添付文書では、小児用クラリスロマイシンとエリスロマイシンについては百日咳が適応症として含まれている一方で、アジスロマイシンについては百日咳が適応症には含まれていないが、保険審査上は認められる84。この時のエリスロマイシンの用法・用量は、「通常、成人にはエリスロマイシンとして1日800-1,200 mg(力価)を4-6回に分割経口投与する。小児には1日体重1 kgあたり25-50 mg(力価)を4-6回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。ただし、小児用量は成人量を上限とする。」とされている。
(5) 患者・家族への説明
急性気道感染症の診療における患者への説明で重要な要素としては表5のようなものが示されている86-88。これらの要素を踏まえた保健指導を行う訓練を受けた医師は、受けなかった医師と比べて、有害事象を増やすことなく、抗菌薬の処方を30-50%減らすことができたことが報告されている87,88。
表5. 急性気道感染症の診療における患者への説明で重要な要素 文献86-88から作成
| 1) 情報の収集 |
|
|---|---|
| 2) 適切な情報の提供 |
|
| 3) まとめ |
|
患者及び家族への説明の際、「ウイルス感染症です。特に有効な治療はありません」、「抗菌薬は必要ありません」という否定的な説明のみでは不満を抱かれやすい89,90が、その一方で、例えば「症状を和らげる薬を出しておきますね」「暖かい飲み物を飲むと鼻づまりがラクになりますよ」といった肯定的な説明は受け入れられやすいことが指摘されている91。肯定的な説明のみを行った場合、否定的な説明のみ行った場合、両方の説明を行った場合の三者を比較すると、両方の説明を行った方が抗菌薬の処方は少なく、患者の満足度も高かったということが報告されている91。否定的な説明だけでなく、肯定的な説明を行うことが患者の満足度を損なわずに抗菌薬処方を減らし、良好な医師-患者関係の維持・確立にもつながると考えられている91。
また、近年、急性気道感染症における抗菌薬使用削減のための戦略として、Delayed Antibiotics Prescription(DAP:抗菌薬の延期処方)に関する科学的知見が集まってきている注 。初診時に抗菌薬投与の明らかな適応がない急性気道感染症の患者に対して、その場で抗菌薬を処方するのではなく、その後の経過が思わしくない場合にのみ抗菌薬を投与すると、合併症や副作用、予期しない受診等の好ましくない転帰を増やすことなく抗菌薬処方を減らすことができることが報告されている92-94。
注11 参考資料(2)を参照のこと。
例えば、感冒は、微熱や倦怠感、咽頭痛等から始まり、1-2日遅れて鼻汁や鼻閉、咳、痰を呈し、3日目前後に症状は最大となり、7-10日にかけて徐々に軽快していくという自然経過を示す13が、一度軽快に向かったものが、再度悪化するような二峰性の悪化が見られた場合には、細菌感染の合併を考慮することが重要と指摘されている56,57。
このように、初診時に抗菌薬投与の明らかな適応がない場合には、経過が思わしくない場合の具体的な再診の指示について患者に伝えておくことが重要である。
【医師から患者への説明例:感冒の場合】
あなたの「風邪」は、診察した結果、ウイルスによる「感冒」だと思います。つまり、今のところ、抗生物質(抗菌薬)が効かない「感冒」のタイプのようです。症状を和らげるような薬をお出ししておきます。こういう場合はゆっくり休むのが一番の薬です。
普通、最初の2-3日が症状のピークで、あとは1週間から10日間かけてだんだんと良くなっていくと思います。
ただし、色々な病気の最初の症状が一見「風邪」のように見えることがあります。また、数百人に1人くらいの割合で「風邪」の後に肺炎や副鼻腔炎等、バイ菌による感染が後から出てくることが知られています。
3日以上たっても症状が良くなってこない、あるいはだんだん悪くなってくるような場合や、食事や水分がとれなくなった場合は、血液検査をしたりレントゲンを撮ったりする必要がでてきますので、もう一度受診するようにしてください。
【医師から患者への説明例:急性鼻副鼻腔炎疑いの場合】
あなたの「風邪」は、鼻の症状が強い「急性鼻副鼻腔炎」のようですが、今のところ、抗生物質(抗菌薬)が必要な状態ではなさそうです。抗生物質により吐き気や下痢、アレルギー等の副作用が起こることもあり、抗生物質の使用の利点が少なく、抗生物質の使用の利点よりも副作用のリスクが上回ることから、今の状態だと使わない方がよいと思います。症状を和らげるような薬をお出ししておきます。
一般的には、最初の2-3日が症状のピークで、あとは1週間から10日間かけてだんだんと良くなっていくと思います。
今後、目の下やおでこの辺りの痛みが強くなってきたり、高い熱が出てきたり、いったん治まりかけた症状が再度悪化するような場合は抗生物質の必要性を考えないといけないので、その時にはまた受診してください。
【医師から患者への説明例:ウイルス性咽頭炎疑いの場合】
あなたの「風邪」は喉の症状が強い「急性咽頭炎」のようですが、症状からはおそらくウイルスによるものだと思いますので、抗生物質(抗菌薬)が効かないと思われます。抗生物質には吐き気や下痢、アレルギー等の副作用が起こることもあり、抗生物質の使用の利点が少なく、抗生物質の使用の利点よりも副作用のリスクが上回ることから、今の状態だと使わない方が良いと思います。痛みを和らげる薬をお出ししておきます。
一般的には、最初の2-3日が症状のピークで、あとは1週間から10日間かけてだんだんと良くなっていくと思います。3日ほど様子を見て良くならないようならまたいらしてください。
まず大丈夫だと思いますが、万が一、喉の痛みが強くなって水も飲み込めないような状態になったら診断を考え直す必要がありますので、すぐに受診してください。
【医師から患者への説明例:急性気管支炎患者の場合】
あなたの「風邪」は咳が強い「急性気管支炎」のようです。熱はないですし、今のところ肺炎を疑うような症状もありません。実は、気管支炎には抗生物質(抗菌薬)はあまり効果がありません。抗生物質により吐き気や下痢、アレルギー等の副作用が起こることもあり、抗生物質の使用の利点が少なく、抗生物質の使用の利点よりも副作用のリスクが上回ることから、今の状態だと使わない方が良いと思います。
咳を和らげるような薬をお出ししておきます。
残念ながら、このような場合の咳は2-3週間続くことが普通で、明日から急に良くなることはありません。咳が出ている間はつらいと思いますが、なんとか症状を抑えていきましょう。
1週間後くらいに様子を見せてください。もし眠れないほど咳が強くなったり、痰が増えて息苦しさを感じたり、熱が出てくるようなら肺炎を考えてレントゲンを撮ったり、診断を見直す必要が出てくるので、その場合は1週間たっていなくても受診してください。
【薬剤師から患者への説明例:抗菌薬が出ていない場合の対応例】
あなたの「風邪」には、医師による診察の結果、今のところ抗生物質(抗菌薬)は必要ないようです。むしろ、抗生物質の服用により、下痢等の副作用を生じることがあり、現時点では抗生物質の服用はお勧めできません。代わりに、症状を和らげるようなお薬が医師より処方されているのでお渡しします。
ただし、色々な病気の最初の症状が「風邪」のように見えることがあります。
3日以上たっても症状が良くなってこない、あるいはだんだん悪くなってくるような場合や、食事や水分がとれなくなった場合は、もう一度医療機関を受診するようにしてください。
※ 抗菌薬の処方の有無に関わらず、処方意図を医師が薬剤師に正確に伝えることで、患者への服薬説明が確実になり、患者のアドヒアランスが向上すると考えられている95-96。このことから、患者の同意を得て、処方箋の備考欄又はお薬手帳に病名等を記載することが、医師から薬剤師に処方意図が伝わるためにも望ましい。
5. 急性下痢症
(1) 急性下痢症とは
急性下痢症は、急性発症(発症から14日間以内)で、普段の排便回数よりも軟便又は水様便が1日3回以上増加している状態と定義されている97,98。急性下痢症の90%以上は感染性、残りの10%程度は薬剤性、中毒性、虚血性、その他非感染性であり、全身性疾患の一症状として下痢を伴うこともあると指摘されている99。感染性の急性下痢症は、吐き気や嘔吐、腹痛、腹部膨満、発熱、血便、テネスムス(しぶり腹。便意が頻回に生じること)等を伴うことがある98が、急性感染性下痢症は、「胃腸炎」や「腸炎」等とも呼ばれることがあり、中には嘔吐症状が際立ち、下痢の症状が目立たない場合もあることが指摘されている98。
(2) 急性下痢症の疫学
感染性胃腸炎の非流行期(2020年10月)に行った厚生労働省の患者調査では、腸管感染症注 の1日あたりの外来受療率は16(人口10万対)と報告している5。
急性下痢症の大部分はウイルス性であり100、冬季に流行するノロウイルスやロタウイルス等が代表例とされている101が、日本では2011年よりロタウイルスワクチンの任意接種が始まり、2020年には定期接種となった。ワクチンの任意接種開始後、基幹定点からの届出によるサーベイランスではロタウイルスによる下痢症は減少傾向にあったが102、定期接種化以降は、さらに激減して稀な疾患となった103。
急性下痢症の原因となりうる細菌としては、非チフス性サルモネラ属菌、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌、ビブリオが代表的であるとされる100が、海外からの帰国者の下痢症では腸管毒素原性大腸菌やカンピロバクターも多く、稀に赤痢菌やコレラ菌が検出されることもあること104、また、最近の抗菌薬投与歴がある場合にはクロストリディオイデス・ディフィシル腸炎を考慮する必要があること104も指摘されている。なお、腸チフス、パラチフスに関しては下痢を伴わないことが多いとされている105。
(3) 急性下痢症の診断方法及び鑑別疾患
急性下痢症の原因推定のための重要な情報としては、発症時期、随伴症状(発熱、腹痛、血便の有無)、疑わしい摂食歴、最近の海外渡航歴、抗菌薬投与歴、免疫不全の有無、同じような症状の者との接触歴等が挙げられており100、特に嘔吐が目立つ場合には、ウイルス性の感染症や毒素による食中毒の可能性が高いと指摘されている106。集団発生の場合、ウイルス性では潜伏期間が14時間以上(通常24-48時間)、食中毒では2-7時間のことが多く、両者の鑑別に役立つと指摘されている106。
吐き気や嘔吐は、消化器疾患以外(急性心筋梗塞、頭蓋内病変、敗血症、電解質異常、薬剤性等)でも伴うことがあるとされており107,108、急性胃腸炎の診断で入院した患者のうち約3割が腸管感染症以外の疾患であったとする報告もある109ことから、症状のみをもって「急性胃腸炎」と決めつけることは控える必要がある。
鑑別に際しては、下痢の性状(水様下痢と血性下痢のどちらであるか)及び下痢の重症度注 を考慮することが重要と指摘されている98。特に、日常生活に大きな支障のある重症の血性下痢で体温が38℃以上の場合や、動くことはできるが下痢のために活動が制限される中等症以上の水様下痢で海外(主に発展途上国)から帰国して約1週間以内の場合には、細菌性腸炎(腸チフス、サルモネラ腸炎、カンピロバクター腸炎、腸管毒素原性大腸菌等)やアメーバ赤痢である可能性を考慮98,110して、渡航医学や感染症の専門家に相談の上、検査と抗菌薬投与を含む治療を検討することが重要と指摘されている。
小児の場合でも、急性下痢症のほとんどがウイルスに起因すると指摘されている111。嘔吐で始まり、臍周囲の軽度から中等度の腹痛や圧痛がある、血便がなく水様下痢である、発熱がない(ないし微熱である)、激しい腹痛がない、家族や周囲の集団に同様の症状がある、といった場合には、ウイルス性の急性下痢症らしい症候であると指摘されている。一方で、血便が存在する場合には、腸管出血性大腸菌感染症等の細菌性腸炎の他、腸重積、メッケル憩室、上部消化管潰瘍等多くの疾患の鑑別が必要と指摘されている112,113。
注12 ICD10コードにおいてA00-A09をまとめたもの。
(i) ウイルスに起因する急性下痢症
ウイルスに起因する急性下痢症については、ロタウイルスの他に、成人ではノロウイルスが急性下痢症の代表的な原因微生物であると指摘されている100,106。汚染された加熱不十分な二枚貝の摂食により感染することが有名であるが、ヒトからヒトへの感染も少なくないことが報告されている114。ノロウイルス感染症の潜伏期間は通常、半日~2日程度であり、急な吐き気と嘔吐から始まることが多く、水様下痢の出現はそれよりもやや遅れると指摘されている115。嘔吐はほとんどの場合、約1日で治まり、下痢は多くの場合、2~3日間で軽快するが、長い人では7~10日間続くこともある116,117。発熱は伴わないか、発熱があっても2日間以内のことが多い116ため、2日間を超えて発熱が続く場合には単なるウイルス性の急性下痢症以外を考える必要がある。
ノロウイルスについては、便の迅速抗原検査が保険収載されており注 、その検査キットの感度については、最近では87.4~93.1%まで改善したことが報告されている118-121。しかしながら、ノロウイルスの流行期に典型的な急性下痢症の患者全員に対して迅速抗原検査を行うことは、検査陰性でもノロウイルス感染症の可能性が否定できないことから、意義が低いと考えられている。感染対策の観点からは、原因は問わず、吐物や排泄物は感染性があるものとして対処することが重要であり、迅速抗原検査が陰性だからといって感染対策が疎かになることは避けなければならない。
なお、小児の場合には、ノロウイルスの迅速抗原検査の保険適応は3歳未満とされている。
注13 下痢の重症度:軽症は、日常生活に支障のないもの、中等症は、動くことはできるが日常生活に制限のあるもの、重症は日常生活に大きな支障のあるもの。
注14 保険適用は、2023年10月現在、3歳未満の患者、65歳以上の患者、悪性腫瘍の診断が確定している患者、臓器移植後の患者、抗悪性腫瘍剤・免疫抑制剤又は免疫抑制効果のある薬剤を投与中の患者のいずれかに該当する場合に認められている。
(ii) 細菌に起因する急性下痢症
細菌による急性下痢症では、ウイルス性による急性下痢症と比べて腹痛が強く、高熱(38℃以上)、血便や粘血便、テネスムス(しぶり腹)を伴いやすいとされるが、身体所見は下痢の原因究明には役立たないことが多いとされており、表6に示すような疑わしい食品の摂食歴及び潜伏期間が原因微生物を推定する上である程度は役に立つと指摘されている116,122,123。
成人の細菌による急性下痢症は自然軽快するものが多いため、軽症例を含めた急性下痢症の患者全員に検査を行い、原因微生物を特定する意義は小さいとされるが、その一方で、中等症~重症例や、長引く下痢、抗菌薬を投与する症例等では、原因微生物の検出を目的として便培養検査を行うことが望ましいことも指摘されている92。
小児でも便培養検査を急ぐ必要のある症例は少なく、検査の適応となる症例には、細菌性腸炎が疑われる症例で、激しい腹痛や血便を呈する者、腸管出血性大腸菌から溶血性尿毒症症候群(Hemolytic Uremic Syndrome: HUS)が疑われるもの、免疫不全者等が挙げられている124。
表6. 感染性の急性下痢症及び食中毒の主な原因食品及び潜伏期間 文献116, 122, 123を参考に作成
| 原因微生物 | 国内で報告されている主な原因食品 | 潜伏期間 | |
|---|---|---|---|
| 毒素性 | セレウス菌 Bacillus cereus |
穀類及びその加工品(焼飯類、米飯類、麺類等)、複合調理食品(弁当類、調理パン)等 | 1-2時間 |
| 黄色ブドウ球菌 Staphylococcus aureus |
にぎりめし、寿司、肉・卵・乳等の調理加工品 及び菓子類等 |
2-6時間 | |
| ボツリヌス菌 Clostridium botulinum |
缶詰、瓶詰、真空パック食品、レトルト類似品、いずし等 | 18-36時間 | |
| 腸管毒素原性大腸菌 Enterotoxigenic E. coli |
特定の食品なし(途上国への旅行者に見られる 旅行者下痢症の主要な原因菌) |
12-72時間 | |
| 非毒素性 | ノロウイルス Norovirus |
牡蠣等の二枚貝 | 12-48時間 |
| 腸炎ビブリオ Vibrio parahaemolyticus |
魚介類(刺身、寿司、魚介加工品) | 2-48時間 | |
| エルシニア属菌 Yersinia enterocolitica |
加工乳、汚染された水、生の豚肉から二次的に 汚染された食品 |
2-144時間 | |
| ウェルシュ菌 Clostridium perfringens |
カレー、シチュー及びパーティ・旅館での複合調理食品 | 8-22時間 | |
| サルモネラ属菌 Salmonella spp. |
卵、食肉(牛レバー刺し、鶏肉)、うなぎ、 すっぽん等 |
12-48時間 | |
| 腸管出血性大腸菌 Enterohemorrhagic E. coli |
生や加熱不十分な牛肉 | 1-7日間 | |
| カンピロバクター・ジェジュニ Campylobacter jejuni |
生や加熱不十分な鶏肉、バーベキュー・焼き肉、牛レバー刺し | 2-7日間 | |
(4) 治療方法
- 急性下痢症に対しては、まずは水分摂取を励行した上で、基本的には対症療法のみ行うことを推奨する。
成人の急性下痢症では、ウイルス性、細菌性に関わらず自然軽快することが多く、脱水の予防を目的とした水分摂取の励行といった対症療法が重要と指摘されている98,100。バイタルサイン(生命兆候)や起立性低血圧の有無等により、脱水の程度を評価し、補液の必要性を検討することや可能な限り経口で水分摂取を行うこと98,100、経口での水分摂取に際しては、糖分、ナトリウム、カリウム等の電解質を含んだ飲料を摂取することが重要と指摘されている。重度脱水の乳幼児や高齢者では、成分調整した経口補水液(Oral Rehydration Solution: ORS)が推奨されているが、成人では、塩分含有量が少ない飲料の場合は適宜塩分摂取も必要とされるものの、多くの場合、果物ジュースやスポーツドリンク等の摂取で十分とされている98,125。
JAID/JSC、ACGの指針では、重症例又は海外渡航歴のある帰国者の急性下痢症(渡航者下痢症)である場合を除いて抗菌薬投与は推奨されておらず98,100、JAID/JSCの指針では、以下の場合には抗菌薬投与を考慮することとされている100。
- 血圧の低下、悪寒戦慄等、菌血症が疑われる場合
- 重度の下痢による脱水やショック状態等で入院加療が必要な場合
- 菌血症のリスクが高い場合(CD4陽性リンパ球数が低値のHIV感染症、ステロイド・免疫抑制剤投与中等、細胞性免疫不全者等)
- 合併症のリスクが高い場合(50歳以上、人工血管・人工弁・人工関節等)
- 渡航者下痢症
小児における急性下痢症の治療でも、抗菌薬を使用せず、脱水への対応を行うことが重要とされている112。
このようなことから、本手引きでは、急性下痢症に対しては、まずは水分摂取を励行した上で、基本的には対症療法のみ行うことを推奨する。
上記のような重症例や渡航者下痢症における具体的な治療法については成書を参照頂きたい。
診断及び治療の手順を図4に示す。
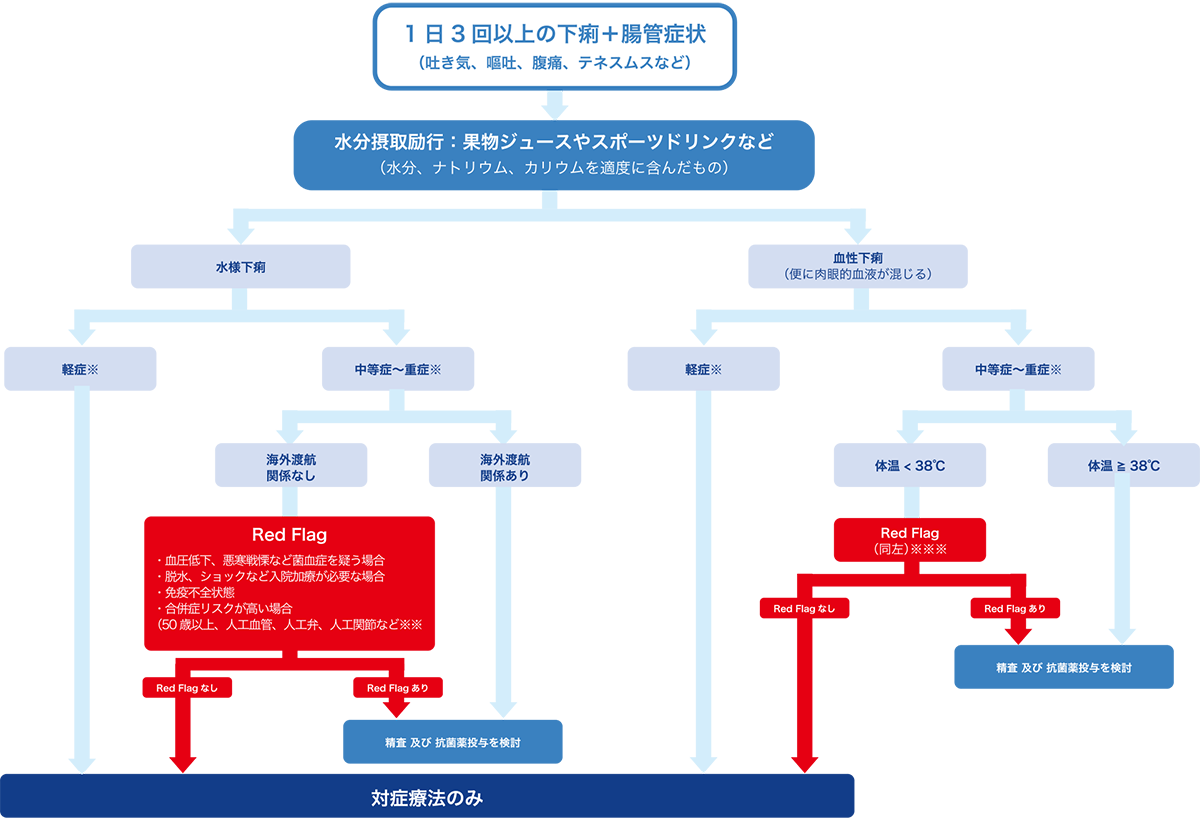
図4. 急性下痢症の診断及び治療の手順
(対象:学童期以上の小児~成人, 文献98を元に改変)
※ 下痢の重症度:軽症は日常生活に支障のないもの、中等症は動くことはできるが日常生活に制限があるもの、重症は日常生活に大きな支障のあるもの。
※※ 他の合併症リスクには炎症性腸疾患、血液透析患者、腹部大動脈瘤等がある。
※※※ EHEC(Enterohemorrhagic E. coli, 腸管出血性大腸菌)による腸炎に注意し、便検査を考慮する。
※※※※ 本図は診療手順の目安として作成したものであり、実際の診療では診察した医師の判断が優先される。
(i) 小児の脱水への対応
急性下痢症と判断した場合、まずは緊急度の判断が重要であり、緊急度に最も影響する要素は脱水の有無とされている112。特に、小児では、体重あたりの水分必要量が多い一方で、水分や食事の摂取を他者(特に保護者)に依存していることから、脱水への対応が重要であると指摘されている。
輸液療法を要することが多い体重の5%以上の脱水(体重減少)を見逃さないことが重要であり、①Capillary Refill Time(CRT)注 が2秒以上、②粘膜の乾燥、③流涙なし、④全身状態の変化の4項目のうち2項目に該当すれば、5%以上の脱水が示唆されると報告されている126。また、経静脈的輸液が必要になる危険性が高い者は、血便、持続する嘔吐、尿量の減少、眼窩の陥凹及び意識レベルの低下のある者とされている14。
ORSは、急性下痢症に対する世界標準の治療であり97,112、その有効性だけではなく、血管確保が不要で患者への負担も少ないという利点も大きく、脱水のない状況での脱水予防や軽度から中等症の脱水に対する治療として推奨されている97,112。
具体的な脱水への対応としては、できるだけ早期(脱水症状出現から3~4時間以内)に、ORSを少量(ティースプーン1杯程度)から徐々に増量しつつ、脱水量と同量(軽症から中等症脱水ならば50 mL/kg~100 mL/kg)を2~4時間で補正することが重要とされている112。なお、下痢に対する止痢薬は科学的根拠に乏しく推奨されていない112。
注15 指先を圧迫して蒼白になった後、圧迫を解除してから赤みを帯びてくるまでにかかる時間のこと。
(ii) 小児に対する抗菌薬の適応
小児の急性下痢症の多くはウイルス性のため、抗菌薬は、無効であるばかりか、腸内細菌叢を乱し、菌交代現象を引き起こすため、使用すべきではないと指摘されている100,112。細菌による急性下痢症が疑われる場合であっても、多くは自然軽快するため、抗菌薬の使用は不要と指摘されている100,112。なお、海外の指針でも、便培養検査の結果を踏まえて抗菌薬治療を行う必要がある状況としては、全身状態が不良又は免疫不全者のサルモネラ腸炎やカンピロバクター腸炎等一部の症例に限定されている112,127。
(iii) サルモネラ腸炎
- 健常者における軽症※のサルモネラ腸炎に対しては、抗菌薬を投与しないことを推奨する。
※軽症とは、日常生活に支障のない状態を指す。
検査の結果、原因微生物がサルモネラ腸炎と判明した場合であっても、非チフス性サルモネラ属菌による腸炎に対する抗菌薬治療は、基礎疾患のない成人において、下痢や発熱等の有症状期間を短縮させず、かえって保菌状態を長引かせることが報告されている128。このことから、本手引きでは、健常者における軽症のサルモネラ腸炎に対しては、抗菌薬を投与しないことを推奨する。
なお、サルモネラ腸炎の重症化の可能性が高く、抗菌薬投与を考慮すべき症例としては、以下が示されている129。
- 3か月未満の小児又は65歳以上の高齢者
- ステロイド及び免疫抑制剤投与中の患者
- 炎症性腸疾患患者
- 血液透析患者
- ヘモグロビン異常症(鎌状赤血球症等)
- 腹部大動脈瘤がある患者
- 心臓人工弁置換術後の患者
なお、JAID/JSCの指針では、サルモネラ腸炎で抗菌薬投与が必要な場合には、第一選択薬の処方としてレボフロキサシン3~7日間 経口投与、第二選択薬(フルオロキノロン低感受性株又はアレルギーがある場合)の処方としてセフトリアキソン点滴静注 3~7日間又はアジスロマイシン 3~7日間 経口投与が推奨されている100。(セフトリアキソンとアジスロマイシンは添付文書上の適応菌種ではない)
(iv) カンピロバクター腸炎
- 健常者における軽症※のカンピロバクター腸炎に対しては、抗菌薬を投与しないことを推奨する。
※軽症とは、日常生活に支障のない状態を指す。
検査の結果、原因微生物がカンピロバクターと判明した場合については、抗菌薬投与群は偽薬群(プラセボ群)と比較して有症状期間を1.32日間(95%信頼区間 0.64-1.99日間)短縮することが報告されている130が、大部分の症例が抗菌薬なしで治癒し、また、近年、カンピロバクターの耐性化が進んでいることから、JAID/JSCの指針でも、全身状態が重症である場合を除いて、抗菌薬の使用は推奨されていない100。このことから、本手引きでは、健常者における軽症のカンピロバクター腸炎に対しては、抗菌薬を投与しないことを推奨する。
なお、カンピロバクターに関しては、世界的にフルオロキノロン系抗菌薬に対する耐性化が進んでおり、JAID/JSCの指針では、全身状態が重症で抗菌薬を投与する場合には、クラリスロマイシン 1回200 mg 1日2回3~5日間経口投与、アジスロマイシン1回500 mg1日1回3日間経口投与が推奨されている100。(アジスロマイシンは添付文書上の適応菌種ではない)
(v) 腸管出血性大腸菌(Enterohemorrhagic E. coli : EHEC)腸炎
腸管出血性大腸菌腸炎に罹患した患者では血便を伴うことが多いが、典型的には高熱を伴うことは少ないと指摘されている129。腸管出血性大腸菌腸炎の原因微生物としては、血清型O157によるものが最も多いが、血清型O26、血清型O111等による症例も報告されている100。EHEC腸炎全体のうち5~10%が溶血性尿毒症症候群(Hemolytic Uremic Syndrome: HUS)を起こすと報告されている100。
検査の結果、原因微生物がEHECと判明した場合であっても、海外の総説では、抗菌薬使用により菌からの毒素放出が促進され、HUS発症の危険性が高くなることから、EHEC腸炎に対する抗菌薬投与は推奨されていない106。統合解析では、抗菌薬投与はHUS発症増加とは関連しないと報告されている(オッズ比1.33倍 95%信頼区間 0.89-1.99倍)131が、より厳密なHUSの定義を用いている研究のみに限定するとオッズ比は2.24倍(95%信頼区間 1.45-3.46倍)になり、抗菌薬投与がHUS発症増加と関連することが示唆されている131。一方で、日本の小児を中心にした研究では、EHEC腸炎に対して発症早期にホスホマイシンを内服した者では、その後のHUS発症率が低いことも報告されており132,133、これらのことも踏まえて、JAID/JSCの指針では、「現時点で抗菌薬治療に対しての推奨は統一されていない」とされている100。
なお、これらの指針では、EHEC腸炎に対する止痢薬に関しては、HUS発症の危険性を高くするため使用しないことが推奨されている100,134,135。
(5) 患者・家族への説明
急性下痢症の多くは対症療法のみで自然軽快するため、水分摂取を推奨し脱水を予防することが最も重要である。一方、下痢や腹痛をきたす疾患は多岐に渡るため、経過を見て必要があれば再受診すべき旨を伝える必要がある。
表7. 急性下痢症の診療における患者への説明で重要な要素
| 1) 情報の収集 |
|
|---|---|
| 2) 適切な情報の提供 |
|
| 3) まとめ |
|
【医師から患者への説明例:成人の急性下痢症の場合】
症状からはウイルス性の腸炎の可能性が高いと思います。このような場合、抗生物質はほとんど効果がなく、腸の中のいわゆる「善玉菌」も殺してしまい、かえって下痢を長引かせる可能性もありますので、対症療法が中心になります。脱水にならないように水分をしっかりとるようにしてください。一度にたくさん飲むと吐いてしまうかもしれないので、少しずつ飲むと良いと思います。下痢として出てしまった分、口から補うような感じです。
下痢をしているときは胃腸からの水分吸収能力が落ちているので、単なる水やお茶よりも糖分と塩分が入っているもののほうが良いですよ。食べられるようでしたら、お粥に梅干しを入れて食べると良いと思います。
一般的には、強い吐き気は1~2日間くらいでおさまってくると思います。下痢は最初の2~3日がひどいと思いますが、だんだんおさまってきて1週間前後で治ることが多いです。
ご家族の人になるべくうつさないようにトイレの後の手洗いをしっかりすることと、タオルは共用しないようにしてください。
便に血が混じったり、お腹がとても痛くなったり、高熱が出てくるようならバイ菌による腸炎とか、虫垂炎、俗に言う「モウチョウ」など他の病気の可能性も考える必要が出てきますので、そのときは再度受診してください。万が一水分が飲めない状態になったら点滴が必要になりますので、そのような場合にも受診してください。
【医師から患者への説明例:小児の急性下痢症の場合】
ウイルスによる「お腹の風邪」のようです。特別な治療薬(=特効薬)はありませんが、自分の免疫の力で自然に良くなります。
子どもの場合は、脱水の予防がとても大事です。体液に近い成分の水分を口からこまめにとることが重要です。最初はティースプーン一杯程度を10~15分毎に与えてください。急にたくさん与えてしまうと吐いてしまって、さらに脱水が悪化しますので、根気よく、少量ずつ与えてください。1時間くらい続けて、大丈夫そうなら、少しずつ1回量を増やしましょう。
それでも水分がとれない、それ以上に吐いたり、下痢をしたりする場合は点滴(輸液療法)が必要となることもあります。半日以上おしっこが出ない、不機嫌、ぐったりして、ウトウトして眠りがちになったり、激しい腹痛や、保護者の方がみて「いつもと違う」と感じられたら、夜中でも医療機関を受診してください。
便に血が混じったり、お腹がとても痛くなったり、高熱が出てくるようならバイ菌による腸炎とか、虫垂炎、俗に言う「モウチョウ」など他の病気の可能性も考える必要が出てきますので、その時は再度受診してください。
【薬剤師から患者への説明例:急性下痢症の場合】
医師による診察の結果、今のところ、胃腸炎による下痢の可能性が高いとのことです。これらの急性の下痢に対しては、抗生物質(抗菌薬)はほとんど効果がありません。むしろ、抗生物質の服用により、下痢を長引かせる可能性もあり、現時点では抗生物質の服用はお勧めできません。
脱水にならないように水分をしっかりとることが一番大事です。少量、こまめな水分摂取を心がけてください。単なる水やお茶よりも糖分と塩分が入っているもののほうがよいです。
便に血が混じったり、お腹がとても痛くなったり、高熱が出たり、水分もとれない状況が続く際は再度医師を受診してください。
※ 医師の抗菌薬の処方の有無に関わらず、処方意図を医師が薬剤師に正確に伝えることで、患者への服薬説明が確実になり、患者のアドヒアランスが向上すると考えられている99,101。このことから、患者の同意を得て、処方箋の備考欄又はお薬手帳に病名等を記載することが、医師から薬剤師に処方意図が伝わるためにも望ましい。
6. 参考資料
(1) 抗微生物薬適正使用を皆さんに理解していただくために
質問1 ウイルスと細菌は違うのですか?
回答1
細菌とはひとつの細胞からなる生き物で、大腸菌やブドウ球菌等が含まれます。大きさが数マイクロメートル(千分の1 mm)の微生物です。細菌は細胞壁という殻のようなものに囲まれており、その中に細菌が生きるのに必要な様々なタンパク等の物質を合成したり代謝を行ったりする装置(細胞内器官と呼びます)と遺伝子を持っていて、それらの装置や遺伝子を使って自力で分裂して増えていくことができます。一方、ウイルスは細胞ではなく、遺伝子とタンパク質等物質の集まり(大きさは数十ナノメートル、細菌の1万分の1程度)だけの微生物です。例えばインフルエンザウイルスやノロウイルス等です。自力では物質の合成や代謝ができず(そのような装置を持っていないため)、ヒトや動物の細胞の中に入り込んで、その細胞の中の装置を借りて遺伝子やタンパク質を合成してもらわないと増えることができません。違いをまとめると回答2にある表のようになります。
質問2 抗微生物薬、抗菌薬、抗生物質、抗生剤の違いは何でしょうか?
回答2
細菌、ウイルス、カビ(真菌と呼びます)、原虫、寄生虫等様々な分類の小さな生物をまとめて微生物といいます。微生物を退治する薬をすべてまとめて抗微生物薬と呼びます。つまり、抗微生物薬には細菌に効く薬、ウイルスに効く薬、カビに効く薬等多くの種類の薬が含まれていることになります。とりわけ細菌に効く薬は細菌による病気(感染症)の治療に使われ、そのような薬を抗菌薬と呼んだり抗生物質、抗生剤と呼んだりします。抗菌薬と抗生物質は厳密に学問的にいうと少し意味が違うのですが、一般的には同じ意味だと考えて差し支えありません。
抗生物質(抗菌薬)が効くかどうかを含めて、細菌とウイルスの違いをまとめると下の表のようになります。注意していただきたい点は、抗生物質(抗菌薬)はウイルスには効果がない、という点です。それは、抗生物質(抗菌薬)が細菌の持つ細胞壁を破壊したり、細菌の自力で増殖する能力を障害する薬だからなのです。ウイルスには細胞壁や自力で増殖する能力がないため、抗生物質(抗菌薬)はウイルスに作用することがないのです。
| 細菌 | ウイルス | |
|---|---|---|
| 大きさ | 1 mmの千分の1程度 | 1 mmの1千万分の1程度 |
| 細胞壁 | あり | なし |
| タンパク合成 | あり | なし |
| エネルギー産生・代謝 | あり | なし |
| 増殖する能力 | 他の細胞がなくても増殖できる | 人や動物の細胞の中でしか 増殖できない |
| 抗生物質(抗菌薬) | 効く | 効かない |
※日常会話では「細菌」の代わりに「バイ菌」と言うこともありますが、一般的に「バイ菌」はすべての微生物(細菌、ウイルス、カビ、原虫等を含む)を指して使われています。
質問3 薬剤耐性(AMR)とはどのようなことでしょうか?私に関係あるのでしょうか?
回答3
細菌は増殖の速度が速いので、人や動物よりも桁違いに速く進化(遺伝子が変化)します。細菌の周りに抗生物質(抗菌薬)があると、たまたま進化の中でその抗生物質(抗菌薬)に抵抗性を身につけた細菌が多く生き残ることになります。このように細菌が抗生物質(抗菌薬)に抵抗性を身につけ、抗生物質(抗菌薬)が効かなくなることを薬剤耐性(Antimicrobial resistance: AMR)と言い、薬剤耐性(AMR)を身につけた細菌を(薬剤)耐性菌と言います。「MRSA」や「多剤耐性緑膿菌」は耐性菌の一種です。また、薬剤耐性(AMR)は、例えばウイルスでも薬剤耐性は起こります。耐性菌が身体の表面や腸の中に住み着いている人に抗生物質(抗菌薬)を使うと、耐性菌以外の細菌は抗生物質(抗菌薬)で死んでしまうので、耐性菌だけが生き残り、身体の表面や腸の中等で増えることになります。普段、健康な私たちでも、耐性菌によって感染症を起こしてしまうと、本来効いてくれるはずの抗生物質(抗菌薬)が効きにくく、治療が難しくなること(症状が長く続く、通院で済むはずが入院しなければならなくなる等)があります。都合の悪いことに、このような耐性菌が日本を含む世界各地で増えています。抗生物質(抗菌薬)を大切に使わなければ、将来、抗生物質(抗菌薬)が効かなくなり、多くの方が感染症で命を落とすことになると考えられています。
薬剤耐性(AMR)は、私たち一人ひとりが、抗生物質(抗菌薬)を使ったことで起こる問題です。私たちは、より丁寧に診察を行い、より大切に抗生物質(抗菌薬)を使いたいと考えています。皆さんには、抗生物質(抗菌薬)が必要であれば必要と、不必要であれば不必要と、しっかりと説明しますので、ご理解ください。
質問4 これからは、風邪を引いた、または下痢をしているのに抗生物質(抗菌薬)を出してもらえないのでしょうか?
回答4
医師はいつも患者さんの速やかな回復を願って診療しています。今後もその方針は何ら変わりません。一見、ウイルスによる風邪や下痢のように見える感染症の中には抗生物質(抗菌薬)の効く細菌による感染症が一部含まれていることは事実ですが、風邪や下痢の大部分は抗生物質(抗菌薬)の効かないウイルス性の感染症や抗生物質(抗菌薬)を飲んでも飲まなくても自然に治る感染症です。抗生物質(抗菌薬)が効くか効かないかはとても大切な区別ですので、私たちはこの手引きに従って、抗生物質(抗菌薬)が必要ないことを確かめた上で抗生物質(抗菌薬)を処方するかしないかを判断しています。
質問5 ウイルス感染症等の自然に治る感染症に対して抗生物質(抗菌薬)を使うと何か悪いことがあるのでしょうか?
回答5
抗生物質(抗菌薬)は細菌の細胞内の装置を阻害する薬ですので、細菌を退治する効果があります。ウイルスは細胞ではないので抗生物質(抗菌薬)は効きません。抗生物質(抗菌薬)はヒトの細胞には作用しないので健康な人が飲んでも直接の害はほとんどありませんが、薬とはいえ人にとっては異物ですので、アレルギー反応を生じたり、肝臓や腎臓を傷めたりすることがあります。また、口から腸の中や皮膚には、無害な細菌や有益な細菌(いわゆる善玉菌)が数多く住み着いています(常在菌と呼びます)。抗生物質(抗菌薬)は常在菌を殺してしまい、下痢や腹痛を起こすことがあります。さらに、常在菌を殺してしまうと、抗生物質(抗菌薬)が効かないように変身した細菌(耐性菌と呼びます)やカビが身体の表面や腸の中で生き残って増えてしまうことがあります。抗生物質(抗菌薬)を飲んだ人には、そのようにして増えた耐性菌やカビが感染症を起こしたり、他人に感染症を起こす原因になったりすることがあります。つまり、抗生物質(抗菌薬)は不要の人には悪い効果しかありません。そして、世の中に抗生物質(抗菌薬)を飲む人が多ければ多いほど、人々(抗生物質を飲む人も飲まない人でも)の身体には耐性菌が多く住み着いている状態になります。そうすると、これから先、あなたやあなたの近くの人が細菌感染症に罹ってしまった場合に、本来効くはずの抗生物質(抗菌薬)が効かない、という状況に陥ってしまいやすくなります。このような状況は以前から指摘されていて、この数年、全世界的な問題になっています。その対策としては、抗生物質(抗菌薬)を本当に必要な場合のみに使う(不要の場合は使わない)ということが求められています。
質問6 以前に風邪や下痢になった時に抗生物質(抗菌薬)を出してもらったことがありますが、それはなぜでしょうか?
回答6
これまで同じような症状の場合には抗生物質(抗菌薬)をもらっていたのがどうしてなのか、疑問に思われるかもしれません。これまで私たち医師が、同じような症状の時に抗生物質(抗菌薬)を出していたことがありますが、それにはいくつか理由が考えられます。
① 入念な診察の結果、単なる風邪か下痢ではなく、抗生物質(抗菌薬)が必要な細菌による感染症だと診断した。
② 抗生物質(抗菌薬)が必要な細菌による感染症か、抗生物質(抗菌薬)が不要なウイルス感染症かの区別をすることが不十分だった。
③ 抗生物質(抗菌薬)を出したら患者さんが良くなったという経験から、抗生物質(抗菌薬)が効いたから良くなったように感じてしまった。
④ 抗生物質(抗菌薬)を出してほしいという患者さんからの強い要望に応えようとした。
この手引きは抗生物質(抗菌薬)を使わないためのものではありません。抗生物質(抗菌薬)が必要かどうかを見極めるためのものです。診察の結果、①の場合は今後も私たち医師は抗生物質(抗菌薬)を処方して飲んでいただきます。私たちはこの手引きを使って慎重に診察することで、抗生物質(抗菌薬)が必要な感染症か不要かをできる限り区別し、②の理由による抗生物質の使用を減らそうとしています。私たちはこの手引きの内容に従って入念に慎重に診察を行い、投与すべきではないと判断した場合には抗生物質(抗菌薬)を処方していません。ただ、これまで、③や④の理由で抗生物質(抗菌薬)を処方していたとも言われています。
感冒やほとんどの下痢は抗生物質(抗菌薬)を飲まなくても自然に軽快します。仮にあなたの「かぜ」が、発熱や気道症状が3日間続いた後に解熱して改善する「感冒」だったとします。1日目、2日目は市販の感冒薬を飲んで自宅で休んでいたのですが良くならないので3日目に病院を受診しました。医師の指示した抗生物質(抗菌薬)を飲んだところ、翌日には解熱して症状が良くなってきました。
この時、患者さんにとっても医師にとっても抗生物質(抗菌薬)が良く効いたように見えるでしょう。しかし、実際に起きたことは、順序として、抗菌薬を飲み始めた後で症状が良くなってきた、ということであって、抗生物質(抗菌薬)を飲んだことが理由で症状が良くなった、ということではありません。医師は「ウイルスには抗生物質(抗菌薬)は効かない」ということが頭ではわかっています。しかし、患者さんは「抗生物質(抗菌薬)を飲んだから良くなった」と思うことでしょう。医師はそのように、抗生物質(抗菌薬)を処方した翌日に症状が良くなったという患者さんをたくさん経験していますから、「効いていないにしても患者さんが良くなったのだから、抗生物質(抗菌薬)を出してよかった」という記憶が残ってしまいます。このような経験を繰り返しているうちに、医師自身、抗生物質(抗菌薬)を出した方が患者さんに喜ばれるのではないか?という気になってしまっていたのです。
結果として「風邪を引いたらお医者さんで抗生物質をもらったら治る」という思い込みができても仕方ありません。まれですが「以前に飲んだらすぐに治ったから、今回も抗生物質を出してほしい」と強く希望される患者さんもいます。医師は患者さんに満足してもらうことを優先しますから、そういう希望を聞いたり、会話の中で感じ取ったりして、患者さんに安心していただくために抗生物質(抗菌薬)を出していたことがあるかもしれません。
質問7 これからは、風邪や下痢の時に抗生物質(抗菌薬)を出さないのですか?
回答7
風邪や下痢には抗生物質(抗菌薬)を出さないということではありません。風邪や下痢の時に、抗生物質(抗菌薬)が必要かどうかを正しく診断できるように診察を進め、必要がないと診断した場合には出さないということです。抗生物質(抗菌薬)が出ていないことで心配に感じられるのであれば、是非お申し出ください。どのように診察して診断したかをご安心できるように詳しく説明いたします。
今まで、医師と患者さんの経験と行動の積み重ねから、抗生物質(抗菌薬)の使いすぎを生じ、そして現在の薬剤耐性(AMR)問題をもたらしてしまいました。これまで医師は、このような「抗生物質(抗菌薬)は、本当は不要でも有害ではないのだから良いだろう」という考えで抗生物質(抗菌薬)を処方していたかもしれません。しかし、これからは違います。この手引きを使って本当に抗生物質(抗菌薬)が必要な状況と不必要な状況とをしっかりと区別し、抗生物質(抗菌薬)が必要な患者さんにだけ抗生物質(抗菌薬)を投与する方針をとりたいと考えています。そのようにしないと、薬剤耐性(AMR)問題は悪化する一方で、抗菌薬が効いてほしい時に効いてくれない薬になってしまう可能性があり、既にある程度、そのようになってしまっていることがわかっています。
私たち医師はいつでもすべての患者さんの速やかな回復を願って診療しています。抗生物質(抗菌薬)の良く効く細菌による感染症の場合にはもちろん抗生物質(抗菌薬)を飲んでもらいます。そのような感染症を見逃さないように慎重に診察を行います。その上で抗生物質(抗菌薬)が必要ないことを確かめた場合には私たちは抗生物質(抗菌薬)を処方しません。抗生物質(抗菌薬)がいざという時(本当に細菌による感染症だった時)に皆さんに良く効く薬であるためですのでご理解ください。
(2) 抗菌薬の延期処方とは
近年、急性気道感染症における抗菌薬使用削減のための戦略として、抗菌薬の延期処方(Delayed Antibiotics Prescription: DAP)に関する科学的知見が集まってきている92-94,136。DAPは、初診時に抗菌薬投与の明らかな適応がない患者に対して、その場で抗菌薬を投与するのではなく、その後の経過が思わしくない場合にのみに抗菌薬を投与する手法であり、不必要な処方を減らすためにも有効であることから、英国では急性気道感染症に関する国の指針においてDAPが推奨されている137,138。日本においてDAPを行う場合は、初診時は抗菌薬を処方せず、症状が悪化した場合や遷延する場合に再度受診をしてもらい、改めて抗菌薬処方の必要性を再評価するという方法が考えられる。
海外の事例を一例として挙げると、スペインで行われた多施設無作為化比較試験では、18歳以上の急性気道感染症(急性咽頭炎、急性鼻副鼻腔炎、急性気管支炎、軽症から中等症の慢性閉塞性肺疾患急性増悪)で、抗菌薬の明らかな適応がないと医師が判断した患者について、初診時に抗菌薬を処方し内服を開始する群(すぐに内服群)と、経過が思わしくない場合に抗菌薬の内服を開始する群(DAP群)注 、抗菌薬を処方しない群(処方なし群)に割り付け、その後の状況について比較した研究結果が示されている94。
この研究では、実際に抗菌薬を使用した割合はすぐに内服群で91.1%、DAP 群で23.0~32.6%、処方なし群で12.1%である一方で、症状が中等度又は重度の期間はすぐに内服群で短いものの、中等度の期間又は重度の期間の差はそれぞれ平均0.5~1.3日、0.4~1.5日と臨床的に意味のある差とは言いがたく、一方で、合併症、副作用、予期しない受診、30日後の全身健康状態、患者の満足度については差が見られなかったことが報告されている94。
以上のようなことを踏まえ、DAPを行うことで、合併症や副作用、予期しない受診等の好ましくない転帰を増やすことなく抗菌薬処方を減らすことができると考えられている92-94。
ここで大事な点は、患者を経時的に診るという視点である。患者の医療機関へのアクセスが比較的良い日本では、症状が悪化した場合や数日しても症状が改善しない場合に同じ医療機関を受診するように説明しておき、再診時に抗菌薬の適応を再検討する方が現実的かつ望ましいと考えられる。普段の忙しい診療のなかでの「一点」のみでは急性気道感染症等に対する適切な診断が難しい場合があることを認識し、急性気道感染症等の通常の経過はどのようなものか、また、今後どのような症状に注意してもらい、どのような時に再診をしてもらうべきか、どのようになった場合に抗菌薬の適応となりうるか、という「線」の時間軸で診療を行い、その内容に沿った患者への説明を行うことが重要である。外来診療では、この「線」の時間軸による考えが適切な感染症診療にも役立ち、抗菌薬の適正使用にもつながる、と再認識してもらえれば幸いである。
注16 日本では、保険医療機関及び保険医療療養規則(昭和32年厚生省令第15号)第20条に基づき、保険医療機関(病院や診療所)で交付される処方箋の使用期間を、交付の日を含めて原則4日以内(休日や祝日を含む)としており、必ずしも海外の事例をそのままの方法では適応できないことに注意が必要である。
(i) 急性気道感染症及び急性下痢症の診療に係るチェックシート
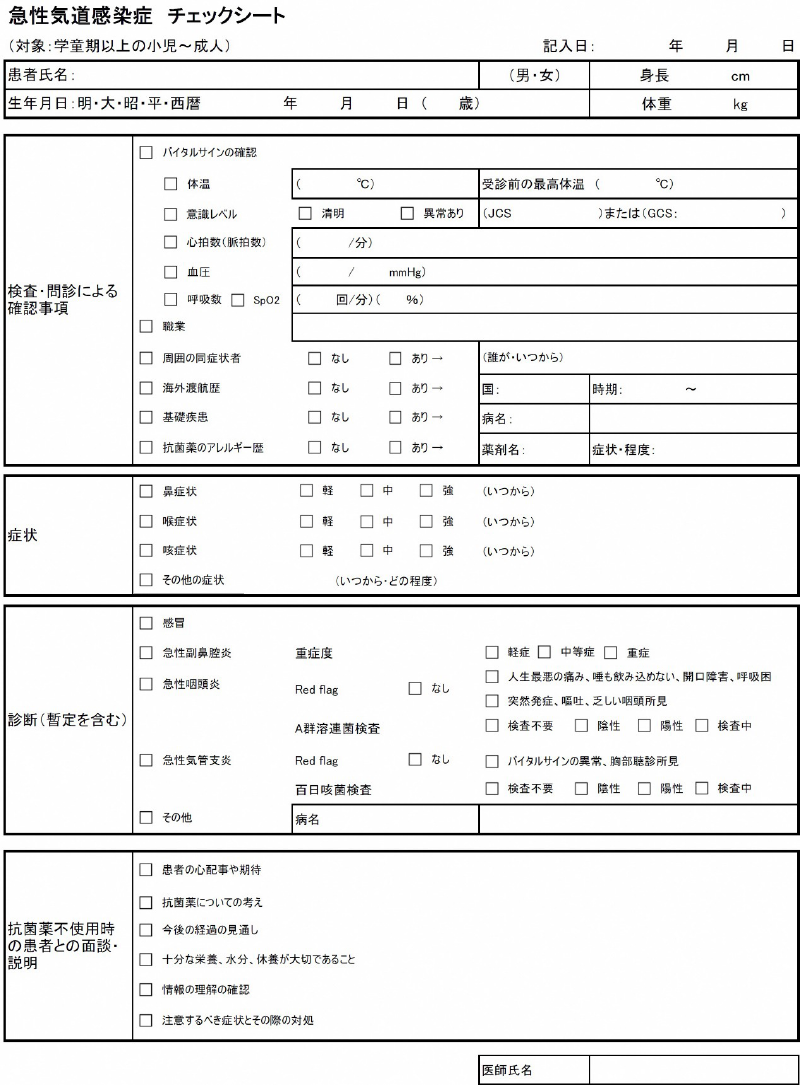
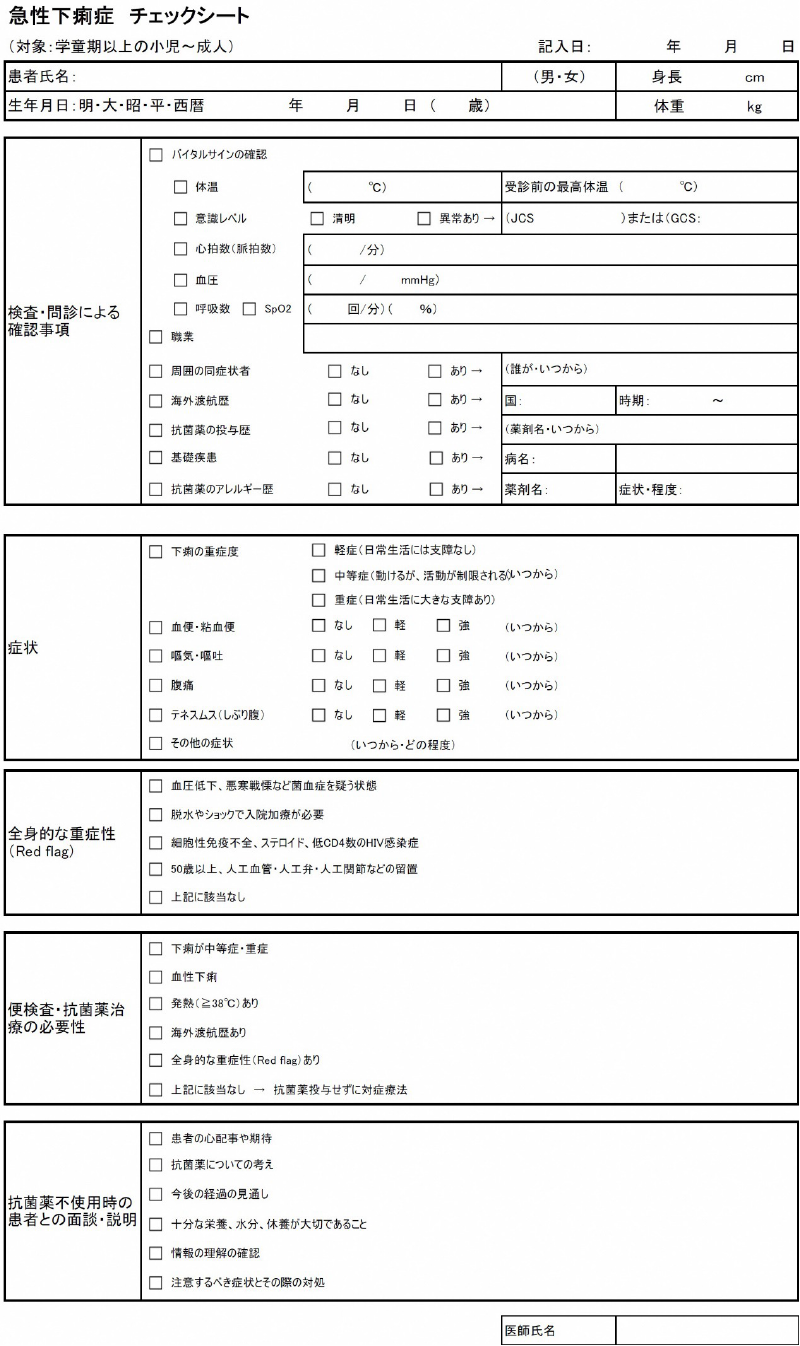
7. 引用文献
- 加地正郎. インフルエンザとかぜ症候群. 東京: 南山堂; 2003.
- 日本呼吸器学会. 成人気道感染症診療の基本的考え方 : 日本呼吸器学会「呼吸器感染症に関するガイドライン」. 東京: 日本呼吸器学会; 2003.
- 松村滎久他. 風邪症候群急性呼吸器感染症 用語の統一と抗菌薬の適正使用のために 定義に関するアンケート結果(1). 内科専門医会誌. 2003;15:217-221.
- 加地正郎. 日常診療のなかのかぜ. 臨床と研究. 1994;71:1-3.
- 厚生労働省大臣官房統計情報部.令和2年(2020). https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/20/dl/kanjya.pdf. 最終閲覧日2023年9月25日.
- Monto AS, Ullman BM. Acute respiratory illness in an American community. The Tecumseh study. JAMA. 1974;227(2):164-169.
- Chen Y, Williams E, Kirk M. Risk factors for acute respiratory infection in the Australian community. PloS One. 2014;9(7):e101440.
- Yokobayashi K, Matsushima M, Watanabe T, Fujinuma Y, Tazuma S. Prospective cohort study of fever incidence and risk in elderly persons living at home. BMJ Open. 2014;4(7):e004998.
- Nicholson KG, Kent J, Hammersley V, Cancio E. Acute viral infections of upper respiratory tract in elderly people living in the community: comparative, prospective, population based study of disease burden. BMJ. 1997;315(7115):1060-1064.
- Graat JM, Schouten EG, Heijnen M-LA, et al. A prospective, community-based study on virologic assessment among elderly people with and without symptoms of acute respiratory infection. J Clin Epidemiol. 2003;56(12):1218-1223.
- Falsey AR, Walsh EE, Hayden FG. Rhinovirus and coronavirus infection-associated hospitalizations among older adults. J Infect Dis. 2002;185(9):1338-1341.
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Fever in under 5s: assessment and initial management | Clinical guideline. https://www.nice.org.uk/guidance/ng143. 最終閲覧日2023年3月24日.
- Heikkinen T, Järvinen A. The common cold. Lancet. 2003;361(9351):51-59.
- Kliegman R, Stanton B, Geme J, Schor N. Nelson Textbook of Pediatrics. 20th edition. Philadelphia, PA: Elsevier; 2015.
- Keith T, Saxena S, Murray J, Sharland M. Risk-benefit analysis of restricting antimicrobial prescribing in children: what do we really know? Curr Opin Infect Dis. 2010;23(3):242-248.
- American Academy of Pediatrics, Committee on Infectious Diseases, Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS. Red Book: 2015 Report of the Committee on Infectious Diseases.; 2015.
- Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2012;55(10):1279-1282.
- Kearns GL, Abdel-Rahman SM, Alander SW, Blowey DL, Leeder JS, Kauffman RE. Developmental pharmacology - drug disposition, action, and therapy in infants and children. N Engl J Med. 2003;349(12):1157-1167.
- Gonzales R, Bartlett JG, Besser RE, et al. Principles of appropriate antibiotic use for treatment of acute respiratory tract infections in adults: background, specific aims, and methods. Ann Intern Med. 2001;134(6):479-486.
- 日本内科学会専門医部会. コモンディジーズブック : 日常外来での鑑別と患者への説明のために. 東京: 日本内科学会; 2013.
- Qaseem A, Lin JS, et al., Diagnosis and Management of Acute Left-Sided Colonic Diverticulitis: A Clinical Guideline From the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2022 Mar;175(3):399-415.
- Monto AS, Gravenstein S, Elliott M, Colopy M, Schweinle J. Clinical signs and symptoms predicting influenza infection. Arch Intern Med. 2000;160(21):3243-3247.
- Gwaltney JM, Hendley JO, Simon G, Jordan WS. Rhinovirus infections in an industrial population. II. Characteristics of illness and antibody response. JAMA. 1967;202(6):494-500.
- Ebell MH, Afonso AM, Gonzales R, Stein J, Genton B, Senn N. Development and validation of a clinical decision rule for the diagnosis of influenza. J Am Board Fam Med. 2012;25(1):55-62.
- Chartrand C, Leeflang MMG, Minion J, Brewer T, Pai M. Accuracy of rapid influenza diagnostic tests: a meta-analysis. Ann Intern Med. 2012;156(7):500-511.
- Meltzer EO, Hamilos DL, Hadley JA, et al. Rhinosinusitis: establishing definitions for clinical research and patient care. J Allergy Clin Immunol. 2004;114(6 Suppl):155-212.
- Berg O, Carenfelt C, Rystedt G, Anggård A. Occurrence of asymptomatic sinusitis in common cold and other acute ENT-infections. Rhinology. 1986;24(3):223-225.
- Dingle J, Badger G, Jordan WS. Illness in the Home: A Study of 25,000 Illnesses in a Group of Cleveland Families. OH: Western Reserve Univ Pr; 1964.
- Lacroix JS, Ricchetti A, Lew D, et al. Symptoms and clinical and radiological signs predicting the presence of pathogenic bacteria in acute rhinosinusitis. Acta Otolaryngol (Stockh). 2002;122(2):192-196.
- Chow AW, Benninger MS, Brook I, et al. IDSA clinical practice guideline for acute bacterial rhinosinusitis in children and adults. Clin Infect Dis. 2012;54(8):e72-e112.
- Bisno AL. Acute pharyngitis. N Engl J Med. 2001;344(3):205-211.
- 鈴木賢二, 黒野祐一, 小林俊光, 西村忠郎, 馬場駿吉. 第 4 回耳鼻咽喉科領域感染症臨床分離菌全国サーベイランス結果報告. 日耳鼻感染症研会誌. 2008;26:15–26.
- Suzuki K, Kurono Y, Ikeda K, et al. Nationwide surveillance of 6 otorhinolaryngological infectious diseases and antimicrobial susceptibility pattern in the isolated pathogens in Japan. J Infect Chemother. 2015;21(7):483-491.
- 武内一, 深澤満, 吉田均, 西村龍夫, 草刈章, 岡崎実. 扁桃咽頭炎における検出ウイルスと細菌の原因病原体としての意義. 日本小児科学会雑誌. 2009;113(4):694-700.
- Bisno AL, Gerber MA, Gwaltney JM, Kaplan EL, Schwartz RH. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Group A Streptococcal Pharyngitis. Clin Infect Dis. 2002;35(2):113-125.
- Tanz RR, Shulman ST. Chronic pharyngeal carriage of group A streptococci. Pediatr Infect Dis J. 2007;26(2):175-176.
- Aliyu SH, Marriott RK, Curran MD, Parmar S, Bentley N, Brown NM, Brazier JS, Ludlam H. Real-time PCR investigation into the importance of Fusobacterium necrophorum as a cause of acute pharyngitis in general practice. J Med Microbiol. 2004;53(Pt 10):1029-1035.
- Batty A, Wren MW. Prevalence of Fusobacterium necrophorum and other upper respiratory tract pathogens isolated from throat swabs. Br J Biomed Sci. 2005;62(2):66-70.
- Amess JA, O'Neill W, Giollariabhaigh CN, Dytrych JK. A six-month audit of the isolation of Fusobacterium necrophorum from patients with sore throat in a district general hospital. Br J Biomed Sci. 2007;64(2):63-65.
- Centor RM, Geiger P, Waites KB. Fusobacterium necrophorum bacteremic tonsillitis: 2 Cases and a review of the literature. Anaerobe 2010;16(6):626-628.
- Shah M, Centor RM, Jennings M. Severe acute pharyngitis caused by group C streptococcus. J Gen Intern Med. 2007;22(2):272-274.
- Centor RM. Expand the pharyngitis paradigm for adolescents and young adults. Ann Intern Med. 2009;151(11):812-815.
- Jensen A, Hansen TM, Bank S, Kristensen LH, Prag J. Fusobacterium necrophorum tonsillitis: an important cause of tonsillitis in adolescents and young adults. Clin Microbiol Infect. 2015;21(3):266.e1-266.e3.
- Hedin K, Bieber L, Lindh M, Sundqvist M. The aetiology of pharyngotonsillitis in adolescents and adults - Fusobacterium necrophorum is commonly found. Clin Microbiol Infect. 2015;21(3):263.e1-263.e7.
- Centor RM, Atkinson TP, Ratliff AE, Xiao L, Crabb DM, Estrada CA, Faircloth MB, Oestreich L, Hatchett J, Khalife W, Waites KB. The Clinical Presentation of Fusobacterium-Positive and Streptococcal-Positive Pharyngitis in a University Health Clinic: A Cross-sectional Study. Ann Intern Med. 2015;162(4):241-247.
- McIsaac WJ, Kellner JD, Aufricht P, Vanjaka A, Low DE. Empirical validation of guidelines for the management of pharyngitis in children and adults. JAMA. 2004;291(13):1587-1595.
- McIsaac WJ, Goel V, To T, Low DE. The validity of a sore throat score in family practice. Can Med Assoc J. 2000;163(7):811-815.
- ESCMID Sore Throat Guideline Group, Pelucchi C, Grigoryan L, et al. Guideline for the management of acute sore throat. Clin Microbiol Infect. 2012;18 Suppl 1:1-28.
- JAID/JSC感染症治療ガイド・ガイドライン作成委員会. JAID/JSC感染症治療ガイド2014. 東京: ライフサイエンス出版; 2014.
- McGinn TG, Deluca J, Ahlawat SK, Mobo BH, Wisnivesky JP. Validation and modification of streptococcal pharyngitis clinical prediction rules. Mayo Clin Proc. 2003;78(3):289-293.
- Humair J-P, Revaz SA, Bovier P, Stalder H. Management of acute pharyngitis in adults: reliability of rapid streptococcal tests and clinical findings. Arch Intern Med. 2006;166(6):640-644.
- Fine AM, Nizet V, Mandl KD. Large-scale validation of the Centor and McIsaac scores to predict group A streptococcal pharyngitis. Arch Intern Med. 2012;172(11):847-852.
- Llor C, Hernández M, Hernández S, Martínez T, Gómez FF. Validity of a point-of-care based on heterophile antibody detection for the diagnosis of infectious mononucleosis in primary care. Eur J Gen Pract. 2012;18(1):15-21.
- Ebell MH, Call M, Shinholser J, Gardner J. Does This Patient Have Infectious Mononucleosis?: The Rational Clinical Examination Systematic Review. JAMA. 2016;315(14):1502-1509.
- Wolf DM, Friedrichs I, Toma AG. Lymphocyte-white blood cell count ratio: a quickly available screening tool to differentiate acute purulent tonsillitis from glandular fever. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2007;133(1):61-64.
- 岸田直樹. 誰も教えてくれなかった「風邪」の診かた 重篤な疾患を見極める! 東京: 医学書院; 2012.
- 山本舜悟. かぜ診療マニュアル. 第2版. 東京: 日本医事新報社; 2017.
- Ebell MH, Lundgren J, Youngpairoj S. How long does a cough last? Comparing patients’ expectations with data from a systematic review of the literature. Ann Fam Med. 2013;11(1):5-13.
- JAID/JSC感染症治療ガイド・ガイドライン作成委員会 呼吸器感染症ワーキンググループ. JAID/JSC感染症治療ガイドライン 呼吸器感染症. 日本化学療法学会雑誌. 2014;62:1-109.
- Cornia PB, Hersh AL, Lipsky BA, Newman TB, Gonzales R. Does this coughing adolescent or adult patient have pertussis? JAMA. 2010;304(8):890-896.
- de Melker HE, Versteegh FG, Conyn-Van Spaendonck MA, et al. Specificity and sensitivity of high levels of immunoglobulin G antibodies against pertussis toxin in a single serum sample for diagnosis of infection with Bordetella pertussis. J Clin Microbiol. 2000;38(2):800-806.
- Yih WK, Lett SM, des Vignes FN, Garrison KM, Sipe PL, Marchant CD. The increasing incidence of pertussis in Massachusetts adolescents and adults, 1989-1998. J Infect Dis. 2000;182(5):1409-1416.
- Torkaman MRA, Kamachi K, Nikbin VS, Lotfi MN, Shahcheraghi F. Comparison of loop-mediated isothermal amplification and real-time PCR for detecting Bordetella pertussis. J Med Microbiol. 2015;64(Pt 4):463-465.
- Brotons P, de Paz HD, Esteva C, Latorre I, Muñoz-Almagro C. Validation of a loop-mediated isothermal amplification assay for rapid diagnosis of pertussis infection in nasopharyngeal samples. Expert Rev Mol Diagn. 2016;16(1):125-130.
- 小児呼吸器感染症診療ガイドライン作成委員会. 小児呼吸器感染症診療ガイドライン 2022.
- Kenealy T, Arroll B. Antibiotics for the common cold and acute purulent rhinitis. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(6):CD000247.
- 日本鼻科学会. 急性鼻副鼻腔炎診療ガイドライン. 日本鼻科学会会誌. 2010;49(2):143-198.
- Yamanaka N, Iino Y, Uno Y, et al. Practical guideline for management of acute rhinosinusitis in Japan. Auris Nasus Larynx. 2015;42(1):1-7.
- Wald ER, Applegate KE, Bordley C, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of acute bacterial sinusitis in children aged 1 to 18 years. Pediatrics. 2013;132(1):e262-e280.
- Lemiengre MB, van Driel ML, Merenstein D, Young J, De Sutter AIM. Antibiotics for clinically diagnosed acute rhinosinusitis in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2012;10:CD006089.
- Ahovuo-Saloranta A, Rautakorpi U-M, Borisenko OV, Liira H, Williams JW, Mäkelä M. Antibiotics for acute maxillary sinusitis in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(2):CD000243.
- Rosenfeld RM, Piccirillo JF, Chandrasekhar SS, et al. Clinical practice guideline (update): adult sinusitis. Otolaryngol--Head Neck Surg. 2015;152(2 Suppl):S1-S39.
- Falagas ME, Karageorgopoulos DE, Grammatikos AP, Matthaiou DK. Effectiveness and safety of short vs. long duration of antibiotic therapy for acute bacterial sinusitis: a meta-analysis of randomized trials. Br J Clin Pharmacol. 2009;67(2):161-171.
- Suzuki K, Nishimaki K, Okuyama K, et al. Trends in antimicrobial susceptibility of Streptococcus pneumoniae in the Tohoku district of Japan: a longitudinal analysis from 1998 to 2007. Tohoku J Exp Med. 2010;220(1):47-57.
- 池辺忠義. 劇症型溶血性レンサ球菌感染症. 感染症発生動向調査週報. 2002;4(46):12-14.
- van Driel ML, De Sutter AI, Habraken H, Thorning S, Christiaens T. Different antibiotic treatments for group A streptococcal pharyngitis. Cochrane Database Syst Rev. 2016;9:CD004406.
- Altamimi S, Khalil A, Khalaiwi KA, Milner RA, Pusic MV, Al Othman MA. Short-term late-generation antibiotics versus longer term penicillin for acute streptococcal pharyngitis in children. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(8):CD004872.
- 清水博之, 齋藤美和子, 厚見恵, 久保田千鳥, 森雅亮. A群β溶連菌に対するペニシリン系とセフェム系抗菌薬の除菌率及び再発率. 日本小児科学会雑誌. 2013;117(10):1569-1573.
- Smith SM, Fahey T, Smucny J, Becker LA. Antibiotics for acute bronchitis. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(3):CD000245.
- Cherry J, Demmler-Harrison GJ, Kaplan SL, Steinbach WJ, Hotez P. Feigin and Cherry’s Textbook of Pediatric Infectious Diseases. 7th edition. PA: Saunders; 2013.
- Esposito S, Bosis S, Faelli N, et al. Role of atypical bacteria and azithromycin therapy for children with recurrent respiratory tract infections. Pediatr Infect Dis J. 2005;24(5):438-444.
- Velissariou IM, Papadopoulos NG, Giannaki M, Tsolia M, Saxoni-Papageorgiou P, Kafetzis DA. Mycoplasma pneumoniae and Chlamydia pneumoniae chronic cough in children: efficacy of clarithromycin. Int J Antimicrob Agents. 2005;26(2):179-180.
- Tiwari T, Murphy TV, Moran J, National Immunization Program, CDC. Recommended antimicrobial agents for the treatment and postexposure prophylaxis of pertussis: 2005 CDC Guidelines. MMWR Recomm Rep. 2005;54(RR-14):1-16.
- Altunaiji S, Kukuruzovic R, Curtis N, Massie J. Antibiotics for whooping cough (pertussis). Cochrane Database Syst Rev. 2007;(3):CD004404.
- 厚生労働省保険局医療課長通知, 保医発 0926 第1号, 医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて, 令和4年9月 26 日
- Cals JWL, Hopstaken RM, Butler CC, Hood K, Severens JL, Dinant G-J. Improving management of patients with acute cough by C-reactive protein point of care testing and communication training (IMPAC3T): study protocol of a cluster randomised controlled trial. BMC Fam Pract. 2007;8:15.
- Cals JWL, Butler CC, Hopstaken RM, Hood K, Dinant G-J. Effect of point of care testing for C reactive protein and training in communication skills on antibiotic use in lower respiratory tract infections: cluster randomised trial. BMJ. 2009;338:b1374.
- Little P, Stuart B, Francis N, et al. Effects of internet-based training on antibiotic prescribing rates for acute respiratory-tract infections: a multinational, cluster, randomised, factorial, controlled trial. Lancet. 2013;382(9899):1175-1182.
- Mangione-Smith R, Elliott MN, Stivers T, McDonald LL, Heritage J. Ruling out the need for antibiotics: are we sending the right message? Arch Pediatr Adolesc Med. 2006;160(9):945-952.
- Cabral C, Ingram J, Hay AD, Horwood J, TARGET team. “They just say everything’s a virus”--parent’s judgment of the credibility of clinician communication in primary care consultations for respiratory tract infections in children: a qualitative study. Patient Educ Couns. 2014;95(2):248-253.
- Mangione-Smith R, Zhou C, Robinson JD, Taylor JA, Elliott MN, Heritage J. Communication practices and antibiotic use for acute respiratory tract infections in children. Ann Fam Med. 2015;13(3):221-227.
- Spurling GKP, Del Mar CB, Dooley L, Foxlee R, Farley R. Delayed antibiotics for respiratory infections. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(4):CD004417.
- Little P, Moore M, Kelly J, et al. Delayed antibiotic prescribing strategies for respiratory tract infections in primary care: pragmatic, factorial, randomised controlled trial. BMJ. 2014;348:g1606.
- de la Poza Abad M, Mas Dalmau G, Moreno Bakedano M, et al. Prescription Strategies in Acute Uncomplicated Respiratory Infections: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2016;176(1):21-29.
- 河添仁, 上野昌紀, 済川聡美, 田中守, 田中亮裕, 荒木博陽. S-1における院外処方せんを利用した双方向性の情報共有の取り組みとその評価. 医療薬学. 2014;40(8):441-448.
- 阪口勝彦, 藤原大一朗, 山口有香子, 奥村麻佐子. 臨床検査値を表示した院外処方せんによる薬剤師業務への影響と課題. 日本病院薬剤師会雑誌. 2016;52(9):1131-1135.
- World Health Organization. The treatment of diarrhoea : A manual for physicians and other senior health workers, 4th rev. https://apps.who.int/iris/handle/10665/43209. 最終閲覧日2023年3月24日.
- Riddle MS, DuPont HL, Connor BA. ACG Clinical Guideline: Diagnosis, Treatment, and Prevention of Acute Diarrheal Infections in Adults. Am J Gastroenterol. 2016;111(5):602-622.
- Kasper AF Stephen Hauser, Dan Longo, J Jameson, Joseph Loscalzo Dennis. Harrison's Principles of Internal Medicine 19th edition. New York: McGraw-Hill Professional; 2015.
- JAID/JSC感染症治療ガイド・ガイドライン作成委員会 腸管感染症ワーキンググループ. JAID/JSC感染症治療ガイドライン2015 -腸管感染症-. 感染症学雑誌. 2016;90(1):31-65.
- 国立感染症研究所. 感染性胃腸炎. 感染症発生動向調査週報. 2017;19(1):7-8.
- 国立感染症研究所, 厚生労働省健康局結核感染症課. ロタウイルス胃腸炎の発生動向とワクチン導入後の報告数の推移. 病原微生物検出情報. 2015;36(7):145-146.
- 国立感染症研究所ホームページより, https://www.niid.go.jp/niid/ja/allarticles/surveillance/2270-idwr/nenpou/11638-syulist2021.html. 最終閲覧日2023年9月25日.
- Cohen SH, Gerding DN, Johnson S, et al. Clinical Practice Guidelines for Clostridium difficile Infection in Adults: 2010 Update by the Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) and the Infectious Diseases Society of America (IDSA). Infect Control Hosp Epidemiol. 2010;31(5):431-455.
- Beeching N, Gill G. Lecture Notes: Tropical Medicine. 7th edition. West Sussex: Wiley-Blackwell; 2014.
- DuPont HL. Acute infectious diarrhea in immunocompetent adults. N Engl J Med. 2014;370(16):1532-1540.
- Scorza K, Williams A, Phillips JD, Shaw J. Evaluation of nausea and vomiting. Am Fam Physician. 2007;76(1):76-84.
- Fontanarosa PB, Kaeberlein FJ, Gerson LW, Thomson RB. Difficulty in predicting bacteremia in elderly emergency patients. Ann Emerg Med. 1992;21(7):842-848.
- Felton JM, Harries AD, Beeching NJ, Rogerson SJ, Nye FJ. Acute gastroenteritis: the need to remember alternative diagnoses. Postgrad Med J. 1990;66(782):1037-1039.
- Kollaritsch H, Paulke-Korinek M, Wiedermann U. Traveler’s Diarrhea. Infect Dis Clin North Am. 2012;26(3):691-706.
- Vernacchio L, Vezina RM, Mitchell AA, Lesko SM, Plaut AG, Acheson DWK. Diarrhea in American infants and young children in the community setting: incidence, clinical presentation and microbiology. Pediatr Infect Dis J. 2006;25(1):2-7.
- King CK, Glass R, Bresee JS, Duggan C, Centers for Disease Control and Prevention. Managing acute gastroenteritis among children: oral rehydration, maintenance, and nutritional therapy. MMWR Recomm Rep. 2003;52(RR-16):1-16.
- Talan D, Moran GJ, Newdow M, et al. Etiology of bloody diarrhea among patients presenting to United States emergency departments: prevalence of Escherichia coli O157:H7 and other enteropathogens. Clin Infect Dis. 2001;32(4):573-580.
- Division of Viral Diseases, National Center for Immunization and Respiratory Diseases, Centers for Disease Control and Prevention. Updated norovirus outbreak management and disease prevention guidelines. MMWR Recomm Rep. 2011;60(RR-3):1-18.
- Glass RI, Parashar UD, Estes MK. Norovirus gastroenteritis. N Engl J Med. 2009;361(18):1776-1785.
- Rockx B, De Wit M, Vennema H, et al. Natural history of human calicivirus infection: a prospective cohort study. Clin Infect Dis. 2002;35(3):246-253.
- Lopman BA, Reacher MH, Vipond IB, Sarangi J, Brown DWG. Clinical manifestation of norovirus gastroenteritis in health care settings. Clin Infect Dis. 2004;39(3):318-324.
- 田中智之. ノロウイルス抗原迅速診断薬クイックナビTM-ノロ2の評価. 医学と薬学. 2012;68(6):1033-1039.
- 山崎勉, 由井郁子, 森島直哉, 黒木春郎. 金コロイドを用いた新規イムノクロマト法による便中ノロウイルス検出試薬の有用性. 感染症学雑誌. 2013;87(1):27-32.
- 渡部雅勝, 武蔵由紀, 鈴木千代子, 渡部あい子, 板橋志穂, 小野弘美. イムノクロマトグラフィーを用いたノロウイルス迅速診断キットの臨床評価. 医学と薬学. 2014;71(10):1917-1926.
- 山崎勉, 由井郁子, 森島直哉, 黒木春郎. イムノクロマト法による便中ノロウイルス検出キットの評価 -検体種による差の検討-. 感染症学雑誌. 2016;90(1):92-95.
- Kelly P. Infectious diarrhoea. Medicine (Baltimore). 2011;39(4):201-206.
- 内閣府食品安全委員会. ファクトシート(科学的知見に基づく概要書). https://www.fsc.go.jp/factsheets/. 最終閲覧日2023年3月24日.
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Diarrhoea and vomiting caused by gastroenteritis in under 5s: diagnosis and management | Guidance and guidelines. https://www.nice.org.uk/guidance/cg84?unlid=6082725412017216194549. 最終閲覧日2023年3月24日.
- Caeiro JP, DuPont HL, Albrecht H, Ericsson CD. Oral rehydration therapy plus loperamide versus loperamide alone in the treatment of traveler’s diarrhea. Clin Infect Dis. 1999;28(6):1286-1289.
- Simel D, Rennie D. The Rational Clinical Examination: Evidence-Based Clinical Diagnosis. 1st edition. New York: McGraw-Hill Education / Medical; 2008.
- Farthing M, Salam MA, Lindberg G, et al. Acute diarrhea in adults and children: a global perspective. J Clin Gastroenterol. 2013;47(1):12-20.
- Onwuezobe IA, Oshun PO, Odigwe CC. Antimicrobials for treating symptomatic non-typhoidal Salmonella infection. Cochrane Database Syst Rev. 2012;11:CD001167.
- DuPont HL. Clinical practice. Bacterial diarrhea. N Engl J Med. 2009;361(16):1560-1569.
- Ternhag A, Asikainen T, Giesecke J, Ekdahl K. A meta-analysis on the effects of antibiotic treatment on duration of symptoms caused by infection with Campylobacter species. Clin Infect Dis. 2007;44(5):696-700.
- Freedman SB, Xie J, Neufeld MS, et al. Shiga Toxin-Producing Escherichia coli Infection, Antibiotics, and Risk of Developing Hemolytic Uremic Syndrome: A Meta-analysis. Clin Infect Dis. 2016;62(10):1251-1258.
- Ikeda K, Ida O, Kimoto K, Takatorige T, Nakanishi N, Tatara K. Effect of early fosfomycin treatment on prevention of hemolytic uremic syndrome accompanying Escherichia coli O157:H7 infection. Clin Nephrol. 1999;52(6):357-362.
- Tajiri H, Nishi J, Ushijima K, et al. A role for fosfomycin treatment in children for prevention of haemolytic-uraemic syndrome accompanying Shiga toxin-producing Escherichia coli infection. Int J Antimicrob Agents. 2015;46(5):586-589.
- Myojin S, Pak K, Sako M, et al. Interventions for Shiga toxin-producing Escherichia coli gastroenteritis and risk of hemolytic uremic syndrome: A population-based matched case control study, ProS One, 2022;17(2):e0263349.
- Bell BP, Griffin PM, Lozano P, Christie DL, Kobayashi JM, Tarr PI. Predictors of hemolytic uremic syndrome in children during a large outbreak of Escherichia coli O157:H7 infections. Pediatrics. 1997;100(1):E12.
- Spurling GKP, Del Mar CB, et al. Delayed antibiotic prescriptions for respiratory infections. Cochrane Database Syst Rev. 2017;9(9):CD004417.
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Respiratory tract infections (self-limiting): prescribing antibiotics | Clinical guideline. 2008. https://www.nice.org.uk/guidance/cg69?unlid=345604181201722763. 最終閲覧日2023年3月24日.
- Ryves R, Eyles C, Moore M, McDermott L, Little P, Leydon GM. Understanding the delayed prescribing of antibiotics for respiratory tract infection in primary care: a qualitative analysis. BMJ Open. 2016;6(11):e011882
一般外来における乳幼児編
8. 小児における急性気道感染症の特徴と注意点
- 小児における急性気道感染症の多くを占める、感冒・鼻副鼻腔炎、咽頭炎、クループ(喉頭炎)、気管支炎、細気管支炎を本手引きでは取り上げる。基礎疾患のない小児(生後3か月以降~小学校入学前)を対象とし、重症例の管理は対象外とする。
– これらの疾患と抗菌薬が必要となるA群溶連菌による咽頭炎、細菌性副鼻腔炎、百日咳、非定型肺炎を鑑別する。
– 二次性の細菌感染症により経過が遷延し増悪する可能性があり、適宜再受診が必要である。ただし、予防的な投与はすべきでない。- 小児では年齢ごとのリスクを加味する必要がある。
– 生後3か月未満の新生児・早期乳児における気道感染症の鑑別には重篤な疾患が含まれるため、小児の診療に慣れた医師による診察が必要である。
– 生後3か月以上の乳幼児における気道感染症では、感冒・鼻副鼻腔炎・咽頭炎の明確な区別は難しい。乳幼児に特徴的な症候群としてクループ症候群や細気管支炎がある。また中耳炎の合併に注意が必要である。重症細菌感染症の鑑別(深頸部膿瘍、細菌性喉頭蓋炎、細菌性気管支炎、細菌性肺炎)を診察時には考慮し、熱源が明らかでない場合は、尿路感染症や潜在性菌血症の鑑別が必要である。強い咳嗽や流行を認めた場合、百日咳の可能性を検討する。
– 学童期(小学生)以降は、感冒、急性鼻副鼻腔炎、咽頭炎、気管支炎を分けて定義し、診療する。(成人学童期編を参照)
- 急性気道感染症の治療に用いられる治療薬には、小児に特有の副作用が知られているものがある。
(1) 小児の急性気道感染症の特徴と分類
急性気道感染症の原因の多くは、自然軽快するウイルス性疾患である1。その中で、抗菌薬による治療が必要となる状態を見逃さず診療することが求められる。成人では、主だった症状から急性気道感染症を感冒・鼻副鼻腔炎・咽頭炎・気管支炎に分類することで治療適応を判別したが、小児でも、学童期以降であれば合併症の危険性は低く、また症状を訴えることができるようになることから、同様の診療を行う事が可能であると考えられる。小児の感染症を扱う海外のガイドラインも5歳をカットオフとしている2。
一方で、低年齢の小児の場合は呼吸器ウイルスの感染による気道の炎症は上気道から下気道に及び鼻汁や咳嗽はしばしば混在し、咽頭痛の訴えも不確かであることから、成人と同様に急性気道感染症を分類することは容易ではない。厳密な病名は炎症の主座や原因微生物によって規定されるが、臨床的には年齢、症状と身体所見をあわせ、感冒・鼻副鼻腔炎、咽頭炎、クループ症候群、気管支炎、細気管支炎と診断される(図1)。COVID-19は、咳嗽および発熱がよく見られる症状であるが、無症状の場合もある。COVID-19流行地域ではCOVID-19を考慮する。教科書や文献上は様々な表記や分類が存在するが、本手引きでは抗菌薬適正使用の観点から、抗菌薬が不要であるウイルス感染症を臨床的に定義した。小児では、これらのウイルス性疾患と細菌感染症やその他の病態との鑑別が診療の上で重要となる。
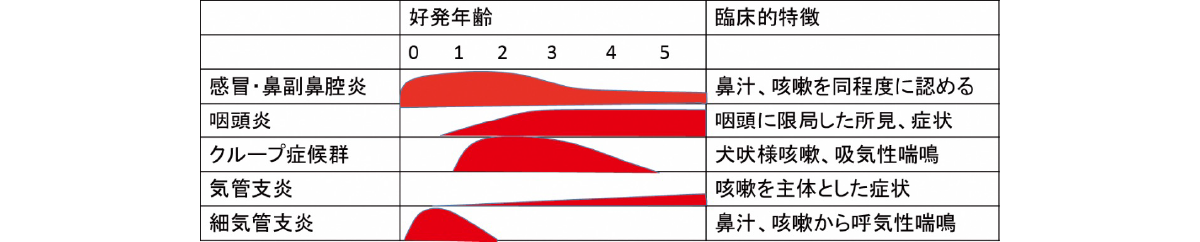
図1. 小児気道感染症の分類
(i) 小児における年齢と感染症の関係
小児では、年齢ごとに考慮すべき病態や合併症の頻度が異なり、年齢を加味した診療が必要である。
| 生後3か月未満の乳児 | 本手引きでは、生後3か月未満の乳児は対象としない。原則として、小児診療に慣れた医師による診察が必要である。 |
|---|---|
| 生後3か月以降の乳幼児 | 生後3か月以降の乳幼児において、鼻汁、軽い咳等の上気道症状をきたす疾患については感冒・鼻副鼻腔炎と広く定義する。成人においては、感冒は急性気道感染症のうち鼻症状・咽頭症状・下気道症状が同時に同程度存在する状態としているが、乳幼児においては症状の明確な区別が困難である。小児に特有な疾患として犬吠様咳嗽を特徴とするクループ症候群また、喉頭炎、下気道症状をきたす疾患として喘鳴を主徴とする細気管支炎がある。これらの疾患は、原則としてウイルス性疾患であり、抗菌薬投与は不要であるが3,4、鑑別となる重症細菌感染症を除外する必要があり、ウイルス性疾患の有無に関わらず中耳炎、潜在性菌血症や尿路感染症について考慮する必要がある。同時に、抗菌薬の適応病態として、幼児であってもA群β溶連菌感染症、百日咳やマイコプラズマ肺炎に注意が必要である。 |
| 学童期以降の小児 | 学童期以降の小児においては、症状や身体所見から成人と同様の疾患定義に基づいて感冒、急性鼻副鼻腔炎、急性咽頭炎、急性気管支炎を診断することが可能である(手引き成人学童期編参照)。同時に、抗菌薬の適応病態として、A群β溶連菌感染症、百日咳やマイコプラズマ肺炎に注意が必要である。 |
(2) 小児の急性気道感染症の鑑別
本手引きの対象となる感冒・鼻副鼻腔炎、咽頭炎、クループ症候群、気管支炎、細気管支炎は急性気道感染症の大多数を占め、原則自然軽快する。日常診療において、抗菌薬の適応となる主な細菌感染症は、3歳以降におけるA群β溶血性連鎖球菌による咽頭炎、感冒・鼻副鼻腔炎が遷延して起こる細菌性副鼻腔炎、中耳炎や肺炎が挙げられる。これらについては、臨床診断に基づき診断し抗菌薬投与の適応を決定する。
その一方で、小児においては重症な疾患あるいは重症化しうる病態を除外することも必要である(図2)。まずは、全身状態の悪い患者の除外が前提となる。小児の診療ではしばしば、「なんとなく具合が悪い」状態から重症感染症を拾い上げることが求められる。重症患者を見逃さないための客観的な指標として外観・皮膚の循環・呼吸状態を評価するPediatric Assessment Triangle(PAT)(図3)が用いられ、看護師や救急救命士等によるスクリーニングが可能となっている5。
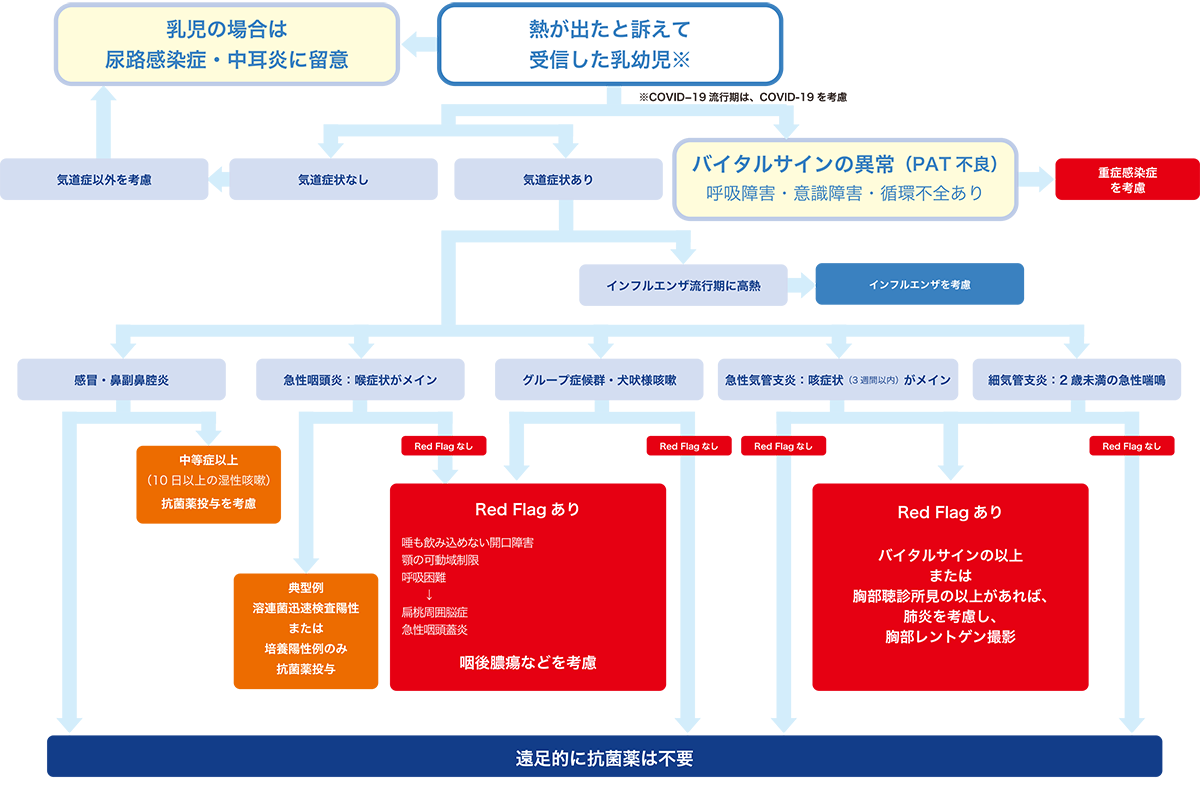
図2. 小児気道感染症の診療フロー
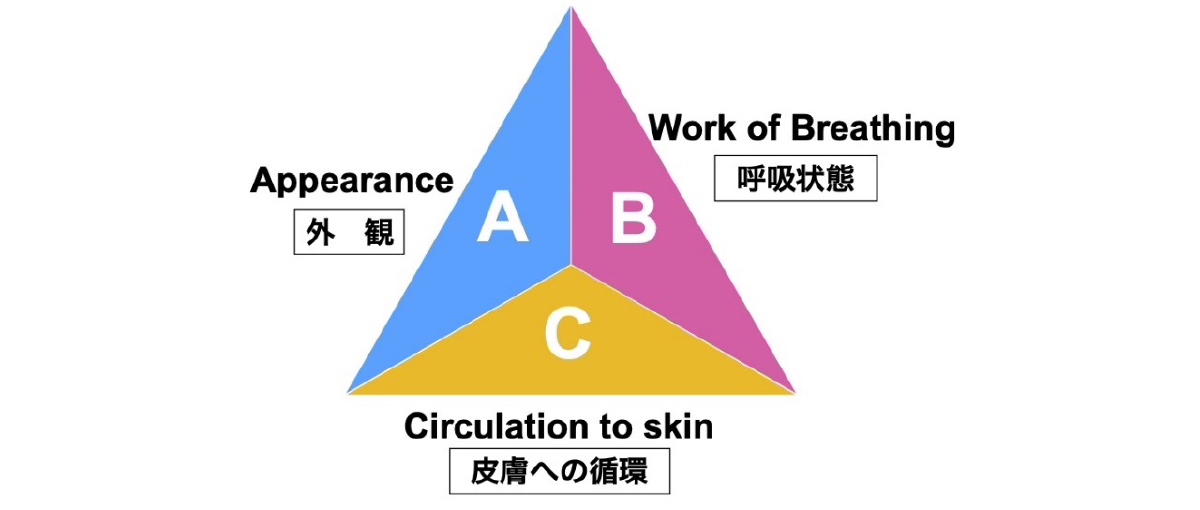
図3. Pediatric Assessment Triangle (PAT)
西山和孝 PATを用いたトリアージの有用性 医学書院第2865号2010年を参考に作成
また、急性気道感染症を診断した場合でも、その合併症や鑑別を身体所見から除外する必要性は高い。具体的には、細菌性副鼻腔炎や中耳炎の合併症としての眼窩蜂窩織炎や乳突洞炎、咽頭炎の鑑別としての深頸部膿瘍、クループ症候群の鑑別として急性喉頭蓋炎や細菌性気管炎、下気道感染症における細菌性肺炎の合併等が挙げられる。通常の自然経過を知り、改善が乏しい場合あるいは二峰性の経過をたどる場合は精査を検討する。適切な検査や診断に基づいて抗菌薬治療の適応を判断する必要があり、安易に発熱のみだけでは、抗菌薬治療の適応にならない。
さらに、急性気道感染症を診断した場合でも、乳幼児においては異なる病態が混在していることがある。乳幼児において頻度が高いのは、急性中耳炎、尿路感染症、潜在性菌血症が挙げられる。急性中耳炎は小児の診察の一環として鼓膜の所見を取ることで除外する。臨床経過や所見が他の有熱性疾患に矛盾しない場合には、尿路感染症の除外検査は必要ないが、高熱を呈し他の所見に乏しい場合は尿検査等を考慮する。発熱を呈している一見元気な生後3か月から36か月の乳幼児では、明らかな所見がなくとも一定の割合で、肺炎球菌や H. influenzaeによる菌血症をきたし、約7%は細菌性髄膜炎等の重症感染症になることが過去に報告されてきた6。このような状態を潜在性菌血症(occult bacteremia)と呼び、39.5℃以上の高熱、高白血球血症(15,000/μL)のある患者については、5〜10%のリスクがあるとされ、血液培養を採取して抗菌薬投与を推奨する診療もかつては行われていた。しかし肺炎球菌ワクチンやヒブワクチン導入後は、リスクが大幅に減少したため、これらのワクチン歴のある患者については必ずしも行う必要はない。
丁寧な問診と診察に基づいて細菌感染症の鑑別を行い、保護者に病状と疾患の自然経過を説明し、再受診の目安について情報提供を行うことが重要である。なお、本手引きは、外来での小児診療において、抗菌薬が必要な病態と不必要な病態を明らかにすることに主眼を置いているため、抗菌薬の適応となる細菌感染症の治療法を網羅した内容とはなっていない。その点については、学会による指針等を参照頂きたい。
(3) 小児において気をつけるべき薬剤について
急性気道感染症に関連する薬剤のうち、小児特有の副作用が懸念される薬剤がある。また多くの対症療法薬にはエビデンスが存在せず、副作用も報告されている。使用にあたっては添付文書の記載等に注意が必要である。
表1. 小児特有の副作用が懸念される薬剤
| 薬剤 | 懸念事項 |
|---|---|
| ST合剤 | 低出生体重児、新生児(生後28日未満)は核黄疸のリスクがあり禁忌である7。 (一般的に生後2か月以内は投与を避ける) |
| セフトリアキソン | 高ビリルビン血症のある早産児・新生児は核黄疸のリスクがあり禁忌、カルシウムを含有する輸液製剤との併用で結晶化するため注意が必要である8。 |
| マクロライド系抗菌薬 | 新生児期における内服で肥厚性幽門狭窄症のリスクが上がる9。(特にエリスロマイシンだが、アジスロマイシンでも報告あり) |
| テトラサイクリン系 抗菌薬 |
8歳未満の小児では歯牙着色のリスクがあるため8歳未満では他に代替薬がない場合を除き使用しない10(テトラサイクリン、ミノサイクリン、ドキシサイクリン)。 |
| ピボキシル基を有する 抗菌薬 |
低カルニチン血症に伴って低血糖症、痙攣、脳症等を起こし、後遺症に至る症例も報告されている。 <セフカペン、セフジトレン、セフテラム、テビペネム> |
| フルオロキノロン系 抗菌薬 |
幼若動物への投与により関節障害が報告され、小児には投与禁忌となっている薬剤がある。(シプロフロキサシン、レボフロキサシン、ガレノキサシン等) |
| アセチルサリチル酸、 メフェナム酸、ジクロフェナクナトリウム等の解熱鎮痛剤、 あるいは総合感冒薬 |
小児のインフルエンザや水痘罹患時に急性脳症発症に関連する。 厚生労働省の重篤副作用疾患別対応マニュアル「小児の急性脳症」(平成23年3月)を参照。 |
| 抗ヒスタミン薬 | 熱性けいれんを誘発するリスク、急性脳症発症に関連することが報告されている。 厚生労働省の重篤副作用疾患別対応マニュアル「小児の急性脳症」(平成23年3月)を参照 |
| ジヒドロコデイン | 呼吸抑制作用の強いジヒドロモルヒネに代謝されるため、米国では12歳未満の小児へは禁忌となっている。(日本小児科学会誌雑誌 2018;122:1186-1190) |
| テオフィリン製剤 | 急性脳症発症に関連する厚生労働省の重篤副作用疾患別対応マニュアル「小児の急性脳症」(平成23年3月)を参照。 急性脳症との因果関係に関して、結論は出ていないものの議論がなされている。 |
| ロペラミド | ロペラミドは乳児で腸閉塞の発症が報告され、6か月未満は禁忌である。6か月以上2歳未満の乳幼児は治療上やむを得ないと判断される場合を除き投与しない。 |
9. 小児の急性気道感染症各論
(1) 感冒・急性鼻副鼻腔炎
- ウイルスによる急性の上気道感染症で、鼻汁、鼻閉が主体である。発熱、筋肉痛、頭痛、咳、咽頭痛、嗄声、不機嫌、睡眠障害、食欲不振、嘔吐、下痢等をきたすこともある11。
- 感冒では、鼻炎の症状が主体であるが、自然治癒する副鼻腔炎を合併することも多く、急性鼻副鼻腔炎を含む11,12。
- 食欲不振、飲水不良等による脱水症状に気をつけ、経口補液を勧める(急性下痢症の項目を参照)
【抗菌薬に関する推奨】
- 感冒・急性副鼻腔炎に対して、抗菌薬投与を投与しないことを推奨する。また、抗菌薬の予防的投与を行わないことを推奨する。
- 初期診断が感冒・急性副鼻腔炎であっても、呼吸状態等が増悪する例、湿性咳嗽が10日以上続く例、軽快後に再増悪する例については、抗菌薬の適応となるような化膿性副鼻腔炎、細菌性肺炎、化膿性中耳炎等を鑑別する。気道系や中耳炎であれば、初期治療はアモキシシリン投与を考慮する。非定型肺炎が考えられる場合は、必要があればマクロライド系抗菌薬を投与する。
(i) 感冒とは
小児における感冒では、咳、咽頭痛といった気道症状に加え、発熱、嗄声、頭痛、筋肉痛、不機嫌、睡眠障害、食欲不振、嘔吐、下痢等多様な症状をきたすこともある11。また、乳幼児では急性鼻副鼻腔炎も合併していることも多いため、感冒と急性鼻副鼻腔炎との明確な区別は難しく、臨床的にはこれらを区別する意義は少なく、細菌による二次感染の有無を鑑別することが求められる。
(ii) 感冒の疫学
乳幼児を中心に小児は年平均6〜8回感冒に罹患し、小児の10〜15%は年に最低12回罹患するが年齢とともに罹患は減少する1,11。感冒については、年間を通して罹患するが、主に冬の前後の時期に多い。集団保育児では、自宅でみている乳幼児より罹患しやすい。感染経路は、接触および飛沫感染であり13、感染してから1〜3日の潜伏期間で症状が出る場合が多い13。
(iii) 診断と鑑別
鼻汁、軽度の咳等の急性の上気道中心の症状で疑い、症状および身体所見による臨床診断が主体である。感冒症状のある者との接触歴も重要である4。
一般的には2〜3日をピークに症状は自然軽快する。10日以内に消失することが多いが軽い症状は2〜3週続くことも稀ではない1。軽快傾向が認められた後に再増悪する場合や発熱が3日以上続く場合は細菌性の二次感染症を考慮する。また、抗菌薬が適応の化膿性鼻副鼻腔炎は、10日以上、症状が遷延することが多い13,14。
治療すべき鑑別疾患の除外も重要である11。鑑別診断は、アレルギー性鼻炎、下気道炎、気道異物、A群β溶血性連鎖球菌感染症、百日咳等である11。感冒では聴診で喉頭の狭窄音(stridor)、肺呼吸音で喘鳴(wheeze)やラ音(crackles)等は伴わないことが鑑別の際の一助になる。
小児は脱水に陥りやすく、水分摂取の状況を聴取し、排尿の有無を確認し、脱水の身体所見がないかの評価も大事である15。
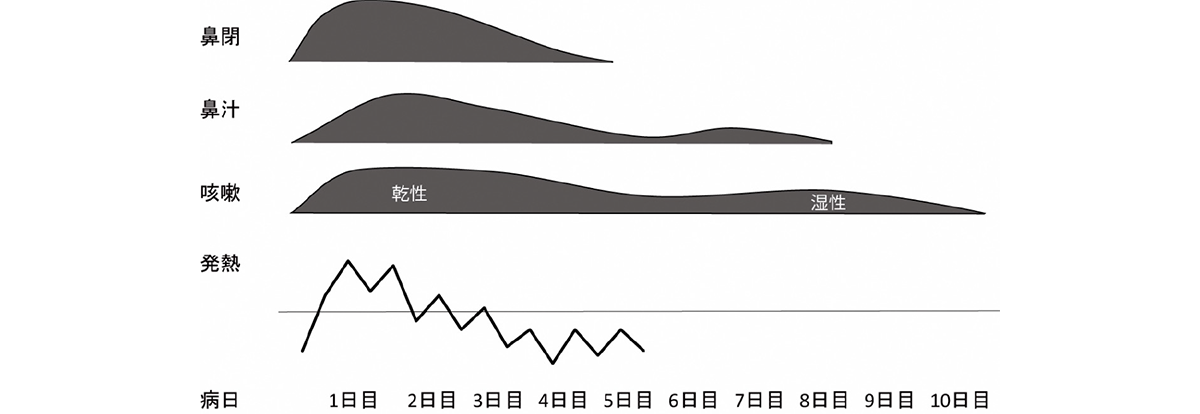
図4. 感冒の自然経過
(iv) 治療方法
発熱、咽頭痛等に対しては、適宜、アセトアミノフェン等の解熱鎮痛剤による対症療法を行う12,16。また、脱水にならないように経口補液を指導する。
(v) 抗菌薬治療
感冒や急性鼻副鼻腔炎に対して抗菌薬は必要ないことが指摘されている14,17-23。ウイルス感染症の経過中の細菌感染症の合併を予防するために抗菌薬を投与することについては、軽症の感冒・鼻副鼻腔炎・咽頭炎・気管支炎患者に対して、抗菌薬投与の有無による症状の改善の有無を比較した複数の無作為化比較試験では差は認められていない17。0歳から12歳の小児を対象とした12個の無作為化比較試験をまとめた系統的レビューにおいても、上気道炎に対する抗菌薬投与は症状緩和や合併症減少に寄与しなかったと報告されている24。なお、乳突洞炎、扁桃周囲膿瘍、肺炎患者を対象とした後方視的検討では、理論上は1名の重篤な細菌感染症を予防するためには2,500人以上の非特異的な上気道感染症患者に抗菌薬を投与する必要があると試算される25。このようなことから、予防目的での抗菌薬は原則として投与しないことを推奨する。
膿性鼻汁を認める小児に抗菌薬投与が行われることがあるが、急性上気道炎患者あるいは膿性鼻汁のある患者に対する抗菌薬と偽薬群(プラセボ薬)との比較で有効性を検討した無作為化比較試験をまとめた系統的レビュー17によると、小児と成人を対象とした6つの検討、あるいは小児を対象とした2つの無作為化比較試験では、第7病日における症状改善率に差を認めなかった。また、成人を対象とした4つの無作為化比較試験における有害事象の頻度は、抗菌薬投与群で相対危険度が2.62(95%信頼区間 1.32-5.18)と高かった17が、小児を対象とした2つの無作為化比較試験では相対危険度は0.91(95%信頼区間 0.51-1.63)と差が認められなかった17。また、4つの無作為化比較試験では膿性鼻汁の発生についても相対危険度1.46(95%信頼区間 1.10-1.94)と有意な差は認められなかった17。直近で2~11歳の小児を対象に行われたランダム化比較試験においても、黄色又は緑色の鼻汁の有無で抗菌薬の有用性に差を認めなかったと報告されている。
※したがって、膿性鼻汁を認めるだけでは、原則、抗菌薬は不要である26,27。
【抗菌薬投与が不適切と考えられる基準】
以下をすべて満たす患者にはその時点で抗菌薬は必要ない
- 鼻汁
- 鼻閉 ± 発熱 ± 軽い咳
- 呼吸障害がない
- 全身状態が良い
- 熱の持続期間が3日以内
- 鼻汁の持続期間が10日以内
- 湿性咳嗽の持続期間が10日(2週間)以内
感冒・鼻副鼻腔炎が遷延し、化膿性合併症をきたす可能性はあり、その見極めは重要である。化膿性副鼻腔炎は、通常、副鼻腔の発達した学童以降に多く、頬部の発赤、疼痛、鼻閉等を伴うことが指摘されている28。また、湿性咳嗽を10日以上呈する症例、すなわち化膿性副鼻腔炎あるいは遷延する気管支炎に該当する小児症例を含んだ検討では、抗菌薬投与による症状改善が認められている29。140名の患者を含む2つの研究では、抗菌薬未投与群に比して抗菌薬投与群における臨床的な治療失敗例のオッズ比は0.13(95%信頼区間 0.06-0.31)であった。
【抗菌薬投与を考慮すべき状態】
以下のいずれかに当てはまる場合、遷延性又は重症と判定する。
- 10日間以上続く鼻汁・後鼻漏や日中の咳を認めるもの。
- 39℃以上の発熱と膿性鼻汁が少なくとも3日以上続き重症感のあるもの。
- 感冒に引き続き、1週間後に再度の発熱や日中の鼻汁・咳の増悪が見られるもの。
日本鼻科学会の指針では、化膿性副鼻腔炎に対する処方例として、アモキシシリン40mg/kg/日(分3)7〜10日間と示されている。
- その他の抗菌薬が適応となるような合併症(化膿性中耳炎、細菌性肺炎、尿路感染症、菌血症等)を認める。原則、アモキシシリンが第一選択になることが多いが、非定型肺炎ではマクロライド系抗菌薬を必要があれば考慮する。
(vi) 患者および保護者への説明
海外の文献では、感冒で受診した患者や保護者の満足度は、抗菌薬処方の有無よりも、病状説明による安心感が得られたことにより強く依存していることが示されている30。説明における要点は、具体的な指導を行うことである。多くの場合は自然に治癒すること、自宅で実施可能な対症療法、再受診を促す目安となる多呼吸、起坐呼吸、努力呼吸、意識状態の低下、水分摂取不可で排尿が半日以上なくてぐったりしているなどあれば、医療機関の受診を勧める。
【医師から患者への説明例:感冒の場合】
- ウイルスによる「かぜ」です。「かぜ」の症状は自然に良くなりますが、完全に消えるまでは1〜2週間続くことがあります。比較的、元気で水分もとれていて、おしっこもよく出ているときは、熱がさがって症状が良くなるまで自宅で安静にしましょう。
- ウイルスには抗菌薬は効きません。必要もないのに服用することで、耐性菌という薬が効かない菌を作って将来、問題になったり、薬の副作用で下痢をしたりでかえって具合が悪くなることもあります。
- 発熱がある場合は安静にして、熱がこもらないように薄着にしてあげましょう。ただし手足が冷たい時や、寒気のする時は逆に保温して構いません。高熱があってだるそうにしている場合は、アセトアミノフェン等の解熱剤を用いても良いです。熱を下げることで食欲が出たり、水分がとれたりすることがあります。水分は、塩分を含んでいるものをあげましょう。鼻が詰まっている場合は、鼻をかむか、出来ない場合はぬぐってあげて、枕を使って上体を上げてあげるのも良いでしょう。
- 時々、中耳炎、副鼻腔炎や肺炎を起こすことがあります。3日以上発熱が続いて具合が悪い場合や、症状が悪くなる場合は再度受診してください。
- 特に苦しそうな呼吸をしていたり(肩で呼吸をしている、呼吸が苦しくて横になれない)、意識がおかしい場合、水分がとれなくて半日以上、おしっこが出てなくてぐったりしているときは、すぐに医療機関を受診してください。
<文献検索方法>
小児の感冒、急性鼻副鼻腔炎に関して、Nelson Textbook of Pediatrics (20th ed)、Feigin and Cherry's Textbook of Pediatric Infectious Diseases (7th ed)、Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases (8th ed)、日本小児感染症学会(JSPID)、日本感染症学会・日本化学療法学会(JAID/JSC)、米国感染症学会(IDSA)、欧州臨床微生物・感染症学会(ESCMID)等の専門家集団による現在の診療ガイドラインの推奨を踏まえつつ、最新のエビデンスを反映させるために第2版以降の文献検索を行った。
<MEDLINEでの検索式>
("common cold"[MeSH Terms] OR ("common"[All Fields] AND "cold"[All Fields]) OR "common cold"[All Fields]) AND ((Clinical Study[ptyp] OR Clinical Trial[ptyp] OR Comparative Study[ptyp] OR Controlled Clinical Trial[ptyp] OR Guideline[ptyp] OR Meta-Analysis[ptyp] OR Multicenter Study[ptyp] OR Observational Study[ptyp] OR Practice Guideline[ptyp] OR Randomized Controlled Trial[ptyp] OR systematic[sb]) AND "2018/09/04"[PDat] : "2023/01/31"[PDat] AND (English[lang] OR Japanese[lang]) AND ("infant"[MeSH Terms] OR "child, preschool"[MeSH Terms]))
結果42件がヒットした。(2018年9月4日~2023年1月31日)
rhinosinusitis[All Fields] AND ((Clinical Study[ptyp] OR Clinical Trial[ptyp] OR Comparative Study[ptyp] OR Controlled Clinical Trial[ptyp] OR Guideline[ptyp] OR Meta-Analysis[ptyp] OR Multicenter Study[ptyp] OR Observational Study[ptyp] OR Practice Guideline[ptyp] OR Randomized Controlled Trial[ptyp] OR systematic[sb]) AND "2018/09/04"[PDat] : "2023/01/31"[PDat] AND (English[lang] OR Japanese[lang]) AND ("infant"[MeSH Terms] OR "child, preschool"[MeSH Terms]))
結果20件がヒットした。(2018年9月4日~2023年1月31日)
<日本語論文(医中誌)での検索方法>
感冒、2008-2018、症例報告除く、原著論文、会議録除く、メタアナリシス、ランダム化比較試験、準ランダム化比較試験。比較試験、小児
結果10件がヒットした。(2018年9月4日~2023年1月31日)
急性鼻副鼻腔炎、2008-2018、症例報告除く、原著論文、会議録除く、メタアナリシス、ランダム化比較試験、準ランダム化比較試験。比較試験、小児
結果3件がヒットした。(2018年9月4日~2023年1月31日)
(2) 急性咽頭炎
- 急性咽頭炎は、感染性、非感染性要因による咽頭の急性炎症である。
- 急性咽頭炎では、その原因がA群β溶血性連鎖球菌(Group A β-hemolytic Streptococcus spp.: GAS)による感染症か否かを、臨床所見と検査結果を合わせて診断することが重要である。
- 迅速抗原検査又は培養検査でGASが検出されていない急性咽頭炎に対しては、抗菌薬投与を行わないことを推奨する。
- 迅速抗原検査又は培養検査でGASが検出された急性咽頭炎に対して、抗菌薬投与する場合には、以下の抗菌薬投与を推奨する。
【抗菌薬に関する推奨】
- アモキシシリン10日間経口投与
(i) 急性咽頭炎とは
急性咽頭炎とは、咽頭の発赤、腫脹、滲出物、潰瘍、水疱を伴う急性炎症である。咽頭の炎症の要因として、非感染性要因と感染性要因がある。非感染性の要因には、環境要因(たばこ、環境汚染物質、アレルゲン等)、食事要因(熱い食べ物や刺激物等)があり、また咽頭はPeriodic Fever, Aphthous Stomatitis, Pharyngitis, Adenitis(PFAPA)症候群や炎症性腸疾患等の自己炎症疾患による炎症の場ともなる。感染性要因と非感染性要因を鑑別するのは、病歴聴取や身体診察である。感染性要因の中で最も多いものは、成人と同様にウイルスである31,32。また、細菌性ではA群β溶血性連鎖球菌(Group A β-hemolytic Streptococcus spp.: GAS)によるものが重要である。
急性咽頭炎診療で重要なことは、急性喉頭蓋炎、頸部膿瘍、扁桃周囲膿瘍等の急性上気道閉塞性疾患を見逃さないことと、自然治癒するウイルス性咽頭炎と治療が必要な疾患(例えばGAS咽頭炎等)とを鑑別し、適切にフォローアップすることである。
(ii) 急性咽頭炎の疫学
急性咽頭炎と診断された小児患者のうち、GAS陽性例は日本における報告では16.3%32、海外における報告では27%とされている31。一方で咽頭培養から検出されるGASのすべてが急性咽頭炎の原因微生物ではなく、無症状の児の10~30%にGAS保菌が認められる33。GASによる急性咽頭炎は、5歳から12歳で頻度が高く、3歳未満児においては稀である。
(iii) 診断と鑑別
急性咽頭炎の診断の目的は、GASが原因微生物かどうかを判断することである。咽頭痛や嚥下痛を小児が正確に訴えることは困難で、頭痛や嘔吐を伴う発熱等の非特異的症状で咽頭炎を疑うことが重要である。小児(3~18歳)を対象としたGAS咽頭炎の症状の尤度比を評価した臨床研究によると、猩紅熱様皮疹や軟口蓋の点状出血斑の陽性尤度比が比較的高い32。ウイルス性咽頭炎とGAS咽頭炎の鑑別点を以下の表に記す。
表2. A群β溶血性連鎖球菌咽頭炎とウイルス性咽頭炎
| GAS咽頭炎 | ・ 突然発症 ・ 発熱 ・ 頭痛 ・ 嘔気・嘔吐 ・ 腹痛 ・ 圧痛を伴う前頸部リンパ節腫脹 ・ 猩紅熱様皮疹 |
|---|---|
| ウイルス性咽頭炎 | ・ 結膜炎 ・ 咳嗽 ・ 嗄声 ・ 鼻汁 ・ 筋肉痛 ・ 下痢 |
小児においてもCentorの基準が用いられるが、最も高いスコア(4点)の最高得点での陽性率は68%である35。スコア値のみで急性咽頭炎の原因がGASであると判断することは、過剰診断と治療につながる。そのことから、より正確な診断のために、検査診断が有用となる。
表3. Centorの基準
| 発熱38℃以上 | 1点 |
|---|---|
| 咳がない | 1点 |
| 圧痛を伴う前頸部リンパ節腫脹 | 1点 |
| 白苔を伴う扁桃炎 | 1点 |
避けるべきことは、検査過剰によるGAS保菌者や臨床像が類似するウイルスが原因である非GAS咽頭炎に対する抗菌薬治療である。そのためには、総合的に診断すること、すなわち患者を診察し、GAS咽頭炎の事前確率が高いと判断した症例に限り、適切に検査を行うことが重要である。また3歳未満では、GAS咽頭炎がそもそも少ないこと、続発する急性リウマチ熱(Acute rheumatic fever: ARF)の合併が少ないために、GAS咽頭炎患者と濃厚接触がある時を除いて、原則的には検査しないことが推奨されている36。
GAS検査の基本原則は、適応外の児に行うと保菌者を拾い上げ、過剰な抗菌薬使用につながるため、①検査適応(表)を吟味すること、②適応のある児に対して検査を行い、③迅速検査が陽性であれば培養は不要、の3点である。また臨床的にウイルス感染症の可能性が高い場合(すなわちGAS咽頭炎の事前確率の低い咳や鼻汁を認める場合等)は、検査しないことを推奨する。
表4. GAS迅速抗原検査の適応
以下の1)、2)、3) を満たすもの
1) 急性咽頭炎の症状と症候があり、急性GAS咽頭炎が疑われる
2) 急性GAS咽頭炎の身体所見を有する
3) 原則、3歳以上(周囲で流行していている場合はその限りではない)
GAS迅速抗原検査の検査特性は、感度は70〜90%、特異度95%である37。感度は研究ごとに幅あり、特異度はほぼ一定である。特異度は優れているため、検査陽性であれば、追加の培養検査は不要と言える。その一方で、検査陰性の場合は、二度繰り返しても陽性率は向上しないので、検査を繰り返す意味は少ない38。
培養検査は、GAS咽頭炎の診断において標準的な検査法である37。しかしながら、流行期においてはGASの保菌者は20%ほど見られ、その状況が6か月以上持続するため、GAS保菌者のウイルス性咽頭炎では、鑑別が困難になる。このようなことから、培養検査の実施については、実際に臨床的にGASの可能性が高いが迅速抗原検査陰性の場合の追加に留めるべきである。
重要な鑑別疾患(レッドフラッグ
急性喉頭蓋炎、頸部膿瘍、扁桃周囲膿瘍等の急性上気道閉塞性疾患
急激に全身状態が悪化し、喘鳴、姿勢の異常(sniffing positionやtripod position)や流涎が目立つ。これらの疾患においては、短時間で窒息にいたる可能性があり、口腔内の診察はもとより採血やレントゲン検査等の、患児にストレスを与えることは避けて、児の楽な姿勢のままで、安全に気道確保できる施設への転院を速やかに決断することが重要である。
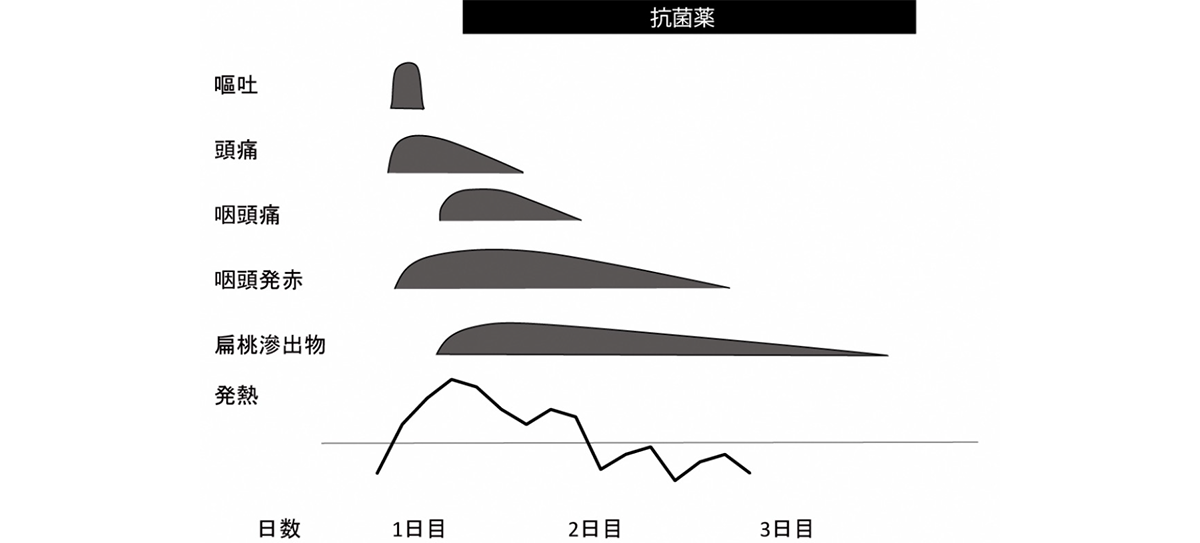
図5. 急性溶連菌性咽頭炎の自然経過
(iv) 抗菌薬治療
上述のように、急性咽頭炎の多くはウイルス性で抗菌薬の適応ではない。一方で、抗菌薬処方を迅速検査又は培養検査でGASが検出された場合のみに限ると、不要な抗菌薬使用を減らすことができるという報告が存在する39。
このことから、本手引きでは、GAS咽頭炎が強く疑われ、かつ、迅速抗原検査もしくは培養検査において陽性であった場合にのみ、抗菌薬投与を検討することを推奨する。
以下、GAS咽頭炎の治療法を主体に述べる。
① GAS咽頭炎の治療目的
GASによる急性咽頭炎に対する抗菌薬使用の目的は3つある。
第一目的は、GAS除菌による急性リウマチ熱(Acute rheumatic fever: ARF)予防である。GAS咽頭炎発病から9日以内の抗菌薬開始でARF予防効果が証明されている40。
第二の目的は、速やかな症状緩和である。一般的にGAS咽頭炎による諸症状は3〜4日で軽快するが、抗菌薬はその有症状期間を半日から1日短くする41。
第三の目的は、周囲への感染伝播防止である。早期の抗菌薬開始で、周囲への伝播を減らすことができる42。その結果、保護者が早期に職場復帰できることより、社会的損失を回避することが可能となる。
② GAS咽頭炎に対する第一選択抗菌薬
GASはすべてのペニシリン系抗菌薬に対して感性である。IDSAのガイドラインではペニシリン系抗菌薬が推奨されている43。また日本の小児呼吸器感染症診療ガイドライン2022では、GAS咽頭炎にはアモキシシリン、又はベンジルペニシリンベンザチンが第一選択抗菌薬として推奨されている44。
③ GAS咽頭炎に対する抗菌薬投与量と投与間隔
小児呼吸器感染症診療ガイドライン2022ではアモキシシリンの小児投与量は30~50 mg/kg/日・分2〜3、又はベンジルペニシリンベンザチン5万単位/kg/日・分3~4とある44,45。
小児外来抗菌薬治療において服用遵守は重要である。米国では50 mg/kg(最大1 g)の1日1回投与・10日間も推奨される。ニュージーランドでの5~12歳の小児353名を対象にした単施設RCT研究によると、アモキシシリン1日1回がペニシリンV1日2回の治療に対し非劣性であることを示された46。またアモキシシリン1日2回と1日1回投与で比較した非劣性研究でも1日1回の非劣性は証明されている47。アモキシシリン1日1回投与はアドヒアランス面では一見有利であるが、本邦ではアモキシシリン製剤は10%又は20%しか存在しないため、現実的にアモキシシリン1,000 mgを1日1回で投与する場合は、10%製剤10 g(20%製剤なら5 g)となり、大量に服用することになる。よって、実際上困難であるため、本手引きでは、上記の投与方法を推奨する。
④ GAS咽頭炎に対する抗菌薬治療期間
GAS咽頭炎に対するペニシリン系抗菌薬での治療期間は10日間を推奨する。2012年のコクランレビューによると、小児のGAS咽頭炎に対する抗菌薬として、ペニシリン系抗菌薬10日間と、ペニシリン系抗菌薬以外の抗菌薬4〜6日の治療を比較した検討によると、短期治療群で症状消失は有意に早いものの再燃率は高かった。また副作用はペニシリン系抗菌薬群の方が少なく、リウマチ熱・腎炎の合併率は有意差がなかった48。アモキシシリン10日間もしくはセファロスポリン系抗菌薬5日間によるGAS咽頭炎後の除菌率、再発率を比較した後方視的コホート研究によると、除菌率は有意にアモキシシリン治療群で高く(91.7%、セファロスポリン系抗菌薬治療群で82.0%、p=0.01)、再発率に差はなかった49。
⑤ GAS咽頭炎に対する抗菌薬の代替薬
重症ペニシリンアレルギー(アナフィラキシーショック等)がある場合はクリンダマイシンが推奨される43。しかし、わが国ではGASのクリンダマイシン耐性は24%と高く(マクロライド系抗菌薬への耐性率も61%と高い)50、使用する際は感受性検査結果等を参考に注意して使用する。他の代替薬の検討が行われているが、有効性においてペニシリン系抗菌薬を明らかに上回ることはない51。
上記をまとめると、急性咽頭炎に対する抗菌薬治療は以下の通りである。
- GASを除く急性咽頭炎に対しては抗菌薬を投与しない
- GASによる急性咽頭炎と診断した場合、
【第一選択】
アモキシシリン 30〜50 mg/kg/日(最大1,000 mg/日)
分2もしくは分3 10日間経口投与
ベンジルペニシリンベンザチン5万単位/kg/日(最大160万単位/日)
分3もしくは分4 10日間経口投与
【重度のペニシリンアレルギーがある場合】
クリンダマイシン 15 mg/kg/日、
重症感染症には20 mg/kg/日(最大 900 mg/日)分3 10日間経口投与
クラリスロマイシン15 mg/kg/日(最大 400 mg/日)
分2 10日間経口投与
(v) 患者および保護者への説明
【医師から患者への説明例:急性咽頭炎の場合】
急性咽頭炎と診断され、溶連菌検査が陽性になったら、重篤な合併症であるリウマチ熱を予防するため、10日間抗菌薬を医師の指示通り飲みきる必要があります。解熱したからといって自己判断で内服を中止しないでください。
溶連菌による急性咽頭炎では、抗菌薬を開始後24時間経過し、全身の状態がよければ登校・登園できます。
急性咽頭炎の原因が溶連菌ではない、と診断された場合。原因の大半がウイルス性ですので、以下の重症化サインに注意し、解熱鎮痛剤等症状を緩和するお薬を使って、ゆっくり休養することが大切です。通常2、3日から10日間くらいで改善します。
のどを強く痛がる、涎を垂らす等の症状があれば、気道(空気の通り道)が狭くなっている可能性がありますので、緊急受診してください。
<文献検索方法>
小児の急性咽頭炎に関して、日本小児感染症学会(JSPID)、日本感染症学会・日本化学療法学会(JAID/JSC)、米国感染症学会(IDSA)、欧州臨床微生物・感染症学会(ESCMID)等の専門家集団による現在の診療ガイドラインの推奨を踏まえつつ、最新のエビデンスを反映させるためにメタ分析、系統的レビュー、ランダム化比較試験について文献検索を行った。
<MEDLINEでの検索式>
"Pharyngitis"[Mesh] AND ((Clinical Trial[ptyp] OR Comparative Study[ptyp] OR Clinical Study[ptyp] OR Meta-Analysis[ptyp] OR Guideline[ptyp] OR Multicenter Study[ptyp] OR Observational Study[ptyp] OR Practice Guideline[ptyp] OR Randomized Controlled Trial[ptyp] OR systematic[sb]) AND "2018/08/14"[PDat]: "2023/01/31"[PDat] AND (English[lang] OR Japanese[lang]))
結果334件がヒットした。これをCHILDREN(birth-18 years)でフィルターすると132件になった。
(2018年8月14日~2023年1月31日)
<日本語論文(医中誌)での検索方法>
咽頭炎、2007-2018、症例報告除く、会議録除く、メタアナリシス、ランダム化比較試験、準ランダム化比較試験。比較試験、小児
結果38件がヒットした。
(2018年8月14日~2023年1月31日)
(3) クループ症候群
- 主にウイルス感染による喉頭の狭窄に伴う吸気性喘鳴(stridor)、甲高い咳(犬吠様咳嗽)、嗄声等を生じる疾患52。
- 先行する鼻炎、咽頭炎等を伴い、夜間に急に増悪することが多く、数日から1週間程度で自然治癒する52。
- 切迫した気道閉塞をきたす急性喉頭蓋炎、細菌性気管炎、喉頭異物、アレルギー性喉頭浮腫等の除外診断が重要である4。
- 安静時に吸気性喘鳴がある児に対し、アドレナリン吸入、デキサメサゾン投与の適応がある。
【抗菌薬に関する推奨】
- クループ症候群に対しては抗菌薬を投与しないことを推奨する。
(i) クループ症候群とは
急性のウイルス感染症による喉頭の炎症によっておこる疾患で、急性の喉頭狭窄により特徴的な犬吠様咳嗽や吸気性喘鳴等の症状や所見を呈する。
(ii) クループ症候群の疫学
歴史的には、ジフテリア菌がクループ症候群の原因であったが予防接種の普及によってみられなくなった53。現在はその主な原因となる病原体はパラインフルエンザを主体としたウイルスであり、3か月から5歳くらいに多く、ウイルスが流行する秋から冬にかけて多い52,54。SARS-CoV-2(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2)が要因となる場合もある。
※毎年、乳幼児の2〜6%に生じ、うち5%で繰り返し罹患する54。感染経路は、接触および飛沫感染である。なお、重要な鑑別診断である急性喉頭蓋炎は、その主な原因が H. influenzae b型であり、ヒブワクチンの普及で激減した4。
(iii) 診断と鑑別
クループ症候群の診断は症状および身体所見による臨床診断である。先行する鼻汁、咳、発熱等の症状が12〜48時間前にあることが多い54。咳が特徴的で甲高い咳(犬吠様咳嗽:barking cough)を伴う。嗄声も多く、進行すると安静時にも吸気性喘鳴を聴取する4。
重要な鑑別疾患(レッドフラッグ)
急性喉頭蓋炎の他、細菌性気管炎、喉頭異物、アレルギー性喉頭浮腫等切迫する上気道閉塞をきたす疾患の除外が重要である。
閉塞が強いと、多呼吸、起坐呼吸、陥没呼吸、酸素飽和度の低下を伴うことがあり、sniffing positionやtripod position等気道閉塞を回避するための姿勢をとることがある(咽頭炎の項参照)。診察で児を啼泣させたり、舌圧子で喉頭を刺激したりすると、気道の閉塞症状が増悪することがあるため極力避けるようにする。原則、臨床診断であり、頸部正面レントゲン検査でのペンシルサインの確認や側面レントゲン撮影は必須ではないとされている2。
鑑別診断のためには、異物誤飲のエピソードを聴取する。急性喉頭蓋炎の鑑別では、側面レントゲン像が有用なことがあるが、検査より気道確保を優先する52。
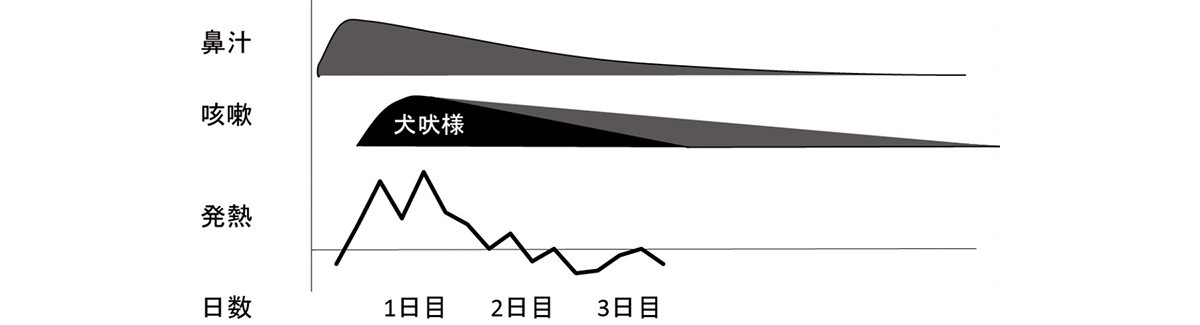
図6. クループ症候群の自然経過
(iv) 治療方法
軽症では治療は必要ない。安静時に吸気性喘鳴が聴取される場合、喉頭の浮腫改善目的でアドレナリン吸入やデキサメタゾン経口投与(0.15~0.6 mg/kg/回)を行う23,55-57。発熱、咽頭痛等に対してアセトアミノフェン等の解熱鎮痛剤を適宜使用する。加湿空気の吸入は効果がない58,59。クループ症候群で気道の閉塞による呼吸不全は稀であるが、切迫する気道閉塞症状がある場合は、気道確保を速やかに行う。
(v) 抗菌薬治療
クループ症候群のほとんどがウイルス性感染症であり、抗菌薬の適用はない23,52,58。一般的には3日以内に自然軽快する。ただし、急性喉頭蓋炎が疑われた時には、入院して静注抗菌薬が必要であり、詳細は成書や学会ガイドラインを参照頂きたい23, 28。
(vi) 患者および保護者への説明
脱水にならないように経口補液を指導し、また、努力呼吸、起坐呼吸等が出現した場合は直ちに医療機関の受診を指示する。
【医師から患者への説明例:クループ症候群の場合】
クループ症候群は、ウイルスによる感染が原因でのどの空気の通り道が狭くなっていることで起こります。原因がウイルスなので抗生物質(抗菌薬)は効果がありません。泣いたり、騒いだりすると悪化することがあるので、できるだけ安静にしましょう。
ほとんどの場合、自然に治りますが、空気の通り道の狭くなる程度が強い場合は、入院が必要になることもあります。クループ症候群は一般的に夜間に悪くなることが多いので、おうちでは本人の様子をよく観察していただき、今よりも呼吸が苦しそうな時はすぐに病院に連れてきてください。
<文献検索方法>
小児のクループに関して、Nelson Textbook of Pediatrics (20th ed)、Feigin and Cherry's Textbook of Pediatric Infectious Diseases (7th ed)、Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases (8th ed)、日本小児感染症学会(JSPID)、日本感染症学会・日本化学療法学会(JAID/JSC)、米国感染症学会(IDSA)、欧州臨床微生物・感染症学会(ESCMID)等の専門家集団による現在の診療ガイドラインの推奨を踏まえつつ、最新のエビデンスを反映させるために文献検索を行った。
<MEDLINEでの検索式>
"Laryngitis"[Mesh] AND ((Clinical Trial[ptyp] OR Comparative Study[ptyp] OR Clinical Study[ptyp] OR Meta-Analysis[ptyp] OR Guideline[ptyp] OR Multicenter Study[ptyp] OR Observational Study[ptyp] OR Practice Guideline[ptyp] OR Randomized Controlled Trial[ptyp] OR Systematic Reviews[sb]) AND "2018/08/20"[PDat]: "2023/01/31"[PDat] AND (English[lang] OR Japanese[lang]))
結果30件がヒットした。これをCHILDREN(birth-18 years)でフィルターすると27件になった。
(2018年8月19日~2023年1月31日)
<日本語論文(医中誌)での検索方法>
クループ、2006-2018、症例報告除く、会議録除く、メタアナリシス、ランダム化比較試験、準ランダム化比較試験。比較試験、小児
結果2件がヒットした。(2018年8月19日~2023年1月31日)
(4) 急性気管支炎
- 急性気管支炎とは咳を主症状とする下気道の炎症で、その多くはウイルス性で自然軽快する
- 診断のための検査は基本的には不要だが、流行状況や所見から臨床的に肺炎や百日咳が疑われる場合は除外診断のための検査を施行する。
【抗菌薬に関する推奨】
- 急性気管支炎に対して抗菌薬を投与しないことを推奨する。
(i) 急性気管支炎とは
急性気管支炎とは咳を主症状とする下気道の炎症であり、発熱や痰の有無は問わない。上気道炎や急性鼻副鼻腔炎との明確な区別は困難なことが多いが、本手引きでは急性気道感染症のうち咳を主症状とするものを急性気管支炎として扱う。なお、小児においては、喘鳴を伴う乳幼児の急性細気管支炎を考慮する必要があり、これについては次項に記載する。
(ii) 急性気管支炎の疫学
原因微生物のほとんどはウイルス性であるとされている60が、他にもマイコプラズマやクラミジア、百日咳菌に注意が必要である。また、乳幼児で3週間以上にわたって咳を呈する場合には、肺炎球菌やH. influenzae等の細菌感染が関与する遷延性細菌性気管支炎という疾患概念が提唱されている44,61,62。その一方で、同様の症状を呈することがある小児の鼻副鼻腔炎との区別は困難なことが多い。
(iii) 診断と鑑別
急性気管支炎の明確な診断基準はなく、急性気道感染症のうち咳嗽を中心とした下気道の症状や聴診上のラ音等の所見があり、呼吸状態や画像所見から肺炎が除外されたものをいうことが多い23。小児呼吸器学会・小児感染症学会における指針では、聴診上、下気道副雑音があるが、胸部X線上明らかな異常陰影を認めない状態と定義されている23。
臨床診断が主なため一般的に急性気管支炎を診断する目的での検査は不要であることから、検査は他の鑑別診断を除外する目的で行われる63。
10日以上咳が遷延する症例については、湿性咳嗽を伴う場合は、鼻副鼻腔炎、遷延性細菌性気管支炎、非定型肺炎が考慮される。稀ではあるが結核にも留意が必要である。その他、気管支喘息、気道異物、胃食道逆流等鑑別は広い。
なお、小児呼吸器感染症診療ガイドライン2022(小児呼吸器感染症診療ガイドライン作成委員会)では1歳未満の小児における咳の鑑別として、特徴的な「吸気性笛声」「発作性の連続性の咳こみ」「咳こみ後の嘔吐」「チアノーゼの有無は問わない無呼吸発作」のうち1つ以上を臨床的百日咳と定義している。1歳以上の小児においては上記の基準に加えて、1週間以上の咳があることが求められる。確定診断には百日咳菌の分離培養あるいは核酸増幅法(PCR法やLAMP法)による検査陽性例、あるいは百日咳菌IgM/IgA抗体およびIgG抗体による血清学的な証明が必要とされている23。
重要な鑑別疾患(レッドフラッグ)
肺炎、膿胸、気道異物が挙げられる。発熱の持続する例、呼吸障害のある症例において、肺炎や膿胸等の除外診断のためにバイタルサインや胸部診察所見に応じて検査が考慮される。気管支喘息等の呼吸器疾患や気道異物等の非感染性疾患についての鑑別も必要である。
(iv) 治療方法
対症療法が中心となる。急性気管支炎に対する気管支拡張薬の有効性の検討をまとめた系統的レビューでは、閉塞性気道疾患のない小児における急性咳嗽に対して気管支拡張薬は無効としている64。
(v) 抗菌薬治療
急性気管支炎に対して抗菌薬は原則として不要である65。近年行われた多施設ランダム化比較試験においても小児の下気道感染症に対する抗菌薬の有効性は認められなかった66。小児の呼吸器疾患を扱った国内外の指針でも、3週間未満の咳を主症状とする急性気管支炎について抗菌薬は不要と定められている19,44,67-70。百日咳が疑われる、もしくは診断した場合はマクロライド系抗菌薬を投与することが推奨されている。一方で、マイコプラズマ、クラミジアが原因微生物と診断された場合はマクロライド系抗菌薬の投与が考慮されるが、気管支炎における有用性は確立していない71。
百日咳を対象として治療する場合には、
| エリスロマイシン | 25〜50 mg/kg/日 分4 14日間経口投与 |
| クラリスロマイシン | 10〜15 mg/kg/日 分2 7日間経口投与 |
| アジスロマイシン | 10 mg/kg/日 分1 5日間経口投与※(添付文書上の適応菌種ではない)72 |
のいずれかの投与を検討する。
また、湿性咳嗽が10日以上続き、軽快が認められず、遷延性細菌性気管支炎や副鼻腔炎が疑われる時は、アモキシシリンの投与を考慮する62,73。
(vi) 患者および保護者への説明
【医師から患者への説明例:急性気管支炎の場合】
急性気管支炎は、ウイルスが原因で、自然に直る病気なので、あまり心配はいりませんが、
1~2週間は咳がつづくことがあります。このままゆっくり良くなっている場合は心配いらないことが多いです。
ほとんどの場合、抗生物質(抗菌薬)は効果がありませんが、時々、百日咳菌や、マイコプラズマといった細菌による感染症であることや、2次的な細菌感染により肺炎になることがあるので、数日経っても良くならない場合、高熱がでる場合や、息苦しさ等がある場合は、再度医療機関を受診してください。
<文献検索方法>
小児の気管支炎に関して、Nelson Textbook of Pediatrics (20th ed)、Feigin and Cherry's Textbook of Pediatric Infectious Diseases (7th ed)、Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases (8th ed)、日本小児感染症学会(JSPID)、日本感染症学会・日本化学療法学会(JAID/JSC)、米国感染症学会(IDSA)、欧州臨床微生物・感染症学会(ESCMID)等の専門家集団による現在の診療ガイドラインの推奨を踏まえつつ、最新のエビデンスを反映させるために文献検索を行った。
<MEDLINEでの検索式>
("bronchitis"[MeSH Terms] OR "bronchitis"[All Fields]) NOT ("bronchiolitis"[MeSH Terms] OR "bronchiolitis"[All Fields]) AND ((Meta-Analysis[ptyp] OR Practice Guideline[ptyp] OR Randomized Controlled Trial[ptyp] OR systematic[sb]) AND ("2018/08/19"[PDAT]: "2023/01/31"[PDAT]) AND (English[lang] OR Japanese[lang]) AND ("infant"[MeSH Terms] OR "child"[MeSH Terms] OR "adolescent"[MeSH Terms]))
結果20件がヒットした。(2018年08月19日~2023年1月31日)
<日本語論文(医中誌)での検索方法>
#1 ((気管支炎/TH or 気管支炎/AL)) and (DT=2019:2023 PT=原著論文,会議録除くRD=メタアナリシス,ランダム化比較試験,準ランダム化比較試験,比較研究,診療ガイドライン (CK=ヒト) AND (CK=新生児,乳児(1~23か月),幼児(2~5),小児(6~12),青年期(13~18)))
#2 (細気管支炎/TH or 細気管支炎/AL)
#1 not #2
上記の結果17件がヒットした。RCTで抗菌薬の必要性を検討した論文はなかった。
(2018年8月20日~2023年1月31日)
(5) 急性細気管支炎
- 急性細気管支炎は、2歳未満の小児において鼻汁、鼻閉等に引き続き、咳、呼気性喘鳴や努力呼吸を呈するウイルス感染症である。
- 診断は臨床診断であり、急性細気管支炎の診断をつける目的での検査は一般的に必要ない。
- 状態を評価するためにバイタルサインや酸素飽和度の測定を行い、呼吸状態を評価する。
また、合併症の有無を見わけることが重要である。
- 呼吸・全身状態に応じた全身管理が重要である。水分バランスに注意し、適宜補液を行う。
上気道の分泌過多がある場合は生理食塩水を用いた鼻腔吸引を行う。- 経過中に病状が進行する可能性や中耳炎や細菌性副鼻腔炎等の合併症をきたす可能性があり、状態の見極めが重要である。
【抗菌薬に関する推奨】
- 急性細気管支炎に対して抗菌薬を投与しないことを推奨する。
(i) 急性細気管支炎とは
乳幼児における急性細気管支炎はウイルスによる下気道感染症で、細気管支上皮の炎症と浮腫や粘液産生による閉塞性病変を特徴とし、呼吸障害をきたす疾患である。一般的に、2歳未満の小児において鼻汁、鼻閉等の上気道炎症状に続いて、下気道感染を伴い咳、呼気性喘鳴や努力呼吸を呈する状態を指す。発熱の有無は問わない。
(ii) 急性細気管支炎の疫学
原因微生物としてRSウイルスが最も重要である。2歳までに9割以上の小児がRSウイルスに感染するとされ、初回感染者の4割は下気道感染症をきたすとされる。その他ヒトメタニューモウイルス、パラインフルエンザ3型、ボカウイルス等もある。
細気管支炎は乳児における入院の原因として最も多く、乳児期早期あるいは基礎疾患のある患者が罹患した場合は呼吸障害をきたすリスクは高い。
(iii) 診断と鑑別
診断は臨床診断であり、血液検査、胸部X線画像、迅速抗原検査は一般的に必要ない70。状態を評価するためにバイタルサインや酸素飽和度の測定を行い、呼吸状態を評価し合併症の有無を見わけることが重要である74。
重要な鑑別疾患(レッドフラッグ)
鑑別診断として肺炎、気管支喘息、気道異物の他に、乳幼児において呼吸障害をきたす多種多様な疾患が該当する。本手引きの対象外の年齢ではあるが、新生児期(生後28日以内)のRSウイルス感染症では、臨床的に上気道炎のみであっても経過中に無呼吸を呈することがあり、入院の上で観察・加療を考慮すべきである。乳幼児では鼻汁、咳を初発症状として、感染後3〜6日頃に喘鳴を特徴とする症状の悪化を認めることが多い。特に乳児期早期、未熟児、先天性心疾患、慢性肺疾患、免疫不全症では呼吸障害が強く入院を要することも少なくないため、多呼吸、努力呼吸、低酸素血症等重症化のサインに注意し必要があれば二次医療機関への紹介を検討する。
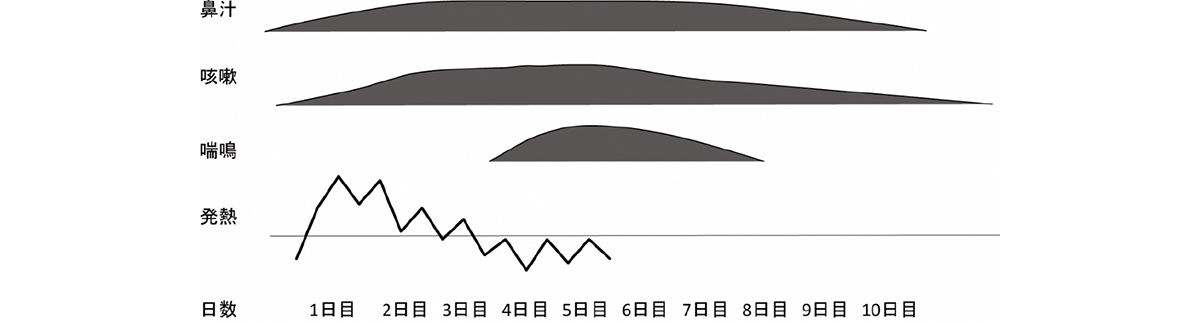
図7. 急性細気管支炎の自然経過
(iv) 治療方法
有効な治療薬はなく、呼吸・全身状態に応じた全身管理が重要である75。脱水に注意し、適宜補液を行うことが重要である。上気道の分泌過多がある場合は鼻腔吸引を行うことも推奨されている76。経過中に病状が進行する可能性や合併症をきたす可能性があり、リスクアセスメントや状態の見極めが重要である。
(v) 抗菌薬治療
急性細気管支炎に対して抗菌薬は不要である。多数の論文に基づいた系統的レビューより抗菌薬の有効性は否定されており77、国内外の診療ガイドラインのコンセンサスでもある44,63,74。
ただし、細菌性肺炎や中耳炎の合併をきたすことがあるので、熱が遷延する場合や、軽快傾向にあった患者が再増悪した場合には注意を要する78。中耳炎の合併率は30〜60%と報告されている79,80。
英国のNational Institute for Health and Care Excellence(NICE)の指針では、鼻腔吸引について、全例での実施は推奨せず、上気道の分泌物過多で呼吸状態が悪いか、経口摂取不良となっている症例に推奨している63。気管支拡張薬やステロイドを用いた薬物療法の有効性、理学療法の有用性についてはいずれも系統的レビュー81-83の結果否定されており、各種ガイドラインでも推奨されていない74。救急外来における吸入アドレナリン療法の検討や高張食塩水の吸入療法84については一部有効性が報告されているが85、十分な監視下で行われるべき治療であり、一般小児科外来では推奨されない。
(vi) 患者および保護者への説明
【医師から患者への説明例:急性気管支炎の場合】
急性細気管支炎はウイルスによる感染症です。細い気管支が狭くなり、咳が出たり、ゼイゼイすることがあります。
急性気管支炎の多くは、自然に治る病気ですが、呼吸が苦しくなることがあり注意が必要です。抗生物質等は効きませんが、熱が続くような場合は、中耳炎や副鼻腔炎を合併することがあります。また脱水にならないように、十分な水分の補給が必要です。呼吸が苦しそうなとき、熱が続くとき、ミルク等水分補給ができないときは受診が必要です。
<文献検索方法>
Bronchiolitisを対象とした国内外のガイドライン(日本小児感染症学会ガイドライン44、英国NICEガイドライン63、米国小児科学会ガイドライン74)や系統的レビュー77が存在し主にこれらを参考とした。過去5年の文献については検討し、外来診療に関わるものを参考とした。
<MEDLINEでの検索式>
"Bronchiolitis"[Mesh] AND ((Meta-Analysis[ptyp] OR Randomized Controlled Trial[ptyp] OR systematic[sb]) AND "2018/08/21"[PDat]: "2023/01/31"[PDat] AND "humans"[MeSH Terms] AND (English[lang] OR Japanese[lang]) AND ("infant"[MeSH Terms] OR "child"[MeSH Terms] OR "adolescent"[MeSH Terms]))
結果93件がヒットした。(2018年8月20日~2023年1月31日)
10. 急性下痢症
- 急性下痢症は、便性と便量の異常のことである。嘔吐腹痛等の腹部症状や発熱を伴うことがある。
- 小児急性下痢症の原因となる微生物は、本邦ではウイルスが大半である
- 小児急性下痢症では、原因診断より重症度の判断が重要である。迅速に緊急度判断を行い、脱水と判断したならば、早期に経口補水療法を開始する。
【抗菌薬に関する推奨】
- 急性下痢症の原因がウイルス性の場合、抗菌薬は不要である。
- 健常者における軽症の細菌性腸炎疑い症例には、抗菌薬を投与しないことを推奨する。
- 生後3か月未満の細菌性腸炎、免疫不全者、重症で敗血症合併が懸念される場合は、抗菌薬投与を検討される。
(1) 急性下痢症とは
急性下痢症は、軟便もしくは水様便といった便性の異常が、24時間以内に3回以上の回数86や、通常の倍以上の回数87、通常の倍以上の量(乳児では10 mL/kg/日以上、乳児以降では200 g/24時間以上)88認められるものと定義される。多くは嘔吐が下痢に先行するが、下痢のみの場合や、特に年少児では嘔吐のみの場合もある。腹痛、発熱の合併を認めることがある。年少児の方が症状の進行は早いが、症状の程度には個人差がある。感染性の要因としてウイルス性と細菌性があるが、日本を始め先進国では、圧倒的にウイルス性が多い。
(2) 急性下痢症の疫学
日本では、冬季に流行し、その大半はノロウイルス等のウイルス感染が原因と推測される89。ノロウイルスは、小児の感染性胃腸炎原因の1位(ないし2位)を占める(12%)90。ワクチンの導入前では、ロタウイルスは先進国、発展途上国関係なく3歳までに90%が罹患する疾患で、ロタウイルスワクチンは先進国では約90%のロタウイルスによる重症下痢症の予防効果がある。日本では、2011年1月よりロタワクチンの任意接種が始まり、2020年より定期接種化された。2013年10月より基幹定点からのロタウイルス胃腸炎の患者届出が始まった。ロタウイルス胃腸炎患者サーベイランスでは、2010/11~2012/13シーズンと比較して、2013/14、2014/15シーズンのロタウイルス胃腸炎患者数は減少傾向と報告されている91。2020年の定期接種化以降は、さらに激減して稀な疾患となった92。
(3) 診断と鑑別
小児の急性下痢症では、原因がウイルス性かどうかを判断することが必要である。嘔吐で始まり、臍周囲の軽度から中等度の腹痛や圧痛がある、血便がなく水様性下痢である、発熱がない(ないし微熱)、激しい腹痛がない、家族・周囲集団に同様の症状がある、といった症状、徴候はウイルス性胃腸炎らしい症候と言える93。一方、発熱、渋り腹や血便の存在は細菌性腸炎を考える。血便の存在は、腸管出血性大腸菌感染症等の細菌性腸炎の他、腸重積、メッケル憩室、上部消化管潰瘍等鑑別疾患が多様である93。特に年少児における血便を呈する疾患の多くは重症で急変の可能性があり、原則的には入院して精査加療が必要になる94。
迅速抗原検査(ロタウイルス、ノロウイルス、腸管アデノウイルス)は、いずれが陽性であっても治療、対処法に違いはなく、小児外来診療において、一般的に検査する意義はない。例外的に入院や集団保育において、感染管理意識させるためや、稀に高熱を呈するロタウイルス、ノロウイルス性胃腸炎もあるために、確実に診断する必要がある場合に適応となる95。
便培養検査を急ぐケースは少なく、検査の適応となるのは、細菌性腸炎が疑われる症例で、激しい腹痛や血便を呈する児、腸管出血性大腸菌感染症から溶血性尿毒症症候群(Hemolytic Uremic Syndrome: HUS)が疑われる児、免疫不全児である。
重要な鑑別疾患(レッドフラッグ)
嘔吐の鑑別として重要な疾患は以下である。
| 所 見 | 疾 患 |
|---|---|
| 急性腹症を示唆する症状・徴候を認める | 腸重積、虫垂炎、精巣捻転、絞扼性イレウス等 |
| 頭蓋内圧上昇症を示唆する症状・徴候を認める | 髄膜炎、頭蓋内出血 |
| その他 | 敗血症(トキシックショック症候群含む)、 糖尿病性ケトアシドーシス、尿路感染症 |
これらはすべて時間単位で悪化する疾患であるため、早急に高次医療機関への転送を検討する。
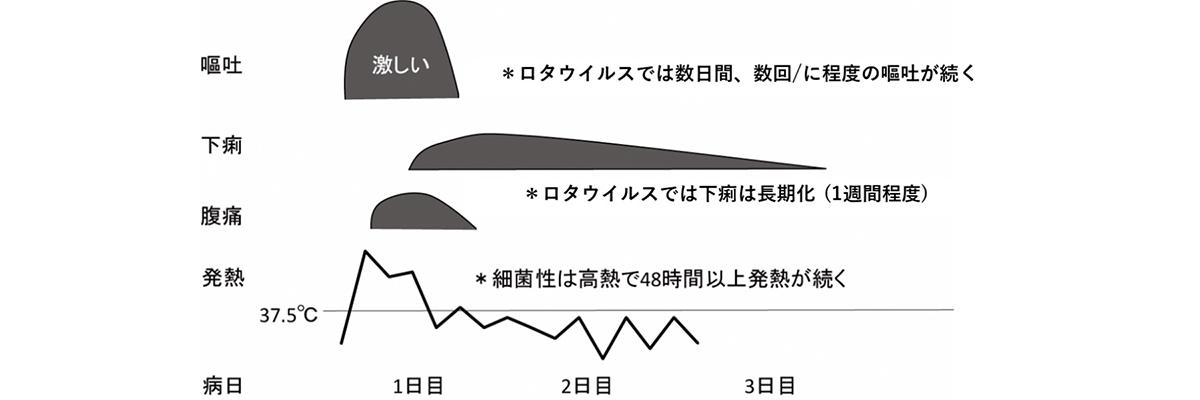
図8. 急性ウイルス性下痢症の自然経過
(4) 治療方法
急性下痢症への治療は、1) 脱水への対応、すなわち経口補水療法(Oral Rehydration Therapy: ORT)や経静脈的輸液が重要であり、2) プロバイオティクスについて検討し、3)抗菌薬を安易に使用しないことが求められる93,94。
(i) 脱水への対応
急性下痢症と判断した場合、まず重症度の判断が重要であり、重症度に最も影響するのが、脱水の有無である。
小児は、体重あたりの水分必要量が多いことと、水分や食事の摂取が自立していないため、その供給を他者(特に保護者)に依存していることから、脱水へのケアが重要であり93,95、速やかに評価し対応する必要がある。
輸液療法を要することが多い体重の5%以上の脱水(体重減少)、またそれ以上の重症脱水を見逃さないことが重要である96。①毛細血管再充満時間(Capillary Refill Time: CRT 指の爪床を5秒間圧迫した後に圧迫を解除。圧迫解除後、爪床の色が元の色に戻るまでの時間)が2秒以上、②粘膜の乾燥、③流涙なし、④全身状態の変化の4項目のうち2項目陽性であれば、5%以上の脱水を示唆するとされている(LR+6.1;95%信頼区間 3.8-9.7)96。
経静脈的輸液が必要になる危険性が高い者は、生後6か月以下、低出生体重児、慢性疾患、生後3か月未満の発熱(38℃以上)、生後3か月~3歳で高熱(39℃以上)、血便、持続する嘔吐、尿量の減少、眼窩の陥凹、そして意識レベルの低下である93。
経口補水液(oral rehydration solution: ORS)は、急性下痢症に対する世界標準治療である95。その有効性だけではなく、血管確保が不要で児への負担も少ないという利点も大きい95。脱水のない状況における脱水予防と、軽度から中等症の脱水に対する治療として推奨されている95。
具体的には、できるだけ早期に(脱水症状出現から3〜4時間以内)、少量(ティースプーン1杯程度)から徐々に増量しつつ、脱水量と同量(軽症から中等症脱水ならば50〜100 mL/kg)を3〜4時間で補正することが重要である。
(ii) プロバイオティクス
英国診療ガイドライン94、欧州小児栄養消化器肝臓学会の2014年ガイドライン95では、急性下痢症に対して小児では下痢の期間と頻度を減らすとして使用推奨がなされた。一方その後、複数の検討では有用性が示されなかったことを受けて、欧州小児栄養消化器肝臓学会は2020年には推奨レベルを下げている。しかし、使用する製剤の国家間での相違もあり、直ちに使用を否定するほどの強いエビデンスがあるわけではない。以上より、本手引きでは現時点でのエビデンスに基づき、一律使用に関する推奨はしないこととする96-100。
(5) 抗菌薬治療
ウイルス性腸炎と診断した場合、抗菌薬は無効であるばかりか、腸内細菌叢を乱し、菌交代現象を引き起こすためとされ、有害であるため使用しない86。
細菌性腸炎と判断した場合は、時宜を得た適正な抗菌薬療法は下痢の重症度を改善し罹病期間を短縮することができる。一方で抗菌薬は保菌状態を長引かせ、また下痢症に対して広範に抗菌薬を使用すると薬剤耐性を引き起こす。
細菌性腸炎による下痢症であっても、多くは自然軽快する。よって、健常児で軽症の場合は、便培養を採取の上、まずは対症療法を行い、経過と便培養結果で抗菌薬治療を考慮する。細菌性腸炎による症状(強い腹痛、しぶり腹、血便、高熱)がある場合は、便培養を採取の上、抗菌薬療法を考慮する。一方、全身状態が不良な症例、生後3か月未満、免疫不全者等のハイリスク症例は原則入院で全身管理と抗菌薬治療を行うことが実際的である。
(i) 初期治療
- 細菌性腸炎による強い症状があり抗菌薬治療を考慮する場合
- 病歴、便のグラム染色よりカンピロバクター腸炎を疑う場合
クラリスロマイシン 15 mg/kg/日 分2 3~5日間経口投与
アジスロマイシン 10 mg/kg/日 分1 3日間経口投与 - カンピロバクター以外の細菌による感染性腸炎が強く示唆され、菌血症等重症化のリスクの高い場合は、国内で保険適用のある薬剤で、有効性に関する明確なエビデンスのあるものはなく、日本感染症学会・日本化学療法学会のガイドライン(JAID/JSC感染症治療ガイドライン2019‐腸管感染症‐)等を参照。
(ii) 確定治療
- カンピロバクター腸炎
自然治癒が望めるため抗菌薬は必須ではない。
高熱、強い腹痛、血便等重症例に抗菌薬投与を考慮する。
クラリスロマイシン 15 mg/kg/日 分2 3~5日間経口投与
アジスロマイシン 10 mg/kg/日 分1 3日間経口投与 - 非チフス性サルモネラ腸炎
抗菌薬により排菌期間が長くなるため、無症状キャリア、軽症患者には投与しない。ハイリスク症例(年少児;特に生後3か月以下、免疫抑制状態、炎症性腸疾患)は治療対象になる。重症であるもの、合併症が出現しているものは入院加療が必要である。この際菌血症を合併することが多いので、血液培養を採取する。
非チフス性サルモネラ腸炎による感染性腸炎が強く示唆され、菌血症等重症化のリスクの高い場合は、国内で保険適用のある薬剤で、有効性に関する明確なエビデンスのあるものはなく、学会のガイドライン(JAID/JSCガイドライン2019‐腸管感染症‐)等を参照する。 - 下痢原性大腸菌感染症
腸管出血性大腸菌(EHEC)を除いたその他の下痢原性大腸菌による腸炎は自然治癒する傾向がある。EHECの関与が疑われる腸炎では、本邦においては未だ抗菌薬投与に関する統一した見解は出ていない。欧米のガイドラインでは抗菌薬(多くはST合剤、β-ラクタム系抗菌薬)は溶血性尿毒症症候群(Hemolytic Uremic Syndrome: HUS)発症のリスクが増すことから、否定的な見解が多い。一方、抗菌薬の投与が HUSのリスクには影響を与えないというメタ解析もある101。さらに国内の限られた症例数ではあるが、ホスホマイシンを中心として抗菌薬を使用し有効であったとの報告もある102-104。
日本感染症学会・日本化学療法学会の指針では、「現時点で抗菌薬治療に対しての推奨は統一されていない」とされている。よって本手引きにおいても上記指針を踏襲し、抗菌薬投与は推奨せず、支持療法を推奨し、EHEC感染者の3~10%にHUSが発症することを十分説明し、頻回に経過フォローを行い、早期発見に最大限努めることを推奨する。
(6) その他の薬物療法に関する考え方
嘔吐に対する制吐剤、下痢に対する止痢剤はエビデンスに乏しく推奨されていない94。ロペラミドは乳児でイレウスの発症が報告され、6か月未満は禁忌、6か月以上2歳未満の乳幼児は治療上やむを得ないと判断される場合を除き投与しない94。
(7) 患者および保護者への説明
【医師から患者への説明例:急性胃腸炎の場合】
「お腹の風邪」と表現されるものです。多くはウイルスが原因で、特別な治療薬(=特効薬)はありません。自分の免疫の力で自然と治癒します。
年少児で発熱を伴う場合や、重症例、免疫不全を除き、細菌検査やウイルス検査する意義はありません。
治療の基本は、脱水の予防です。体液に近い成分の水分を口からこまめにとることが重要です。最初は少量を(最初はティースプーン一杯程度)10~15分毎に与えてください。急にたくさん与えてしまうと嘔吐を誘発することになり、さらに脱水が悪化しますので、根気よく、少量ずつ与えてください。1時間くらい続けて、症状の悪化がないことが確認できたら、少しずつ
1回量を増やしましょう。どれくらいの量をあたえるべきかに関しては、かかりつけの医師に相談してください。
このような水分摂取をしても水分がとれない、それ以上に吐く・下痢をするということがありましたら、さらに脱水が進む可能性があり、点滴(輸液療法)が必要となることもあります。また尿が出ない、不機嫌、意識状態の悪化(ぐったり感が強い、ウトウトして眠りがち)、激しい腹痛や、保護者の方がみて「いつもと違う」と感じられたら、再度、医療機関を受診してください。
<文献検索方法>
小児の急性下痢症に関して、日本小児救急医学会(JSEP)、日本感染症学会・日本化学療法学会(JAID/JSC)、世界保健機関(WHO)、英国の診療ガイドライン(NICE)、欧州小児栄養消化器肝臓学会(ESPGHAN)等の専門家集団による現在の診療ガイドラインの推奨を踏まえつつ、最新のエビデンスを反映させるためにメタ分析、系統的レビュー、ランダム化比較試験について文献検索を行った。
<MEDLINEでの検索式>
((("Diarrhea"[Mesh] AND "Acute Disease"[Mesh]) OR "infectious diarrhea"[All Fields]) OR ("dysentery"[MeSH Terms] OR "dysentery"[All Fields])) OR "acute gastroenteritis"[All Fields] AND ((Clinical Study[ptyp] OR Clinical Trial[ptyp] OR Comparative Study[ptyp] OR Guideline[ptyp] OR Meta-Analysis[ptyp] OR Multicenter Study[ptyp] OR Observational Study[ptyp] OR Practice Guideline[ptyp] OR Randomized Controlled Trial[ptyp] OR systematic[sb]) AND "2018/8/14"[PDat] : "2023/1/31"[PDat] AND (English[lang] OR Japanese[lang]))
結果261件がヒットした。これをCHILDREN(birth-18 years)でフィルターすると179件になった。
(2018年8月14日~2023年1月31日)
<日本語論文(医中誌)での検索方法>
急性下痢症、2019-2023、症例報告除く、会議録除く、と結果7件がヒットした。
(2018年8月14日)
上記文献のうち内容吟味し、薬剤耐性(AMR)対策アクションプランにふさわしい内容と考えられたもの(参考文献)7件
上記に加えて、本邦の小児急性胃腸炎診療ガイドライン2017年度版(日本小児救急医学会診療ガイドライン作成委員会編)を参照した。
11. 急性中耳炎
- 小児の急性中耳炎を診断するためには、耳痛や耳漏の訴えだけに頼らず、発熱、不機嫌、風邪症状等を訴える患者の鼓膜所見をとることが重要である。
- 鼓膜発赤のみで膨隆がない場合は、原則として急性中耳炎と診断しない。
- 中耳由来の耳漏を認める急性中耳炎には、抗菌薬の投与が推奨される。
- 発熱、不機嫌、耳痛等があり、発赤と膨隆を伴う鼓膜所見がある場合は、抗菌薬投与を考慮する。
- 鼓膜所見を認める場合でも、急性中耳炎は自然軽快する可能性が有り、年齢、基礎疾患等の患者リスク、中耳の局所炎症所見、全身状態等の程度を考慮し、軽症で重症化のリスクが低いものは抗菌薬を投与せず2-3日の経過観察を検討する。
【抗菌薬に関する推奨】
- 急性中耳炎の第一選択薬はアモキシシリンである。
- 耳鼻咽喉科医との連携が重要な疾患である。
※ 本稿は中耳炎の疑われる小児に対して、一般診療医が抗菌薬投与の必要性を判断するための基準と初期選択薬を記した。難治例や耐性菌による感染症等複雑な症例については学会のガイドライン等を参照されたい。
(1) 急性中耳炎とは
耳痛、発熱、耳漏を伴うことがある急性に発症した中耳の感染症と定義される105。急性中耳炎は、耳管経由で中耳腔にまで炎症,感染が波及して生じる。主たる原因菌は、肺炎球菌とHaemophilus influenzaeであり、次いでMoraxella catarrhalisが原因となる。
なお、滲出性中耳炎とは、急性炎症症状(耳痛や発熱)を伴わず、鼓膜穿孔もなく、中耳腔に液体貯留液を認める難聴の原因になるものと定義106され、急性中耳炎とは異なる。また、滲出性中耳炎自体に対する抗菌薬投与の適応はない。
(2) 急性中耳炎の疫学
急性中耳炎は1歳までに75%が罹患、7歳までに40%が4回以上罹患する頻度の高い感染症である107,108。
乳幼児に多い理由として、解剖学的要因と免疫学的要因が挙げられる。解剖学的要因として、成人の耳管は約45度と傾斜が高く細長いのに対し、小児の耳管は約10度と傾斜が低く,太く短いため,上咽頭(鼻腔)から炎症が波及しやすく,急性中耳炎を発症しやすいことが挙げられる。免疫学的要因としては、特に生後6か月から2歳までは肺炎球菌やH. influenzae に対する特異的抗体が低いため,易感染性となることが報告されている108-111。また、乳幼児は自分で鼻をかむことができず,ドレナージ不良が起きやすいことも一因とされる。その他に周囲の喫煙や非母乳栄養等が発症のリスクを上げるとされる。
(3) 診断
急性中耳炎の診断は、耳鏡を用いた鼓膜診察で局所所見を正確に取ることによる。国内の中耳炎ガイドラインは局所所見を重要視し、詳細な所見に基づく診断を推奨している105。米国小児科学会ガイドライン112でも、急性中耳炎の診断は鼓膜所見に基づいた以下3点の基準が掲げられている。①中等度~高度の鼓膜膨隆,あるいは急性外耳道炎によらない耳漏が認められる場合は急性中耳炎と診断する。②鼓膜の軽度膨隆と強い鼓膜発赤とともに急性(48時間以内)に発症した耳痛(耳を触る,引っ張る,擦る)がある場合は急性中耳炎と診断する。③中耳腔液体貯留がない鼓膜発赤は急性中耳炎と診断すべきでない。総合すると、中耳炎の最も重要な所見は、鼓膜の膨隆である。鼓膜発赤は、発熱や啼泣のみでも認めることがある。
乳幼児は耳痛を正確に表現できないため,発熱と不機嫌だけが訴えとなる可能性や、発熱のない中耳炎が40%あることが挙げられ113-116、鼓膜所見が重要視される。一方で、耳痛や発熱不機嫌の鑑別として、他の局所感染や全身性の重症細菌感染症を見極める必要性がある。口腔内病変等でも耳痛の原因となることがある。耳垢があり除去できず鼓膜の評価が困難な場合は、耳鼻咽喉科医への紹介等を検討する。
表5. 耳痛の鑑別
| 耳痛で鑑別すべき疾患 | |
|---|---|
| 1) 中耳炎 2) 鼓膜炎 3) 外耳道炎 4) 外耳道異物 5) 流行性耳下腺炎(ムンプス) 6) 耳介前、耳介後部リンパ節炎 7) う歯,歯肉炎 |
8) 髄膜炎 9) 化膿性唾液腺炎 10) 帯状疱疹 11) 乳様突起炎 12) 外傷 13) 蜂窩織炎 |
表6. 耳痛・中耳炎の診療中に注意すべき所見(レッドフラッグ)と検討すべき事項
| 所 見 | 検討事項および鑑別すべき疾患 |
|---|---|
| 抗菌薬を投与せず経過観察して2-3日で局所・全身所見ともに改善しない | 中耳炎として抗菌薬の投与を検討する 他の感染巣の有無を見極め、診断を再検討する |
| 抗菌薬治療を開始して2-3日で局所・全身所見ともに改善しない | 他の感染巣の有無を見極め、診断を再検討する 外科的ドレナージ(鼓膜切開)の適応を見極める 耐性菌を意識した抗菌薬の変更を検討する |
| 耳介後部の発赤・腫脹と圧痛、耳介聳立 | 乳様突起炎 |
| 項部硬直、意識障害、けいれん、‟not doing well” | 髄膜炎 |
| 下顎角周囲の腫脹、疼痛、唾液腺開口部の発赤 | 化膿性唾液腺炎、流行性耳下腺炎 |
(4) 抗菌薬治療
(i) 抗菌薬による中耳炎の治療目的と治療適応の考え方
抗菌薬治療の目的は急性中耳炎に伴う症状(発熱、耳痛等)の早期改善と急性中耳炎に続発する合併症を減らすことである。2015年に発表されたコクランレビューでは、抗菌薬治療は、ティンパノメトリーの異常(鼓膜の可動不良)、鼓膜穿孔、反対側の急性中耳炎の発症を防ぐことに対して、一定の効果があるとされる117。一方で急性中耳炎は、抗菌薬処方がなくても、4分の3以上が1週間で自然治癒し、2歳以上は3日で70%改善し、2歳未満の場合は10日で約半数が治癒することも知られ、全例に抗菌薬が必要な疾患ではない118-122。また抗菌薬治療は、下痢等の副作用や細菌の薬剤耐性化の原因となりうるため、必要の可否と必要な場合の適切な抗菌薬選択が重要である。
米国小児科学会ガイドラインでは、抗菌薬投与を①耳漏がある場合,②重症(toxic、48時間以上持続する耳痛,39℃以上の発熱)の場合,③ 6か月~2歳で両側の場合に抗菌薬投与を行うと推奨している112。本邦のガイドラインでも、年齢とリスク因子を考慮し、臨床症状と鼓膜所見の評価の上で、自然寛解を期待して2~3日間の抗菌薬を投与しない期間を設けることが妥当とされている105。
(ii) 抗菌薬投与基準
上記を踏まえて中耳炎に対する抗菌薬投与基準を以下のように定める。
- 中耳由来の耳漏がある場合には抗菌薬投与を考慮する。吸引等で鼓膜を可視化し穿孔部位から拍動性の耳漏が確認できれば最も診断精度が高い。
- 発熱、不機嫌、耳痛等があり、発赤と膨隆を伴う鼓膜所見がある場合は、抗菌薬投与を考慮する。
- 全身状態が良く、中耳由来の耳漏がない場合は、自然に改善することが多いこと、抗菌薬の使用は副作用や耐性菌を作るデメリットがあること、フォローで改善しない場合には抗菌薬治療を考慮することの説明を行い、同意を得た上で(下記説明文参照)、2-3日間の抗菌薬を投与せずに、解熱鎮痛剤等を中心とした対症療法を行う。
- 抗菌薬投与の適応は、中耳炎が重症化する以下のリスクファクターを考慮する。(2歳未満の低年齢、免疫不全等の基礎疾患の存在、肺炎球菌ワクチン未接種、中耳炎の既往歴、医療アクセス不良。)
(iii) 第一選択薬
アモキシシリンを第一選択薬として推奨する。治療ターゲットとする細菌は肺炎球菌とNon-typable H. influenzae(NTHi)である。肺炎球菌ワクチン(PCV)導入後はワクチンに含有される13価以外の血清型による感染症の増加もあり、現在肺炎球菌とNTHiは同じくらいの頻度かH. influenzaeが多くなってきている96。本邦では、肺炎球菌はPRSP(Penicillin-resistant S. pneumoniae)、NTHiはBLNAR(β-lactamase-negative ampicillin-resistant)が問題となる。肺炎球菌の場合は非侵襲性感染症であれば、多くの場合は高用量のアモキシシリンで対応できるため、アモキシシリンを第一選択とすることが可能である122。
一方でBLNARによる中耳炎の場合は、耐性度が高い株が少なくなく、治療に難渋する場合はこれを考慮し、ガイドライン等を参考に治療選択を行う105。β-ラクタマーゼを産生するM. catarrhalisやBLPAR(β-lactamase-positive ampicillin-resistant)H. influenzaeでは、アモキシシリンは選択しにくく、β-ラクタマーゼ阻害剤との合剤であるクラブラン酸/アモキシシリンが選択される。しかし、M. catarrhalis単独での病原性はほぼなく、BLPAR H. influenzaeも本邦では出現頻度は低い123。よって、アモキシシリンによる十分量治療に反応が悪いケースにのみ、クラブラン酸/アモキシシリンや他剤の使用が考慮される。なお、国内の小児を対象としたランダム化比較試験では、中耳炎に対してアモキシシリン単独よりクラリスロマイシン併用の方が治療失敗は少なかったと報告している124。
(iv) 投与量と投与間隔
アモキシシリン:60~90 mg/kg/日 分3 経口投与 (90 mg[力価]/kg/日を越えない)
(v) 治療期間
米国小児科学会ガイドラインでは、年齢別に2歳未満では10日間、2-5歳は7-10日間、6歳以上は5-7日間とされている112。本邦ガイドラインでは5日間で治療開始後、3、4日目に病態の推移を観察することが推奨されている123。2歳未満に限定した非劣性RCTでは、5日間投与は10日間投与に比べて失敗率が高いと報告されている125。
本手引きでは、2歳未満は10日間を推奨し、それ以降の年齢では、5日間を基本的な推奨とする。一方、全身状態が不変、悪化傾向の場合には2-3日間で、再評価し、推奨の治療期間前に治癒した場合、個々の症例に合わせて治療期間の短縮や延長を決定することを推奨する。
(vi) 代替薬
β-ラクタム系抗菌薬にアレルギーがある場合等でペニシリン系抗菌薬が使用できない場合は学会のガイドラインを参考に選択薬を考慮する105。国内の原因菌感受性結果からはマクロライド系抗菌薬は推奨されない。
(vii) 治療後の経過
治療開始24時間以内は所見が悪化する可能性があるが,多くは24時間以内に改善し始め、72時間以内には改善する121。
(viii) 点耳薬(抗菌薬)
点耳薬(抗菌薬)が中耳腔内に入れば、理論的には高濃度の抗菌薬が中耳に届くことが期待される。鼓膜穿孔がない場合は無効であり、推奨されない。また鼓膜切開後の点耳薬は十分に検討された報告はない。鼓膜換気チューブ留置患者においては、いくつかのRCTにて治癒までの期間が短縮される等の有効性が証明されており、症例を選択して投与することが検討される105。
(ix) 鼓膜切開の適応
鼓膜切開が急性中耳炎の治癒を促進させるか否かは十分に証明されていないが、激しい耳痛、発熱、難聴の早期改善効果が認められる。激しい耳痛、発熱、不機嫌等の強い全身症状があり、かつ、鼓膜の局所所見、全体的な膨隆がある場合には、適応を考慮する。
(x) 鎮痛薬
アセトアミノフェン 頓用 10~15 mg/kg/回 経口投与(4~6時間以上の間隔を開けて使用)
(5) 患者および保護者への説明
【医師から患者への説明例:急性中耳炎の場合】
中耳は耳管という管で鼻の一番奥とつながっています。子どもの耳管は大人に比べて、太くて短く、角度も水平に近いため、感冒等のウイルス感染症、アレルギー等が原因で、耳管を経由して炎症が中耳に広がりやすくなっています。中耳の炎症の結果、耳を痛がって機嫌が悪くなったり、熱が出たり、鼓膜が腫れたり、赤くなったりします。この時期には、抗菌薬は特に必要なく、熱や痛みに対して解熱鎮痛剤で治療するだけで治ることが多いです。抗菌薬は良い薬ですが、必要のないときに使用すると悪いことがあり、下痢等の副作用、耐性菌を作ってしまい将来、非常に治療が難しくなることがあります。
小さいお子さんは風邪を引きやすく、鼻を自分でかんだりもできないうえ、中耳炎の原因になる細菌に対して抵抗力が弱いので、中耳(鼓膜の奥)の中での細菌の量が増えすぎてしまうことがあります。機嫌が悪く、鼓膜がひどく腫れている状態が続いたりするようになると、抗菌薬の助けが必要となります。稀に鼓膜切開をして膿を出すこともあります。待つ時期と抗菌薬が必要な時期を見極めるためにも、外来で経過をみる必要があります。<科学的根拠の採用方針(検索式等)>
小児の急性中耳炎に関して、日本小児感染症学会(JSPID)、日本感染症学会・日本化学療法学会(JAID/JSC),米国感染症学会(IDSA),欧州臨床微生物・感染症学会(ESCMID)等の専門家集団による現在の診療ガイドラインの推奨を踏まえつつ,最新のエビデンスを反映させるためにメタ分析,系統的レビュー,ランダム化比較試験について文献検索を行った。
<MEDLINEでの検索式>
"otitis media"[Mesh] AND ((Clinical Trial[ptyp] OR Comparative Study[ptyp] OR Clinical Study[ptyp] OR Meta-Analysis[ptyp] OR Guideline[ptyp] OR Multicenter Study[ptyp] OR Observational Study[ptyp] OR Practice Guideline[ptyp] OR Randomized Controlled Trial[ptyp] OR systematic[sb]) AND "2019/5/17"[PDat]: "2023/1/31"[PDat] AND (English[lang] OR Japanese[lang]))
結果220件がヒットした。
これをCHILD(birth-18 years)でフィルターすると154件になった。
(2019年5月16日)
<日本語論文(医中誌)での検索方法>
急性中耳炎、2019-20123、症例報告除く、会議録除く、メタアナリシス、ランダム化比較試験、準ランダム化比較試験、比較試験
結果2件がヒットした。
(2019年5月17日)
12. 引用文献
- Heikkinen T, Järvinen A. The common cold. Lancet. 2003;361(9351):51-59.
- National Institute for Health and Care Excellence(NICE). Fever in under 5s: assessment and Initial management.
- Farley R, Spurling GKP, Eriksson L, Del Mar CB. Antibiotics for bronchiolitis in children under two years of age. Cochrane Database Syst Rev. 2014:Cd005189.
- Cherry JD. Croup (Laryngitis, Laryngotracheitis, Spasmodic Croup, Laryngotracheobronchitis, Bacterial Tracheitis, and Laryngotracheobronchopneumonitis) and Epiglottitis (Supraglottitis). In: Cherry J, ed. Feigin and Cherry's Textbook of Pediatric Infectious Diseases. 7th ed. Philadelphia: Saunders; 2014:241-260.
- Dieckmann RA, Brownstein D, Gausche-Hill M. The pediatric assessment triangle: a novel approach for the rapid evaluation of children. Pediatric emergency care 2010;26:312-5.
- McGowan JE, Jr., Bratton L, Klein JO, Finland M. Bacteremia in febrile children seen in a "walk-in" pediatric clinic. The New England journal of medicine. Jun 21 1973;288(25):1309-1312.
- Andersen DH, Blanc WA, Crozier DN, Silverman WA. A difference in mortality rate and incidence of kernicterus among premature infants allotted to two prophylactic antibacterial regimens. Pediatrics. Oct 1956;18(4):614-625.
- Bradley JS, Wassel RT, Lee L, Nambiar S. Intravenous ceftriaxone and calcium in the neonate: assessing the risk for cardiopulmonary adverse events. Pediatrics. Apr 2009;123(4):e609-613.
- Honein MA, Paulozzi LJ, Himelright IM, et al. Infantile hypertrophic pyloric stenosis after pertussis prophylaxis with erythromcyin: a case review and cohort study. Lancet. Dec 18-25 1999;354(9196):2101-2105.
- Forti G, Benincori C. Doxycycline and the teeth. Lancet. Apr 12 1969;1(7598):782.
- Miller EK, Williams JV. The Common Cold. In: Kliegman RM, Stanton BMD, Geme JS, Schor NF, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 20th ed. Amsterdam: Elsevier; 2015:2011-2014.
- Cherry JD. The Common Cold. In: Cherry J, ed. Feigin and Cherry's Textbook of Pediatric Infectious Diseases. 7th ed. Philadelphia: Saunders; 2014:132-139.
- Turner RB. The Common Cold. In: Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ, eds. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. 8th ed. Philadelphia: Saunders; 2015:748-752.
- Chow AW, Benninger MS, Brook I, et al. IDSA clinical practice guideline for acute bacterial rhinosinusitis in children and adults. Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America. Apr 2012;54(8):e72-e112.
- Steiner MJ, DeWalt DA, Byerley JS. Is this child dehydrated? JAMA : the journal of the American Medical Association 2004;291:2746-54.
- Kim SY, Chang YJ, Cho HM, Hwang YW, Moon YS. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for the common cold. Cochrane Database Syst Rev. Sep 21 2015(9):CD006362.
- Kenealy T, Arroll B. Antibiotics for the common cold and acute purulent rhinitis. The Cochrane Database Syst Rev. Jun 04 2013(6):CD000247.
- Arroll B. Common cold. BMJ Clin Evid. Mar 16 2011;2011.
- Shields MD, Bush A, Everard ML, McKenzie S, Primhak R. BTS guidelines: Recommendations for the assessment and management of cough in children. Thorax. Apr 2008;63 Suppl 3:iii1-iii15.
- National Institute for Health and Care Excellence(NICE). Respiratory Tract Infections - Antibiotic Prescribing: Prescribing of Antibiotics for Self-Limiting Respiratory Tract Infections in Adults and Children in Primary Care. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK53632/. 最終閲覧日2023年3月24日.
- Cronin MJ, Khan S, Saeed S. The role of antibiotics in the treatment of acute rhinosinusitis in children: a systematic review. Archives of disease in childhood. Apr 2013;98(4):299-303.
- Orlandi RR, Kingdom TT, Hwang PH, et al. International Consensus Statement on Allergy and Rhinology: Rhinosinusitis. Int Forum Allergy Rhinol. Feb 2016;6 Suppl 1:S22-209.
- 小児呼吸器感染症診療ガイドライン作成委員会. 上気道炎. In: 石和田稔彦/新庄正宜, eds. 小児呼吸器感染症診療ガイドライン2022. 東京: 協和企画; 2022.
- Fahey T, Stocks N, Thomas T. Systematic review of the treatment of upper respiratory tract infection. Archives of disease in childhood. Sep 1998;79(3):225-230.
- Keith T, Saxena S, Murray J, Sharland M. Risk-benefit analysis of restricting antimicrobial prescribing in children: what do we really know? Current opinion in infectious diseases. Jun 2010;23(3):242-248.
- Shaikh N, Hoberman A, Shope TR, Jeong JH, Kurs-Lasky M, Martin JM, Bhatnagar S, Muniz GB, Block SL, Andrasko M, Lee MC, Rajakumar K, Wald ER. Identifying Children Likely to Benefit From Antibiotics for Acute Sinusitis: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2023 Jul 25;330(4):349-358.
- Caballero TM, Altillo BSA, Milstone AM. Acute Bacterial Sinusitis: Limitations of Test-Based Treatment. JAMA. 2023 Jul 25;330(4):326-327.
- Cherry JD, Rhinosinusitis, Feigin and Cherry's Textbook of Pediatric Infectious Diseases, 2014. Saunders: Philadelphia. p193-202.
- Marchant JM, Morris P, Gaffney JT, Chang AB. Antibiotics for prolonged moist cough in children. Cochrane Database Syst Rev. Oct 19 2005(4):Cd004822.
- Welschen I, Kuyvenhoven M, Hoes A, Verheij T. Antibiotics for acute respiratory tract symptoms: patients' expectations, GPs' management and patient satisfaction. Fam Pract. Jun 2004;21(3):234-237.
- Bisno AL. Acute pharyngitis. The New England journal of medicine. Jan 18 2001;344(3):205-211.
- 武内一, 深澤満, 吉田均, 西村龍夫, 草刈章, 岡崎実. 扁桃咽頭炎における検出ウイルスと細菌の原因病原体としての意義. 日本小児科学会雑誌. 2009;113(4):694-700.
- Tanz RR, Shulman ST. Chronic pharyngeal carriage of group A streptococci. The Pediatric infectious disease journal. Feb 2007;26(2):175-176.
- Shaikh N, Swaminathan N, Hooper EG. Accuracy and precision of the signs and symptoms of streptococcal pharyngitis in children: a systematic review. The Journal of pediatrics 2012;160:487-93.e3.
- Centor RM, Witherspoon JM, Dalton HP, Brody CE, Link K. The diagnosis of strep throat in adults in the emergency room. Medical decision making : an international journal of the Society for Medical Decision Making. 1981;1(3):239-246.
- Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the Infectious Diseases Society of America. Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America. Nov 15 2012;55(10):1279-1282.
- Gerber MA, Shulman ST. Rapid diagnosis of pharyngitis caused by group A streptococci. Clinical microbiology reviews. 2004;17:571-80.
- Ezike EN, Rongkavilit C, Fairfax MR, Thomas RL, Asmar BI. Effect of using 2 throat swabs vs 1 throat swab on detection of group A streptococcus by a rapid antigen detection test. Archives of pediatrics & adolescent medicine. May 2005;159(5):486-490.
- McIsaac WJ, Kellner JD, Aufricht P, Vanjaka A, Low DE. Empirical validation of guidelines for the management of pharyngitis in children and adults. JAMA. Apr 07 2004;291(13):1587-1595.
- Catanzaro FJ, Stetson CA, Morris AJ, et al. The role of the streptococcus in the pathogenesis of rheumatic fever. The American journal of medicine. Dec 1954;17(6):749-756.
- Brink WR, Rammelkamp CH, Jr., Denny FW, Wannamaker LW. Effect in penicillin and aureomycin on the natural course of streptococcal tonsillitis and pharyngitis. The American journal of medicine. Mar 1951;10(3):300-308.
- Gerber MA. Comparison of throat cultures and rapid strep tests for diagnosis of streptococcal pharyngitis. The Pediatric infectious disease journal. Nov 1989;8(11):820-824.
- Bisno AL, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis. Infectious Diseases Society of America. Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America. Jul 15 2002;35(2):113-125.
- 小児呼吸器感染症診療ガイドライン作成委員会. 小児呼吸器感染症診療ガイドライン2017. 協和企画; 2016.
- Iijima H, Kubota M, Ogimi C. Clinical characteristics of pediatric patients with COVID-19 between Omicron era vs. pre-Omicron era. J Infect Chemother. 2022 Nov;28(11):1501-1505.
- Lennon DR, Farrell E, Martin DR, Stewart JM. Once-daily amoxicillin versus twice-daily penicillin V in group A beta-haemolytic streptococcal pharyngitis. Archives of disease in childhood. Jun 2008;93(6):474-478.
- Clegg HW, Ryan AG, Dallas SD, et al. Treatment of streptococcal pharyngitis with once-daily compared with twice-daily amoxicillin: a noninferiority trial. The Pediatric infectious disease journal. Sep 2006;25(9):761-767.
- Altamimi S, Khalil A, Khalaiwi KA, Milner RA, Pusic MV, Al Othman MA. Short-term late-generation antibiotics versus longer term penicillin for acute streptococcal pharyngitis in children. Cochrane Database Syst Rev. Aug 15 2012(8):Cd004872.
- 清水博, 齋藤美和子, 厚見恵, 久保田千鳥, 森雅亮. A群β溶連菌に対するペニシリン系とセフェム系抗菌薬の除菌率及び再発率. 日本小児科学会雑誌. 2013; 117(10):1569-1573.
- 奥野ルミ, 久保田寛顕, 内谷友美, et al. 2011~2014年に分離されたA群溶血性レンサ球菌(Streptococcus pyogenes)の薬剤感受性について. IASR. 2015; 36:152.
- van Driel ML, De Sutter AI, Thorning S, Christiaens T. Different antibiotic treatments for group A streptococcal pharyngitis. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Mar 17;3(3):CD004406.
- Roosevelt GE. Acute Inflammatory Upper Airway Obstruction (Croup, Epiglottitis, Laryngitis, andBacterial Tracheitis). In: Kliegman RM, Stanton BMD, Geme JS, Schor NF, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 20th ed. Amsterdam: Elsevier; 2015:2031-2036.
- 厚生労働省. ジフテリア. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/diphtheria/index.html. 最終閲覧日2023年3月24日.
- Bower J, McBride JT. Croup in Children (Acute Laryngotracheobronchitis). In: Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ, eds. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. 8th ed. Philadelphia: Saunders; 2015:762-766.
- Bjornson C, Russell K, Vandermeer B, Klassen TP, Johnson DW. Nebulized epinephrine for croup in children. Cochrane Database Syst Rev. Oct 10 2013(10):CD006619.
- Eghbali A, Sabbagh A, Bagheri B, Taherahmadi H, Kahbazi M. Efficacy of nebulized L-epinephrine for treatment of croup: a randomized, double-blind study. Fundam Clin Pharmacol. Feb 2016;30(1):70-75.
- Aregbesola A. et al. Glucocorticoids for croup in children. Cochrane Database Syst Rev. 2023;1(1):CD001955.
- Lenney W, Boner AL, Bont L, et al. Medicines used in respiratory diseases only seen in children. The European respiratory journal. Sep 2009;34(3):531-551.
- Moore M, Little P. Humidified air inhalation for treating croup: a systematic review and meta-analysis. Fam Pract. Sep 2007;24(4):295-301.
- Kliegman RM, Stanton BMD, Geme JS, Schor NF, Behrman RE Wheezing, Bronchiolitis, and Bronchitis. Nelson Textbook of Pediatrics. 19th ed. Philadelphia: Elsevier; 2011:1456-1463.
- Chang AB, Robertson CF, Van Asperen PP, et al. A multicenter study on chronic cough in children : burden and etiologies based on a standardized management pathway. Chest. Oct 2012;142(4):943-950.
- Marchant J, Masters IB, Champion A, Petsky H, Chang AB. Randomised controlled trial of amoxycillin clavulanate in children with chronic wet cough. Thorax. Aug 2012;67(8):689-693.
- National Institute for Health and Care Excellence(NICE). Bronchiolitis in children: diagnosis and management. 2015.
- Becker LA, Hom J, Villasis-Keever M, van der Wouden JC. Beta2-agonists for acute cough or a clinical diagnosis of acute bronchitis. Cochrane Database Syst Rev. Sep 03 2015(9):Cd001726.
- Gonzales R, Anderer T, McCulloch CE, et al. A cluster randomized trial of decision support strategies for reducing antibiotic use in acute bronchitis. JAMA internal medicine. Feb 25 2013;173(4):267-273.
- Little P, et al. Antibiotics for lower respiratory tract infection in children presenting in primary care in England (ARTIC PC): a double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Lancet. 2021 Oct 16;398(10309):1417-1426.
- Hersh AL, Jackson MA, Hicks LA. Principles of judicious antibiotic prescribing for upper respiratory tract infections in pediatrics. Pediatrics. Dec 2013;132(6):1146-1154.
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) guidance on prescribing of antibiotics for self-limiting respiratory tract infections in adults and children in primary care. 2008.
- Gibson PG, Chang AB, Glasgow NJ, et al. CICADA: Cough in Children and Adults: Diagnosis and Assessment. Australian cough guidelines summary statement. The Medical journal of Australia. Mar 01 2010;192(5):265-271.
- Braman SS. Chronic cough due to acute bronchitis: ACCP evidence-based clinical practice guidelines. Chest. Jan 2006;129(1 Suppl):95s-103s.
- Gardiner SJ, Gavranich JB, Chang AB. Antibiotics for community-acquired lower respiratory tract infections secondary to Mycoplasma pneumoniae in children. Cochrane Database Syst Rev. Jan 08 2015;1:Cd004875.
- Recommended Antimicrobial Agents for the Treatment and Postexposure Prophylaxis of Pertussis: 2005 CDC Guidelines
- Ruffles TJC, et al. Duration of amoxicillin-clavulanate for protracted bacterial bronchitis in children (DACS): a multi-centre, double blind, randomised controlled trial. Lancet Respir Med. 2021 Oct;9(10):1121-1129.
- Ralston SL, Lieberthal AS, Meissner HC, et al. Clinical practice guideline: the diagnosis, management, and prevention of bronchiolitis. Pediatrics. Nov 2014; 134(5):e1474-1502.
- Haskell L, Tavender EJ, Wilson CL, O'Brien S, Babl FE, Borland ML, Cotterell E, Schembri R, Orsini F, Sheridan N, Johnson DW, Oakley E, Dalziel SR; PREDICT Network. Effectiveness of Targeted Interventions on Treatment of Infants With Bronchiolitis: A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr. 2021 Aug 1;175(8):797-806.
- Schreiber S, Ronfani L, Ghirardo S, et al. Nasal irrigation with saline solution significantly improves oxygen saturation in infants with bronchiolitis. Acta paediatrica 2016;105:292-6.
- Farley R, Spurling GK, Eriksson L, Del Mar CB. Antibiotics for bronchiolitis in children under two years of age. Cochrane Database Syst Rev. Oct 09 2014(10):Cd005189.
- Librizzi J, McCulloh R, Koehn K, Alverson B. Appropriateness of testing for serious bacterial infection in children hospitalized with bronchiolitis. Hospital pediatrics 2014; 4:33-8.
- Tomochika K, Ichiyama T, Shimogori H, Sugahara K, Yamashita H, Furukawa S. Clinical characteristics of respiratory syncytial virus infection-associated acute otitis media. Pediatrics international: official journal of the Japan Pediatric Society. Aug 2009; 51(4):484-487.
- Andrade MA, Hoberman A, Glustein J, Paradise JL, Wald ER. Acute otitis media in children with bronchiolitis. Pediatrics. Apr 1998; 101(4 Pt 1):617-619.
- Fernandes RM, Bialy LM, Vandermeer B, et al. Glucocorticoids for acute viral bronchiolitis in infants and young children. Cochrane Database Syst Rev. Jun 04 2013(6):Cd004878.
- Hartling L, Bialy LM, Vandermeer B, et al. Epinephrine for bronchiolitis. Cochrane Database Syst Rev. Jun 15 2011(6):Cd003123.
- Gadomski AM, Scribani MB. Bronchodilators for bronchiolitis. Cochrane Database Syst Rev. Jun 17 2014(6):Cd001266.
- Zhang L, Mendoza-Sassi RA, Klassen TP, Wainwright C. Nebulized Hypertonic Saline for Acute Bronchiolitis: A Systematic Review. Pediatrics. Oct 2015;136(4):687-701.
- Zhang L, Mendoza-Sassi RA, Wainwright C, Klassen TP. Nebulised hypertonic saline solution for acute bronchiolitis in infants. Cochrane Database Syst Rev 2013:Cd006458.
- WHO. The Treatment of Diarrhoea: a manual for physicians and other senior health workers. 2005.
- Sharland M, Butler K, Cant A. Manual of Childhood Infection: The Blue Book (Oxford Specialist Handbooks in Paediatrics) 4th Edition. 2016.
- Kliegman R, Stanton B, Geme J, Schor N. Nelson Textbook of Pediatrics. 20th edition. Phialdelphia, PA: Elsevier; 2015. p1761.
- 国立感染症研究所. <注目すべき感染症>感染性腸炎. 2012.
- Patel MM, et al. Systematic literature review of role of noroviruses in sporadic gastroenteritis. Emerging infectious diseases 2008;14:1224-31.
- 国立感染症研究所. <速報>ロタウイルス胃腸炎の発生動向とワクチン導入後の報告数の推移. IASR. 2015;36:145-146.
- 国立感染症研究所. 病原体微生物検出情報 ロタウイルス 2018/19~2022/23シーズン. https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr/510-surveillance/iasr/graphs/1532-iasrgv.html. 最終閲覧日2023年3月24日.
- Bhutta Z. Acute Gastroenteritis in Children. Nelson Textbook of Pediatrics: Elsevier; 2016:p1870.
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Diarrhoea and vomiting diagnosis, assessment and management in children younger than 5 years caused by gastroenteritis. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK63844/. 最終閲覧日2023年3月24日.
- Guarino A, et al. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe: update 2014. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014 Jul;59(1):132-52.
- Freedman BS, et al. A randomized trial evaluating virus-specific effects of a combination probiotic in children with acute gastroenteritis. Nat Commun. 2020;11(1):2533.
- Schnadower D, et al. Association Between Diarrhea Duration and Severity and Probiotic Efficacy in Children With Acute Gastroenteritis. Am J Gastroenterol. 2021;116(7):1523-1532.
- Vassilopoulou L. et al. Effectiveness of probiotics and synbiotics in reducing duration of acute infectious diarrhea in pediatric patients in developed countries: a systematic review and meta-analysis. Eur J Pediatr. 2021;180(9):2907-2020.
- Collinson S, et al. Probiotics for treating acute infectious diarrhoea. Cochrane Database SystRev. 2020 Dec 8;12(12):CD003048.
- Szajewska H, et al. Working Group on Probiotics and Prebiotics of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Use of Probiotics for the Management of Acute Gastroenteritis in Children: An Update. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020 Aug;71(2):261-269.
- JaA. The Rational Clinical Examination: Evidence-Based Clinical Diagnosis. McGraw-Hill Education, LLC; 2009.
- Tajiri H, et al. A role for fosfomycin treatment in children for prevention of haemolytic-uraemic syndrome accompanying Shiga toxin-producing Escherichia coli infection. Int J Antimicrob Agents. 2015 Nov;46(5):586-9.
- Myojin S, et al. Interventions for Shiga toxin-producing Escherichia coli gastroenteritis and risk of hemolytic uremic syndrome: A population-based matched case control study. PLoS One. 2022 Feb 4;17(2):e0263349.
- Ikeda K, Ida O, Kimoto K, Takatorige T, Nakanishi N, Tatara K. Effect of early fosfomycin treatment on prevention of hemolytic uremic syndrome accompanying Escherichia coli O157:H7 infection. Clinical nephrology 1999;52:357-62.
- 日本耳科学会/日本小児耳鼻咽喉科学会/日本耳鼻咽喉科感染症・エアロゾル学会. 小児急性中耳炎診療ガイドライン2018年版. 金原出版; 2018
- 日本耳科学会/日本小児耳鼻咽喉科学会. 小児滲出性中耳炎診療ガイドライン 2015年版. 金原出版; 2015
- Faden H, Duffy L, Boeve M. Otitis media: back to basics. Pediatr Infect Dis J. 1998;17:1105-13
- Kerschner JE, Preciado D. Otitis media. In: Kliegman RM, Stanton BF, St. Geme JW, Schor NF, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 20th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2016:chap 640 p3085
- Todberg T, Koch A, Andersson M, Olsen SF, Lous J, Homoe P (2014) Incidence of Otitis Media in a Contemporary Danish National Birth Cohort. PLoS ONE 9(12)
- Hotomi M, Yamanaka N, Saito T, Shimada J, Suzumoto M, Suetake M, Faden H. Antibody responses to the outer membrane protein P6 of non-typeable Haemophilus influenzae and pneumococcal capsular polysaccharides in otitis-prone children. Acta Otolaryngol. 1999;119(6):703-7.
- Yamanaka N, Faden H: Antibody response to outer membrane protein of nontypeable Haemophilus influenzae in otitis-prone children. J Pediatr 1993;122:212-8.
- Lieberthal AS, Carroll AE, Chonmaitree T, Ganiats TG, Hoberman A, Jackson MA, Joffe MD, Miller DT, Rosenfeld RM, Sevilla XD, Schwartz RH, Thomas PA, Tunkel DE. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics. 2013 Mar;131(3):e964-99
- 佐伯忠彦;愛媛医学13巻1号 26-33, 1994.
- Heikkinen T, Ruuskanen O. Signs and symptoms predicting acute otitis media. Arch Pediatr Adolesc Med. 1995 Jan;149(1):26-9.
- Uhari M, Niemelä M, Hietala J. Prediction of acute otitis media with symptoms and signs. Acta Paediatr 1995;84(1):90-2.
- Damoiseaux RA, van Balen FA, Hoes AW, Verheij TJ, de Melker RA. Primary care based randomised, double blind trial of amoxicillin versus placebo for acute otitis media in children aged under 2 years. BMJ. 2000 Feb 5;320(7231):350-4.
- Venekamp RP, et al. Antibiotics for acute otitis media in children. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jun 23;2015(6):CD000219.
- Glasziou PP, Del Mar CB, Sanders SL, Hayem M. Antibiotics for acute otitis media in children. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(1):CD000219.
- Rosenfeld RM, Kay D. Natural history of untreated otitis media. Laryngoscope. 2003 Oct;113(10):1645-57.
- Jacobs J, Springer DA, Crothers D. Homeopathic treatment of acute otitis media in children: a preliminary randomized placebo-controlled trial. Pediatr Infect Dis J. 2001 Feb;20(2):177-83.
- Venekamp RP, Sanders S, Glasziou PP, et al. Antibiotics for acute otitis media in children. Cochrane Database Syst Rev. 2015(6):CD000219.
- Casey JR, Adlowitz DG, Pichichero ME. New Patterns in the otopathogens causing acute otitis media six to eight years after introduction of pneumococcal conjugate vaccine. Pediatr Infect Dis J. 2010 Apr;29(4):304-9.
- Shiro H, Sato Y, Toyonaga Y, et al. Nationwide survey of the development of drug resistance in the pediatric field in 2000-2001, 2004, 2007, 2010, and 2012: evaluation of the changes in drug sensitivity of Haemophilus influenzae and patients’ background factors. J Infect Chemother 2015; 21:247-56.
- Kono M, et al. Features predicting treatment failure in pediatric acute otitis media. J Infect Chemother. 2021 Jan;27(1):19-25.
- Hoberman A, Paradise JL, Rockette HE, Kearney DH, Bhatnagar S, Shope TR, Martin JM, Kurs-Lasky M, Copelli SJ, Colborn DK, Block SL, Labella JJ, Lynch TG, Cohen NL, Haralam M, Pope MA, Nagg JP, Green MD, Shaikh N. Shortened Antimicrobial Treatment for Acute Otitis Media in Young Children. N Engl J Med. 2016;375:2446-2456.
入院患者における抗微生物薬適正使用編
13. 入院患者の感染症に対する基本的な考え方
(1) 診断・治療のプロセス
(i) 入院患者の発熱へのアプローチ
要旨
- 入院患者の発熱ではまずは感染症の可能性からアセスメントする。
- 原因微生物の特定には臓器特異的な臨床所見に対応した培養検査が必須である。
- クロストリディオイデス・ディフィシル感染症(Clostridioides difficile Infection: CDI)を疑う場合は便培養ではなくCDトキシン/ Glutamate dehydrogenase(GDH)検査を提出する(CDIの項参照)。
- 感染臓器が特定できない場合は、血液培養を2セット採取する。
- 感染症の検索をしても感染症を示唆する所見が得られなければ、偽痛風や薬剤熱等の非感染性疾患の可能性について考える。
① 疫学
入院患者の発熱とは、入院して48時間以上経過した後に新たに発熱したものを指す。入院患者の発熱の原因では感染症が最も多い(図1)ため1、まずは感染症の可能性から考える。感染症の中では肺炎、手術部位感染症(Surgical site infection: SSI)、腸管感染症、尿路感染症(Urinary tract infection: UTI)、血流感染症等が多い2。非感染症の中では、薬剤熱、結晶性関節炎、手技に関連する発熱、血腫等が見られる1。
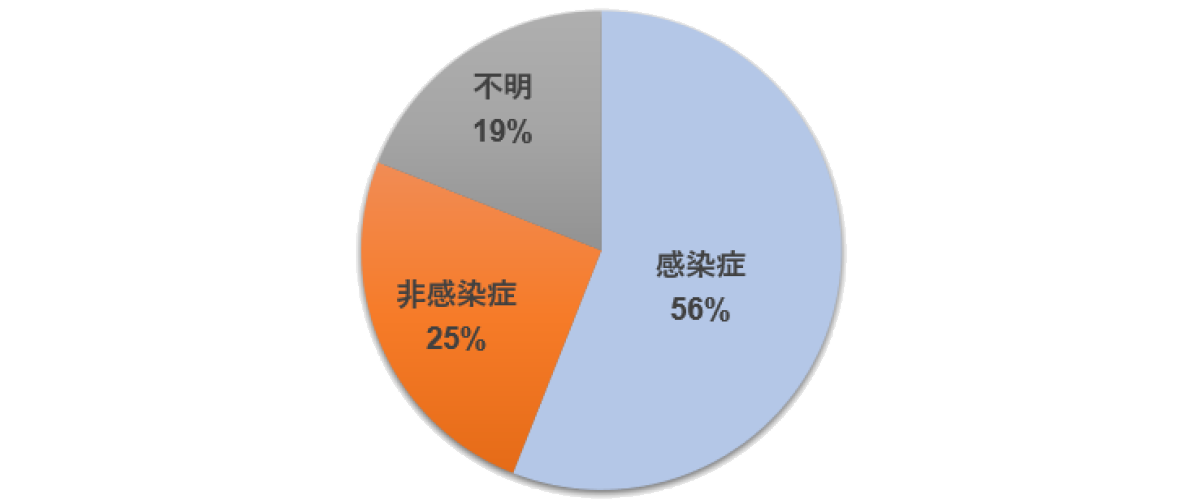
図1. 入院患者の発熱の内訳1
② 診断のポイント
【肺炎】
- 臨床所見:咳・痰、呼吸音の異常、呼吸数増加、動脈血酸素分圧(PaO2)低下、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)低下
- 臓器診断に必要な検査:胸部X線、必要に応じて胸部CT検査
- 微生物診断に必要な検査:痰グラム染色、痰培養
- 人工呼吸器関連肺炎(Ventilator-associated pneumonia: VAP)の場合も同様である。
【UTI】
- 臨床所見:背部痛や肋骨脊柱角(Costovertebral angle: CVA)、叩打痛があれば急性腎盂腎炎を疑うが、これらの症状が見られない場合も多い。男性の場合、前立腺の圧痛や精巣上体の圧痛、陰嚢の腫大も確認する。
- 臓器診断に必要な検査:尿中白血球定性、尿沈渣。
- 微生物診断に必要な検査:尿グラム染色、尿培養。
- カテーテル関連尿路感染症(Catheter-associated urinary tract infections: CAUTI)を疑う場合は、尿道カテーテルを入れ替えてから尿培養を提出することが望ましい。
【腸管感染症】
- 入院72時間以降に新たに生じた下痢のうち、感染性の下痢が29.4%(CDI 24.6%、その他 4.8%)、非感染性が45.3%、原因不明が25.3%とされる3。ここでは主にCDIを例に挙げる。
- 臨床所見:食欲低下、腹痛、下痢(初期には下痢を認めないことがある)
- 臓器診断に必要な検査:特になし。臨床症状で判断する。
- 微生物診断に必要な検査:CDIの項参照。CDI の診断に便培養は原則不要である。
【カテーテル関連血流感染症】
- 末梢静脈カテーテル、中心静脈カテーテル、動脈留置カテーテル等あらゆるカテーテルはカテーテル関連血流感染症(Catheter-related blood stream infection: CRBSI)の原因となる。
- 臨床所見:カテーテル刺入部の発赤があれば感染を疑うが、中心静脈カテーテルや中心静脈ポートの感染ではほとんど見られず、その頻度は末梢静脈カテーテルで約60%4、中心静脈カテーテルで約3%程度である5。
- 臓器診断に必要な検査:血液培養2セット。
※中心静脈カテーテルが挿入されている場合、1セットはカテーテル逆流血で、もう1セットは末梢血で採取する。2セットとも同一菌種が検出されれば、中心静脈カテーテル関連血流感染症(Central line-associated bloodstream infection: CLABSI)と診断する。
- カテーテル先端培養と末梢血の血液培養で同一菌種が検出された場合にもCRBSIと診断できる5。なお、逆流血の方が末梢血よりも2時間以上早く陽性になればCRBSI診断の感度85%、特異度91%との報告もある6。
- 微生物診断に必要な検査:血液培養2セット。
【創部感染症】
- 主に褥瘡感染や手術後のSSIがある。SSIは感染部位によって、浅部切開部SSI、深部切開部SSI、臓器・体腔SSIに分けられる7。
- 臨床所見:創部からの排膿、創部の発赤、腫脹、熱感、疼痛。
- 浅部切開部SSI:切開部表面からの排膿、創部の発赤、腫脹、熱感、疼痛。
- 深部切開部SSI:切開深部からの排膿、創部の発赤、腫脹、熱感、疼痛。
- 臓器・体腔SSI:臓器・体腔に入っているドレーンからの排膿。
- 臓器診断に必要な検査:浅部SSIは肉眼所見で臓器診断が可能だが、深部SSI、臓器・体腔SSIの場合、エコーやCT検査等を施行する。
- 微生物診断に必要な検査:創部滲出液や膿汁のグラム染色・培養。臓器・体腔から無菌的に採取された液体又は組織のグラム染色・培養。
(ii) 適切な培養の実施
要旨
- 臨床症状のない患者に対して培養検査を行わない。
- 入院72時間以上経過した後に発症した下痢症に対して便培養検査を行わない。
- 抗菌薬投与前と、広域抗菌薬に変更前は必ず血液培養検査を提出する。
- 原則として、感染症の治療効果判定として培養検査を再検しない。
① 培養検体採取時の注意点
臨床症状のない患者に対して培養検査を行わない(呼吸器症状のない患者の痰培養検査等)。感染症が疑われる患者に抗菌薬を投与する際は、投与前に必ず培養検査を提出する。臨床症状の改善に乏しく、既に開始されている抗菌薬を変更する場合も、培養検査の提出が望ましい。
痰は唾液成分が少なく、膿性部分が多いものが培養に適している。唾液成分しかない不良検体を培養検査に提出しない。
尿は、中間尿又は導尿での採取が推奨される。尿道留置カテーテルが挿入されている患者でUTIを疑った場合には、可能であればカテーテルを入れ替えてから尿検体を採取することが望ましい。尿沈渣でも白血球が見られなければ、尿培養を提出しない。
便は下痢便のみ培養に提出する。耐性菌スクリーニング検査以外で固形便を提出してはいけない。入院72時間以上経過した後に発症した下痢症ではCDIの頻度が高いため、通常の便培養ではなく、CDIの検査を行う(C. difficileの項目参照)3。
膿汁は、既に空気に触れている開放膿と空気に触れていない閉鎖膿に分けられる。閉鎖膿の場合、嫌気性菌の関与も考えられるため、嫌気培養も提出する。糖尿病足壊疽等の創部培養を提出する際は、創部表面ではなく壊死組織をデブリドマンした後のなるべく深部の液体や組織を検体として提出することが推奨されている8。創部表面の培養に関しては常在菌を拾い上げてしまうこともあり、解釈が難しい。
② 血液培養を採取すべきタイミング
抗菌薬投与開始前と、既に投与中で広域抗菌薬に変更する前には必ず血液培養を採取する。発熱、悪寒戦慄、原因不明の低体温、原因不明のショック、原因不明の意識障害、原因不明の炎症反応上昇等でも血液培養を採取する。1セットあたり20mL(好気ボトル10mL、嫌気ボトル10mL)の血液を採取し、原則2セット以上採取する。成人の入院患者を対象にした研究では血液培養1セット、2セット、3セット採取時の陽性率はそれぞれ73.1%、89.7%、98.2%である9。
③ その他
原則、感染症の治療効果判定として培養検査を再検しない。例外は、感染性心内膜炎等の血管内感染症、又は血液から黄色ブドウ球菌あるいはカンジダが検出された場合である。これらの状況では、治療効果判定として治療開始後に必ず血液培養を再検すべきである(「黄色ブドウ球菌」、「カンジダ」の項参照)。なお、肺炎における喀痰やUTIにおける尿等、グラム染色で菌の減少や消失を見ることにより治療効果判定を行うことができる場合もある。
(iii) 経験的(エンピリック)治療
要旨
- 抗菌薬開始前には、バイタルサインの評価を中心に、直ちにエンピリック治療が必要かどうかについて検討する。
- エンピリック治療が必要な感染症と判断した場合、抗菌薬開始前に原因臓器と原因微生物について検討し、想定された原因微生物に対して効果のある抗菌薬を選択する。
- 抗菌薬開始後には、臨床経過や培養結果を元に患者の状態を再評価し、抗菌薬調整する。
抗菌薬は通常、経験的に投与される。つまり、どの細菌が患者に感染しているのか、あるいは患者が実際に細菌感染しているのかさえも正確に把握できないまま投与が開始されことが多い11。日常診療において、通常は診断が確定してから治療が開始されることが多いが、感染症診療では培養検査の結果を得るのに日数を要するため、診断が確定する前に経験的治療を開始することが多い。よって治療開始前に原因臓器や原因微生物をある程度想定しておくことが重要である。
① 感染症に対して経験的治療が必要な状況であるかどうかを評価する
「細菌感染症=直ちに経験的治療が必要」というわけではなく、結果が待てる状況であれば結果を待つ選択も可能である。一方で、免疫不全者における細菌感染症や、敗血症の場合は速やかな抗菌薬投与が必要だが、どのように敗血症を早期に察知するかリスクの評価が重要である。実臨床においては、覚えやすいquick Sequential Organ Failure Assessment(qSOFA)や集中治療領域ではSOFAスコア等が使用されることもあるが、単一の指標だけでは判断せず、複合的に判断することが重要である。表にバイタルサインやその他の指標の評価のポイントについてまとめた。特に発熱前さらに治療後と比較をすることで、重症度評価や経過の予測に役立つ。
表1. 感染症評価の際の評価項目とそのポイント
| バイタルサイン | ポイント |
|---|---|
| 体温 |
|
| 呼吸数 |
|
| 血圧 |
|
| 脈拍数 |
|
| 意識レベル |
|
| 入院患者で有用な指標 | ポイント |
| 食事量 |
|
| 悪寒、戦慄 |
|
| 血糖値 |
|
日常臨床で頻用される白血球数(WBC)、C反応性蛋白(CRP)は、他の様々な要因で変動するため経験的治療に対する主たる指標として推奨されない17。プロカルシトニンは細菌感染症に対して特異的と言われているが、院内の菌血症患者における感度は十分ではないという報告もある1。プロカルシトニンが陽性だったとしても、原因臓器や原因微生物の推定には寄与しないため、どの抗菌薬を選択するか、といった判断に何ら影響しない。よって、単一の数値のみで判断をせずに、発熱以外のバイタルサイン、悪寒戦慄の有無、食事量の低下や低血糖等の敗血症の前兆を見逃さないことが重要である。上記徴候に加えて、臓器障害があれば重症であり、より初期治療選択が重要になる。臓器障害評価の1つとして既述のSOFAスコアがある18。
② 院内発熱に対する経験的治療の実際
入院して48時間以内の場合は、市中発症として対応し、上記以降は院内で起きた感染症として対応する。ただし、入院後間もない発熱でも施設からの入院や直近90日以内の入院歴等は、院内発熱に近い状態を想定することが重要である。
経験的治療の抗菌薬のスペクトラムは、鑑別診断に挙がった疾患の原因微生物をカバーするために必要な範囲に留める必要がある19。つまり、重症 = 広域抗菌薬、耐性菌保有者 = 耐性菌カバーというわけではない。耐性菌保有患者におけるその耐性菌による感染症の発生率は、8〜14%と報告されており決して高くはない20。
重症患者では、抗菌薬の速やかな投与が重要である10。「Surviving Sepsis Campaign Guidelines 2021」では、ショックを呈する敗血症の場合には適切な培養を採取して1時間以内の投与が推奨されている17。
一方で発熱はしているが、敗血症としての重症化の懸念が低いと判断される症例においては、必ずしも経験的治療から広域抗菌薬を選択する必要はない。その場合は培養を採取した上で、抗菌薬を投与せずに経過観察するという選択肢や、狭域の抗菌薬で治療を開始して、後日判明する培養結果等を参考に抗菌薬を変更するという戦略も存在する21。
抗菌薬治療を開始したら、治療開始後に適正化の作業を必ず行うことが重要である。経験的治療の選択については、耐性菌の頻度等地域・施設間の差が大きい。このため、病院のASTの推奨する院内ガイドライン等のある場合はそれを参照する。
院内で問題となる細菌感染症の鑑別は比較的限られており、CRBSI(末梢静脈ライン、中心静脈ライン、動脈血ライン、透析カテーテル等)、UTI(CAUTIを含む)、肺炎(VAPを含む)、CDI、SSIの頻度が高い。これら以外に胆道系感染症、褥瘡部位等からの皮膚軟部組織感染症がある。それぞれの感染症で問題となる代表的な原因微生物を表2にまとめた。
表2. 院内での頻度の高い感染症で問題となる代表的な原因微生物
| 感染症 | 想定される原因微生物 |
|---|---|
| CRBSI |
|
| UTI |
|
| 肺炎(VAPを含む) |
|
| SSI |
|
最後に、抗菌薬を開始する時には、抗菌薬の種類だけでなく、適切な量を適切な投与間隔で、適切なタイミングで投与することが重要である。いずれかが不適切だと感染症の治癒の問題ばかりではなく、副作用・耐性菌のリスクが上昇するため、これらを遵守することが患者のアウトカム改善の視点でも重要といえる22。
腎機能に応じた投与計画をもとに、病棟薬剤師やASTから疑義照会があった場合には、それをオーダーに反映する必要がある。
(iv) 培養結果の解釈
要旨
- 培養結果=真の原因微生物とは限らない。
- それぞれの臓器ごとに原因微生物の頻度は異なるため、検出された微生物の種類だけでなく、その微生物が検出された培養検体の種類にも注目する。
- 尿培養で黄色ブドウ球菌が検出された場合は、UTIの可能性は低く、血流感染症の可能性を検討すべきである
- コンタミネーション(汚染菌)となりやすい細菌が血液培養2セット中1セットから検出された場合はコンタミネーションの可能性が高く、2セット中2セットとも検出された場合は真の原因菌と考える。
① 培養結果の解釈
培養から検出される菌は、検体によっては定着菌(保菌)の可能性があり、必ずしも培養で検出された菌=治療対象とはならない。この原則は、後述する「入院患者の感染症で問題となる微生物」においても当てはまり、たとえ薬剤耐性菌が検出されても定着菌であれば、治療対象とする必要はない。臨床所見やグラム染色所見等を合わせて、真の原因菌かどうか常に検討すべきである。
病院内での肺炎をきたす微生物は耐性グラム陰性桿菌や黄色ブドウ球菌が多い。呼吸器検体から表皮ブドウ球菌やカンジダ、腸球菌が培養されたとしても通常は原因菌とは考えない。病院内でのUTIは耐性グラム陰性桿菌や腸球菌が多い。カンジダや黄色ブドウ球菌、表皮ブドウ球菌は通常原因菌とは考えない。ただし、尿培養から黄色ブドウ球菌が検出された場合、約27%で血流感染を合併するため、炎症反応の上昇があれば血液培養も採取すべきである23。糖尿病足壊疽で表面を擦過した検体は真の原因菌ではなくコンタミネーションの可能性が高い。
② 血液培養検査の結果
血液培養から検出された菌のうち、真の原因菌かコンタミネーションかは菌種によって判断が異なる。
肺炎球菌やA群β溶血性連鎖球菌、黄色ブドウ球菌、グラム陰性桿菌、カンジダ等は1セットでも検出されたら真の原因菌と考える。一方で、コアグラーゼ陰性ブドウ球菌(Coagulase-negative Staphylococci: CNS)、Cutibacterium(旧Propionibacterium)spp.(Propionibacterium acnesはCutibacterium属に再分類された)、Corynebacterium spp.、Bacillus spp.等が1セットのみ検出された場合は汚染菌の可能性を考える(表3、表4)。ただし、これらの菌種でも2セット以上で検出されたら真の原因菌として治療することを検討すべきである24。
CNSに限らず、コンタミネーションかどうかの判断に迷う場合は、血液培養を再検する。患者の臨床症状が改善しない場合は血液培養再検に加え、抗菌薬治療の開始を検討する。
血液培養を1セットのみ提出した場合は、コンタミネーションかどうかの判断は困難である。
表3. 血液培養から検出された微生物について真の原因菌とコンタミネーションの割合25
| 菌名 | 真の原因菌 | コンタミネーション | 臨床意義不明 |
|---|---|---|---|
| 肺炎球菌 | 100% | 0% | 0% |
| Candida glabrata | 100% | 0% | 0% |
| Candida albicans | 98% | 0% | 2% |
| β溶連菌 | 97% | 0% | 3% |
| Bacteroides spp. | 97% | 0% | 3% |
| 大腸菌 | 97% | 1% | 2% |
| Klebsiella pneumoniae | 95% | 1% | 4% |
| 黄色ブドウ球菌 | 93% | 1% | 6% |
| Clostridium spp. | 64% | 24% | 12% |
| 腸球菌 | 63% | 11% | 26% |
| Viridans Streptococci | 30% | 55% | 15% |
| CNS | 10% | 82% | 7% |
| Corynebacterium spp. | 8% | 88% | 3% |
| Bacillus spp.※ | 0% | 100% | 0% |
※ Bacillus spp.に関しては、8.3%で真の原因菌だったとの報告もある24
表4. 血液培養よりCNS(Staphylococcus epidermidis:表皮ブドウ球菌)が陽性時の真の原因菌とコンタミネーションの割合24
| 陽性セット数 | 真の原因菌 | コンタミネーション | 判定不能 |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 0 | 97% | 3% |
| 1/2 | 2% | 95% | 3% |
| 2/2 | 60% | 3% | 37% |
| 1/3 | 0 | 100% | 0% |
| 2/3 | 75% | 0 | 25% |
| 3/3 | 100% | 0 | 0% |
(v) 抗菌薬の選択の適正化
要旨
- 治療開始後には、必ず治療効果を評価し、治療開始72時間の時点で細菌感染症の証拠がなければ抗菌薬の中止を検討する。
- 培養で検出された細菌のうち、原因菌と考えられる細菌をカバーする狭域スペクトラムの抗菌薬へ変更する(狭域化:de-escalation, narrowing )。
- 治療開始72時間以内であっても患者の状態が悪化する場合には、原因臓器、原因微生物、抗菌薬選択について再検討する。
① 治療効果と培養結果判定のタイミング
初期治療において適切な抗菌薬を選択することは難しく、不適切な使用や不要な抗菌薬が投与されている場合も少なくない(補遺p1参照)。
よって、治療開始後は適切に治療効果を評価し、培養検査の結果等を参考にして抗菌薬治療を適正化することが必要である。入院患者に対して開始した経験的治療の抗菌薬に対する治療評価と抗菌薬の適正化は、治療開始72時間後を推奨する26-29。
血液培養は検査が開始され48時間以上陰性であれば、99.8%は陰性であることが報告されている30。好中球減少性発熱の患者における菌血症も24時間以内に血液培養は90%以上で陽性になることが報告されている31。カンジダは一般細菌と比べてより長い発育時間を要するが、院内発熱で問題となる真菌のほとんどは培養開始から72時間以内に陽性となる。
喀痰培養、尿培養も感受性まで判明していない場合もあるが、原因菌として優位な菌がいるかどうかは判明している。そして、抗菌薬が奏効していれば、グラム染色では、培養結果が出る以前に菌数の減少や菌の消失を確認することができる。UTIについては、数時間後には菌減少を確認することができる。そして、肺炎、UTIは、72時間経過した時点で改善を認めているかどうかが治療効果判定の目安とされている29,32。
細菌検査を外部機関に委託している施設では輸送の分だけ評価タイミングが遅れる可能性がある。
日々、患者を評価することは重要であるが、実臨床において72時間後というのは、
A) 培養検査の結果のほとんどが判明し、感染症診断及び原因微生物診断が確立(あるいは疑いが否定)できるタイミング
B) 抗菌薬治療に対する効果が確認できるタイミング
であるため上記時間を推奨した33。なお、それよりも早期に適正化できる情報があるのであればその時点で適正化することはむしろ望ましい。
② 適切性の評価
経験的治療で開始した広域抗菌薬が、対象疾患に対して安全かつ有効であったとしても、その疾患が狭域の抗菌薬で治療可能かつ治療に関するエビデンスがある場合、現在使用している広域抗菌薬は不適切と判断される。その理由の一つは、上記状況では広域抗菌薬の過剰使用につながり、患者自身及び集団における耐性菌のリスクを増大させてしまうからである。もう一つの理由として、感染症病名ごとに第1選択薬が存在するが、多くは狭域抗菌薬であり、第1選択ではない広域抗菌薬を使用し続けることで治療失敗のリスクを高めてしまうからである(不適切:Inappropriate)。
培養結果・画像検査等から合理的に感染症が証明できない場合は、開始した抗菌薬の継続は不必要であると判断される。また、標準治療期間を超過して継続される抗菌薬も不必要と判断される(不必要:Unnecessary)。
投与量や投与間隔がその患者の腎機能から推奨される量ではない場合や推奨される投与方法ではない場合も不適切であると判断される(最適でない:Suboptimal)。
上記のような抗菌薬投与は、耐性菌の増加34、副作用の出現35、そしてCDIの発生につながることが強調されている36。内科入院患者に対する抗菌薬による副作用の頻度は、20%程度と言われており、そのうち、不要な抗菌薬で20%程度の副作用が起きていることが知られている35。
③ 院内発熱における抗菌薬の選択の適正化の実際
治療開始から72時間の時点で(それより早く判断できる場合は待つ必要はない)、
A) 治療経過、検査結果から治療対象となる細菌感染症が合理的に証明できない場合は開始した抗菌薬を終了する。
B) 治療経過、検査結果から細菌感染症の病名を決定する。
C) MRSA等抗MRSA薬が必要な菌の検出がなければ、抗MRSA薬は終了する。
D) カルバペネム系抗菌薬で経験的治療を開始した場合は、Extended-spectrum β-lactamase(ESBL)産生菌による菌血症、カルバペネム系抗菌薬でしか治療できない感染症、血液悪性腫瘍患者における好中球減少性発熱でフォーカスが不明な重症例を除き、より狭域な抗菌薬への変更を行う。
E) 偏性嫌気性菌を含む複数菌が関与する感染症がない場合は、β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗菌薬以外の抗菌薬へ変更を行う。
F) 適切な抗菌薬が投与されており、患者の状態が安定している場合には、あえて途中から広域抗菌薬に変更するメリットはない37。
G) 重症例、または抗菌薬を終了することによる懸念が強い場合には、診断された感染症病名に応じた治療期間を設定する。不必要な抗菌薬の因子として診断名の不確かさが指摘されており、診断をつけることはすなわちそれが抗菌薬適正使用につながる38。
④ 特定の状況に関する適正化
A) フルオロキノロン系抗菌薬は、フルオロキノロン系抗菌薬が第1選択となる感染症、又はフルオロキノロン系抗菌薬以外の代替薬がない場合に限り使用する。高齢者では頻度は低いが、重篤な副作用が報告されている39。
B) 重症の市中発症の消化管穿孔や院内発症の腹腔内感染症(臓器/体腔のSSI)でCandida spp.が検出された場合は治療対象とする40。
C) 血液培養で黄色ブドウ球菌、グラム陰性桿菌が1セットでも検出された場合は、原則として治療対象とし、複数菌感染症ではない状況であれば、検出された菌のみをカバーする抗菌薬へ適正化する41。
D) 好中球減少性発熱では、原則として抗緑膿菌活性のある抗菌薬を継続するが、バイタルサインが落ち着いていれば培養結果に基づき抗菌薬を適正化することも可能である42。血液悪性腫瘍(急性骨髄性白血病等)の患者背景でも同様の対応で臨床的悪化はないという報告がある43,44。
一般に、広域抗菌薬からの狭域化は安全に行えることが報告されている45-49。また抗真菌薬についても同様である50,51。そして、CDIのリスクを下げることが報告されている52。患者のアウトカムを最大化し、耐性菌・副作用・CDIのリスクを最小化することは、抗菌薬適正使用の目標である。
また、広域抗菌薬の処方後監査とフィードバック等のASTの推奨を受け入れることで、死亡率や入院期間には影響なく広域抗菌薬の使用量が低下することが示されている53-56。感染症の治療選択や適切な治療期間等については、日々知見がアップデートされている。抗菌薬選択の適正化に際して、主治医だけではなくASTや感染症専門医等病院全体でサポートして行うことが、患者個人の予後改善だけではなく、薬剤耐性の防止に対しても有効である。
(vi) 感染症の治療期間
要旨
- 感染症の治療期間は患者背景や感染臓器、原因微生物のすべてを考慮して決定する。
- 膿瘍等の合併症がなく、臨床経過も良好であれば、治療期間の短縮を検討できる。
- カテーテル等の人工物が抜去困難な場合、ドレナージしていない膿瘍がある場合は治療期間の延長を検討する。
① 入院中によく遭遇する感染症の一般的な治療期間と近年の動向
感染症に対する抗菌薬の投与期間は、もともと専門家の意見や経験則等に基づく慣習により決定されていた部分が大きく、ランダム化比較試験(Randomized controlled trial: RCT)等の良質なエビデンスに乏しいのが実情であった57。近年、抗菌薬の投与に伴う影響−薬剤耐性や常在細菌叢の破壊の問題−が大きいことが認識されるようになった58-60。抗微生物薬の治療期間を短縮できないか検討され、エビデンスが蓄積し一部はガイドラインにも反映されている61。一方、治療期間短縮の大きな懸念点は、治療失敗や再燃、それに伴う死亡率の増加等が挙げられる62-65。
表5. 入院中によく遭遇する感染症の治療期間の例と最近の動向
| 感染症 | 標準的な治療期間※ | 短縮された治療期間※ |
|---|---|---|
| VAPを含む院内肺炎 | 14-15日間 | 7-8日間 |
| 女性の非複雑性膀胱炎 | 3(-7)日間 | — |
| 女性の非複雑性腎盂腎炎 | 10-14日間 | 5-7日間 |
| 男性の有熱性UTI | 14日間 | — |
| CAUTI | 7-14日間 |
|
| 蜂窩織炎 | 10日間 | 5-6日間 |
| 非複雑性CRBSI |
|
— |
| 急性胆嚢炎 | 7-14日間 |
|
| 急性化膿性胆管炎 | 4-7日間 | 3-5日間 |
| 消化管穿孔による腹膜炎 | 10-15日間 | 4-8日間 |
| ドレナージが十分になされた 術後腹腔内感染症 |
10-15日間 | 4-8日間 |
| ドレナージが十分ではない 術後腹腔内感染症 |
症例ごとに検討が必要 | はっきりしていない |
| 非複雑性黄色ブドウ球菌菌血症※※ | 血液培養陰性化から28~42日間 | 血液培養陰性化から14日間 |
| 非複雑性グラム陰性菌菌血症 (腸内細菌目細菌) |
10-14日間 | 7日間 |
| 非複雑性グラム陰性菌菌血症 (ブドウ糖非発酵菌[例:緑膿菌、アシネトバクター等]) |
11-15日間あるいは11-21日間 | 6-11日間 |
※ 治療期間の留意点と参考文献は補遺p2-4を参照
※※ 黄色ブドウ球菌の項を参照
② 治療期間の考え方と注意点
A) 治療期間の決定に係る因子
治療期間の決定には臨床病態の推定・把握が欠かせない66。そのために把握しておく事項について、表6にまとめた。
まず、患者の基礎疾患等の背景因子を把握する。高度の免疫不全が存在する場合には短期治療を適用しづらい場合もある。また、固形臓器腫瘍が背景にある場合は、腫瘍による気道や胆道の狭窄・閉塞、手術・放射線治療による変化等、解剖学的な異常に伴う感染症の難治化が起こりやすい67,68。
次に、どの「臓器」に感染が生じているかを可能な限り明確にする。例として、男性において高熱を伴うUTIは腎盂腎炎・前立腺炎が一般的だが69、このうち前立腺炎は薬剤移行の悪さ等から2-4週間程度の治療期間を推奨する専門家もいる70。男性の有熱性UTI(前立腺炎も含まれる)では7日間治療が14日間治療に対して劣性と報告するRCTもある63。
原因微生物とその薬剤感受性も重要である。VAPにおいてはガイドライン上7日間の治療が推奨されている71。ただし、緑膿菌によるVAPに関するRCTでは、短期治療(8日間)が長期治療(15日間)に対する非劣性を示せなかった報告もある72。また、高度薬剤耐性菌に対し、第一選択ではない抗菌薬を使用する場合も、治療期間については慎重に検討すべきである。その他、外科的介入や、治療期間の延長が必要となるため、膿瘍等の局所の感染性合併症や感染性心内膜炎等の血管内感染症を含めた遠隔の感染性合併症の有無についても評価が必要である。また、人工物に感染が及んでいる場合、除去/抜去ができているかも治療期間を考える上で重要である。
さらに、黄色ブドウ球菌やカンジダの菌血症および血管内感染症の治療にあたっては血液培養の陰性化を確認する6,73,74。
治療への反応は、解熱や血行動態(バイタルサイン)の安定化に加え、食事摂取量等の全身状態の変化や採血所見の変化、感染臓器に特異的な症状所見の変化を参考にして評価する。治療への反応が緩徐な症例においては短期治療の適用を見送る場合もある75。
表6. 治療期間を決めるにあたり把握すべき事項
- 患者の基礎疾患等の背景因子:特に免疫不全や解剖学的な変化/異常
- 感染臓器
- 原因微生物とその感受性
- 膿瘍、膿胸、化膿性血栓等局所の感染性合併症はないか
- 遠隔の感染性合併症(関節炎、椎体椎間板炎、感染性心内膜炎等)はないか
- カテーテル等の人工物に感染が及んでいないか、及んでいる場合は除去/抜去できているか
- 血流感染症例、特に黄色ブドウ球菌・カンジダによる血流感染、CRBSIを含む血管内感染症では、血液培養の陰性化が確認できているか
- 抗微生物薬治療への反応は良いか(概ね72時間程度の時点で評価)
B) 短期治療を適用するための条件
多くの場合、短期治療を適用するための前提条件がある。例えば、黄色ブドウ球菌の菌血症の治療期間は血液培養が陰性化してから4~6週間が一般的だが76、一定の条件を満たす「非複雑性」菌血症の症例については、例外的に短期治療が選択可能かもしれない(黄色ブドウ球菌の項を参照)77。
また、グラム陰性菌による菌血症の治療期間は従来14日間の治療が一般的であったが、特に腸内細菌目細菌による「非複雑性」菌血症では7日間治療が非劣性であるとするRCTがあり78-80、メタアナリシスでも7日治療群と14日治療群の予後に有意な差は認めなかった81(補遺p5参照)。デルファイ法を用いてグラム陰性菌の「非複雑性」菌血症を定義する試みの研究では、表7の条件すべてを満たす症例を「非複雑性」菌血症と定義されている82。短期治療の患者への適応にあたってはこれらの条件に概ね相当するかを十分検討する。
表7. 専門家によるグラム陰性菌における非複雑性菌血症の定義の例82
| 菌血症の原因となった感染巣が以下のいずれか (1) UTI、(2) 腹腔内/胆道感染、(3) CRBSI、(4) 肺炎(器質的肺疾患のある症例・膿胸/膿瘍の合併・嚢胞性線維症例を除く)、(5) 皮膚軟部組織感染 |
|---|
| ソースコントロールができている – 感染した人工物やカテーテル・デバイスの除去、感染性液体貯留のほぼ完全なドレナージ、 必要に応じ画像検査で残存する感染巣がないことの確認 |
| 固形臓器移植や好中球減少症、ステロイド・免疫抑制剤使用等の免疫不全がない – ただし、免疫抑制治療中でも安定していれば症例ごとに判断する |
有効な抗菌薬治療開始後48-72時間以内に臨床上の改善が見られる、最低でも解熱し血行動態が安定化している |
(2) マネジメント
(i) 感染症が改善しない場合の考え方
要旨
- 感染症の治療効果判定の指標の選択とそのタイミングが重要
- 感染症の治療効果が不十分な原因は、抗微生物薬のスペクトラムに起因するもの以外にも多く存在するため、まず考えるべきは抗微生物薬の変更ではなくその原因についてアセスメントすることである
- 患者背景から考えられる原因微生物を想起し、現在投与中の抗微生物薬でどの微生物がカバーできていないか具体的に検討することが重要
A) 治療効果判定のタイミングと治療効果判定に用いる指標の重要性
治療効果判定のタイミングについては前項((v) 抗菌薬の選択の適正化、①治療効果と培養結果判定のタイミング)を参照のこと。このタイミングが早すぎる場合、有効な抗微生物薬が投与されているにも関わらず、効果が不十分と判定され結果として不要な抗菌薬の追加や変更につながる懸念がある。
また、治療効果判定に用いる指標の選択も重要である。一般に、感染症の治療効果判定に用いる指標は、発熱や食事量、白血球数・CRP値等の臓器非特異的な指標と、腎盂腎炎における腰痛や肋骨脊柱角(CVA)の叩打痛、膿尿・細菌尿等のような、感染臓器に比較的特異性の高い指標の2種類に大別することができる(表8)。感染症の治療効果判定にはこれら2種類の指標を意識し、治療効果が得られないと感じた場合に、どの指標が改善していないのかを考えることが大切である。
臓器非特異的な指標で注意が必要な点として、異なる臓器の感染症や非感染症による影響を受けやすいことが挙げられる。例えば、肺炎に対する治療において、呼吸数や酸素飽和度、呼吸苦等の自覚症状、あるいは聴診所見といった臓器特異的な指標は改善が得られているにも関わらず発熱のみが続く場合がある。こうした場合、肺炎の悪化以外に、肺膿瘍等の局所合併症、感染性心内膜炎や椎体椎間板炎といった遠隔の合併症、CAUTIやCRBSIといった肺炎以外の感染症による発熱の可能性、又は偽痛風や薬剤熱等の非感染性の発熱の可能性について検討する必要がある83。
一方、肺炎における胸部画像所見の改善のように、臓器特異的ではあるが、その改善が臨床的改善に遅れる指標もある84。このような場合、胸部画像所見のみで肺炎の治療効果判定を行うと、不必要な抗微生物薬の広域化や治療の長期化につながるリスクがある。さらに、特に院内発症の感染症では、当初から発熱やCRPの上昇等臓器非特異的な症状所見以外に臨床上の指標が乏しい場合がある(典型的にはCRBSIやCAUTIの一部等が当てはまる)。そのような臓器特異的な所見が乏しい感染症では、血液培養を再検することや感染臓器から採取した検体のグラム染色を再検し経時的な所見の比較を行うことが、治療効果判定の一助となる場合がある。
表8. 感染症の治療効果に用いる指標の分類と代表的な例
| 指標の種類 | 特徴 | 代表例 | |
|---|---|---|---|
| 臓器非特異的な指標 |
|
|
|
| 感染臓器に 比較的特異性の高い指標 |
|
感染臓器 | 代表的な指標 |
| 肺(肺炎) |
|
||
| 腎臓 (腎盂腎炎) |
|
||
| 前立腺 (前立腺炎) |
|
||
| 血管内(感染性心内膜炎、CRBSI) |
|
||
| 髄膜・脳 (髄膜炎・脳炎) |
|
||
B) 感染症が改善しない場合の原因の鑑別
まず、抗菌薬投与後も全身状態が非常に悪い場合、広域スペクトラムの抗菌薬に変更するのは妥当である。ただし、患者背景(基礎疾患、医療曝露歴、動物曝露歴や海外渡航歴等を含む)により、想定される原因微生物が異なることに留意が必要である。例えば、高齢者や免疫不全者の治療不応の肺炎の鑑別では結核や非結核性抗酸菌症を考える必要があり、腹部術後で長期にICUに入室し広域抗菌薬曝露がある症例では、カンジダを敗血症の原因として検討する必要がある85。このように、患者背景から考えられる原因微生物を具体的に想起し、現在投与中の抗微生物薬でどの微生物がカバーできていないのか、具体的に検討することが非常に重要である。
全身状態が悪いわけではないが、感染症が改善しないと感じた場合、表に挙げたような原因の鑑別を検討する83,86,87。
治療効果が感じられない場合、薬剤耐性菌による感染症を念頭に抗菌薬の変更を検討する場合が多いと思われるが、抗微生物薬のスペクトラムが原因でない場合も多い(補遺p5参照)。
治療効果が不十分と感じた場合、表9の鑑別を検討し、必要に応じ微生物学的検査や画像検査を追加し、その原因を精査することが重要である。同時に、現在投与中の抗微生物薬のスペクトラムに含まれていない原因微生物による感染症の可能性を考え、抗微生物薬の追加や変更についても検討を行う。
表9. 治療効果が不十分と感じる場合の主な原因
| 分類 | 鑑別 |
|---|---|
| 効果判定の問題 |
|
| 抗微生物薬のスペクトラムの問題 |
|
| 抗微生物薬の投与方法に関連した問題 |
|
| 免疫不全の存在 |
|
| 局所的な解剖変化を伴う感染 |
|
| 遠隔部位の感染 |
|
| 新たな感染の合併 |
|
| 感染症以外の原因 |
|
(ii) 抗菌薬の経静脈投与と経口投与
要旨
- 抗菌薬の経静脈投与から経口投与への変更には多くの利点があり、可能な症例では積極的に検討する
- 経口抗菌薬への変更にあたっては、一定の条件を満たす必要がある
- バイオアベイラビリティ(bioavailability)に優れた経口抗菌薬を選択することで、経静脈抗菌薬と同等の効果を期待できることが多い
はじめに
抗菌薬の投与ルートには経静脈と経口がある。入院患者では重症度や経口摂取困難等の理由から経静脈的な抗菌薬投与が初期治療として選択されることが多い。各感染症の治療期間すべてを経静脈投与にて完遂されることもあるが、経静脈投与から経口投与への変更には、薬剤コストや静注抗菌薬の調整に関わる時間の削減・入院期間の短縮・患者の快適性の向上・点滴に関連した感染症や血栓症等の合併症の減少等様々な利点がある88-90。このため、抗菌薬適正使用の観点から切り替えが可能な症例では積極的な検討を行うことが望ましい。
経静脈抗菌薬から経口抗菌薬への切り替え
経静脈抗菌薬から経口抗菌薬への切り替えを考慮する際は、以下のような基準をすべて満たしていることが推奨されている(表10)89-91。
表10. 経静脈抗菌薬から経口抗菌薬への切り替えが可能な推奨基準
- 臨床症状が改善している
- 24時間38℃未満の解熱を維持しており、呼吸・循環動態が安定している
- 静注抗菌薬による治療継続が必要な感染症(例:髄膜炎、発熱性好中球減少症、感染性心内膜炎等)ではない
- 経口もしくは経鼻胃管での投与が可能で、かつ、十分な吸収が見込まれる
- 適切な経口抗菌薬の選択肢がある
- 患者が経口抗菌薬を自己中断せず継続可能である(外来等の場合)
経静脈抗菌薬から経口抗菌薬への切り替えには、以下のようないくつかのパターンが考えられるが92、感染症の症候群や薬剤感受性、患者特性(腎機能やアレルギー歴等)に応じ、可能な経口抗菌薬の中から薬剤選択を行う。
① ある薬の経静脈抗菌薬を、同じ化合物の経口抗菌薬に置き換える場合 (例:レボフロキサシンの点滴静注から経口への切り替え)
② 同じクラスで同じ効能を持つが、化合物が異なる経静脈抗菌薬から、同等の経口抗菌薬に変更する場合(例:セファゾリン点滴静注からセファレキシン経口への変更)
③ 経静脈抗菌薬から別のクラスの経口抗菌薬に変更する場合(例:バンコマイシン点滴静注からスルファメトキサゾール・トリメトプリム[ST合剤]経口への変更)
経口抗菌薬のバイオアベイラビリティ
経口抗菌薬では薬剤ごとにバイオアベイラビリティが異なり、バイオアベイラビリティに優れた経口抗菌薬であれば、経静脈抗菌薬と同等の効果が期待できることが多い。表11にバイオアベイラビリティが良好な(60%以上)経口抗菌薬の例を記載した90,92,93。実際の投与にあたっては感染巣に応じた投与期間の設定や腎機能に応じた用法用量調整が必要になる。また、ボリコナゾールでは治療薬物モニタリング(Therapeutic Drug Monitoring: TDM)による血中濃度測定や用量調整が推奨されている21,94。
表11. バイオアベイラビリティが良好な経口抗菌薬の投与例
| 抗菌薬 | |
|---|---|
| ペニシリン系 | アモキシシリン |
| クラブラン酸/アモキシシリン※ | |
| セファロスポリン系 | セファレキシン |
| フルオロキノロン系 | シプロフロキサシン |
| レボフロキサシン | |
| モキシフロキサシン | |
| テトラサイクリン系 | ドキシサイクリン |
| ミノサイクリン | |
| リンコマイシン系 | クリンダマイシン |
| ニトロイミダゾール系 | メトロニダゾール |
| オキサゾリジノン系 | リネゾリド |
| ST合剤 | スルファメトキサゾール/トリメトプリム |
| 抗真菌薬 | |
| アゾール系 | フルコナゾール |
| ボリコナゾール | |
※ クラブラン酸のbioavailabilityは60%を切る場合もある95
(iii) 終末期患者に対する抗菌薬治療
要旨
人生の最終段階において「抗菌薬投与を行わない」選択肢も存在する
人生の最終段階にある患者の治療を考える場合、「治療ゴールがどこなのか」を考えることがとても重要である。患者の置かれた状況から、目指すのは症状緩和なのか、延命なのか、まずは患者やその家族と話し合いの上意思を確認し、ゴールを見定めることが必要である。抗菌薬投与の必要性や有用性に関してはこの治療ゴールに基づいて判断がなされることになる(図2)96。所定の倫理的手続きが必要になる場合もある。
感染症診療においては、抗菌薬投与を行うことがすべてではない。適切な抗菌薬投与のためには診断が必要である。また抗菌薬投与以外にも、感染巣のコントロール、宿主免疫の改善といった大切な要因がある。このために侵襲的な検査や治療が必要になる場合もありうる。感染巣のコントロールができないまま漫然と抗菌薬投与を行う場合は、患者の状態によっては、患者の苦痛をむしろ不要に長引かせることにもなりうる。
抗菌薬投与により患者の背景にある、進行した認知症、進行したがんの自然経過を変化させることはできるわけではない。生存を伸ばす可能性はあるかもしれないが、苦痛を伴う期間をむしろ長引かせる可能性もあることを理解しておく必要がある。また、発熱は必ずしも感染によるものではなく、腫瘍熱や薬剤熱、血栓形成等非感染性の発熱も鑑別に上がる。そのような中、点滴ルートの確保、身体拘束、採血、静脈炎、薬疹、下痢、CDI、多剤耐性菌の出現等、複数のデメリットを伴いうる抗菌薬投与を選択する必要性を熟慮する必要がある。
一方で、症状緩和が治療ゴールの患者においても抗菌薬投与がメリットになる場合はありうる。例えばUTIの治療は排尿時痛を、口腔内カンジダ症の治療は嚥下障害を緩和する可能性がある97。
最も大事なことは患者の治療ゴールは何なのかをしっかり話し合い見定めることである。その上で、抗菌薬投与が患者にとってメリットになるかどうかの判断を行いたい。
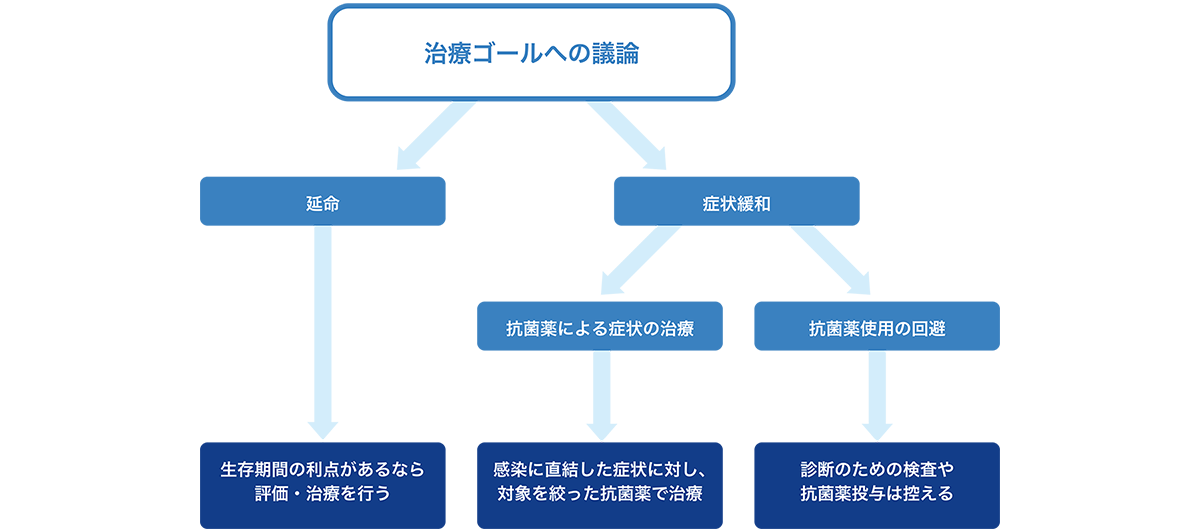
図2. 治療ゴールの議論において、抗菌薬使用の議論を始めるためのアルゴリズム96
14. 引用文献
- Arbo MJ, Fine MJ, Hanusa BH, Sefcik T, Kapoor WN. Fever of nosocomial origin: etiology, risk factors, and outcomes. Am J Med 1993;95(5):505-512.
- Magill SS, Edwards JR, Bamberg W, et al. Multistate point-prevalence survey of health care-associated infections. N Engl J Med 2014;370(13):1198-1208.
- McFarland LV. Epidemiology of infectious and iatrogenic nosocomial diarrhea in a cohort of general medicine patients. Am J Infect Control. 1995;23(5):295-305.
- Guembe M, et al. Nationwide survey on peripheral-venous-catheter-associated-bloodstream infections in internal medicine departments. J Hosp Infect 2017;97(3):260-266.
- Mermel LA, et al. Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of intravascular catheter-related infection: 2009 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2009;49(1):1-45.
- Safdar N, Fine JP, Maki DG. Meta-analysis: methods for diagnosing intravascular device-related bloodstream infection. Ann Intern Med 2005;142(6):451-466.
- Surgical Site Infection Event. National Healthcare Safety Network January 2023. https://www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscmanual/9pscssicurrent.pdf. 最終閲覧日2023年6月19日.
- Lipsky BA, Berendt AR, Cornia PB, et al. 2012 Infectious Diseases Society of America clinical practice guideline for the diagnosis and treatment of diabetic foot infections. Clin Infect Dis 2012;54(12):e132-173.
- Lee A, et al. Detection of bloodstream infections in adults: how many blood cultures are needed?, J Clin Microbiol, 2007;45(11):3546-3548.
- Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th ed. Philadelphia: Elsevier; 2019.
- Coburn B, Morris AM, Tomlinson G, Detsky AS, Does this adult patient with suspected bacteremia require blood cultures?, JAMA 2012; 308(5): 502-511.
- Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8):801-810.
- McFadden JP, et al, Raised respiratory rate in elderly patients: a valuable physical sign, Br Med J (Clin Res Ed). 1982;284(6316):626-627.
- Komatsu T, Onda T, Murayama G, et al. Predicting bacteremia based on nurse-assessed food consumption at the time of blood culture. J Hosp Med. 2012;7(9):702-705.
- Tokuda Y, Miyasato H, Stein GH, Kishaba T. The degree of chills for risk of bacteremia in acute febrile illness. Am J Med. 2005;118(12):1417.
- Miller SI et al. Hypoglycemia as a manifestation of sepsis. Am J Med. 1980;68(5):649-654.
- Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2021. Crit Care Med. 2021;49(11):e1063-e1143
- Vincent JL, et al. Use of the SOFA score to assess the incidence of organ dysfunction/failure in intensive care units: results of a multicenter, prospective study. Working group on "sepsis-related problems" of the European Society of Intensive Care Medicine. Crit Care Med. 1998;26(11):1793-1800.
- Spellberg B, Srinivasan A, Chambers HF. New Societal Approaches to Empowering Antibiotic Stewardship. JAMA. 2016;315(12):1229-1230.
- Willems RPJ, van Dijk K, Vehreschild MJGT, et al. Incidence of infection with multidrug-resistant Gram-negative bacteria and vancomycin-resistant enterococci in carriers: a systematic review and meta-regression analysis. The Lancet Infectious Diseases. 2023.
- 抗菌薬適正使用支援プログラム実践のためのガイダンス 8学会合同抗微生物薬適正使用推進検討委員会 感染症学雑誌, 第91巻, 第5号
https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/guidelines/1708_ASP_guidance.pdf - Dryden M, et al. Using antibiotics responsibly: right drug, right time, right dose, right duration. J Antimicrob Chemother. 2011;66(11):2441-2443.
- Schuler F, Froböse N, Schaumburg F. Prevalence and risk factors for bacteremia in patients with Staphylococcus aureus bacteriuria: A retrospective cohort study. Int J Infect Dis. 2020;98:467-469.
- Weinstein MP, et al. The clinical significance of positive blood cultures in the 1990s: a prospective comprehensive evaluation of the microbiology, epidemiology, and outcome of bacteremia and fungemia in adults. Clin Infect Dis. 1997;24(4):584-602.
- Pien BC, et al. The clinical and prognostic importance of positive blood cultures in adults. Am J Med 2010; 123(9): 819-828
- Hodnett ED, et al. Re-conceptualizing the hospital labor room: the PLACE (pregnant and laboring in an ambient clinical environment) pilot trial. Birth, 2009;36(2):159-166.
- Torres A, et al. International ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines for the management of hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated pneumonia: Guidelines for the management of hospital-acquired pneumonia (HAP)/ventilator-associated pneumonia (VAP) of the European Respiratory Society (ERS), European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) and Asociación Latinoamericana del Tórax (ALAT). Eur Respir J. 2017;50(3):1700582.
- Janmaimool P, Watanabe T. Evaluating determinants of environmental risk perception for risk management in contaminated sites. Int J Environ Res Public Health. 2014;11(6):6291-6313.
- Gupta K, Hooton TM, Naber KG, et al. International clinical practice guidelines for the treatment of acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women: A 2010 update by the Infectious Diseases Society of America and the European Society for Microbiology and Infectious Diseases. Clin Infect Dis. Mar 1 2011;52(5):e103-120.
- Pardo J, Klinker KP, Borgert SJ, Trikha G, Rand KH, Ramphal R. Time to positivity of blood cultures supports antibiotic de-escalation at 48 hours. The Annals of pharmacotherapy. 2014;48(1):33-40.
- Puerta-Alcalde P, Cardozo C, Suarez-Lledo M, et al. Current time-to-positivity of blood cultures in febrile neutropenia: a tool to be used in stewardship de-escalation strategies. Clin Microbiol Infect. Apr 2019;25(4):447-453.
- Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A, et al. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society consensus guidelines on the management of community-acquired pneumonia in adults. Clin Infect Dis. Mar 1 2007;44 Suppl 2(Suppl 2):S27-72.
- Thom KA, et al. Impact of a Prescriber-driven Antibiotic Time-out on Antibiotic Use in Hospitalized Patients. Clin Infect Dis. 2019;68(9):1581–1584.
- Yoshida H, Motohashi T, De Bus L, et al. Use of broad-spectrum antimicrobials for more than 72 h and the detection of multidrug-resistant bacteria in Japanese intensive care units: a multicenter retrospective cohort study. Antimicrob Resist Infect Control. Sep 29 2022;11(1):119.
- Tamma PD, Avdic E, Li DX, Dzintars K, Cosgrove SE. Association of Adverse Events With Antibiotic Use in Hospitalized Patients. JAMA Intern Med. Sep 1 2017;177(9):1308-1315.
- Dantes R, et al. Association Between Outpatient Antibiotic Prescribing Practices and Community-Associated Clostridium difficile Infection. Open Forum Infect Dis. 2015 Aug 11;2(3):ofv113.
- Ho C-Y, Lee C-H, Yang C-Y, Hsieh C-C, Ko W-C, Lee C-C. Antimicrobial escalation is not beneficial for Gram-negative bacteremia in adults who remained critically ill after appropriate empirical therapy. Journal of infection and chemotherapy: official journal of the Japan Society of Chemotherapy. 2020 Sep;26(9):933-940.
- Roger P-M, et al. Risk Factors for Unnecessary Antibiotic Therapy: A Major Role for Clinical Management. Clin Infect Dis. 2019 Jul;69(3):466-472.
- Baggio D, Ananda-Rajah MR. Fluoroquinolone antibiotics and adverse events. Aust Prescr. 2021 Oct;44(5):161-164.
- Bassetti M, Vena A, Giacobbe DR, et al. Risk Factors for Intra-Abdominal Candidiasis in Intensive Care Units: Results from EUCANDICU Study. Infect Dis Ther. 2022 Apr;11(2):827-840.
- Shime N, Satake S, Fujita N. De-escalation of antimicrobials in the treatment of bacteraemia due to antibiotic-sensitive pathogens in immunocompetent patients. Infection. 2011 Aug;39(4):319-325.
- Averbuch D, Orasch C, Cordonnier C, et al. European guidelines for empirical antibacterial therapy for febrile neutropenic patients in the era of growing resistance: summary of the 2011 4th European Conference on Infections in Leukemia. Haematologica. 2013 Dec;98(12):1826-1835.
- Ly WJ, Brown EE, Pedretti Z, Auten J, Wilson WS. Evaluation of early de-escalation of empiric antimicrobial therapy in acute leukemia patients with febrile neutropenia at a large academic medical center.J Oncol Pharm Pract. 2023 Mar;29(2):305-310.
- Petteys MM, Kachur E, Pillinger KE, He J, Copelan EA, Shahid Z. Antimicrobial de-escalation in adult hematopoietic cell transplantation recipients with febrile neutropenia of unknown origin. J Oncol Pharm Pract. Apr 2020;26(3):632-640.
- Ohji G, Doi A, Yamamoto S, Iwata K. Is de-escalation of antimicrobials effective? A systematic review and meta-analysis. Int J Infect Dis. 2016 Aug;49:71-79.
- Garnacho-Montero J, Gutiérrez-Pizarraya A, Escoresca-Ortega A, et al. De-escalation of empirical therapy is associated with lower mortality in patients with severe sepsis and septic shock. Intensive Care Med. 2014 Jan;40(1):32-40.
- Guo Y, Gao W, Yang H, Ma Ce, Sui S. De-escalation of empiric antibiotics in patients with severe sepsis or septic shock: A meta-analysis. Heart Lung. 2016Sep-Oct;45(5):454-459.
- Routsi C, Gkoufa A, Arvaniti K, et al. De-escalation of antimicrobial therapy in ICU settings with high prevalence of multidrug-resistant bacteria: a multicentre prospective observational cohort study in patients with sepsis or septic shock. J Antimicrob Chemother. 2020 Dec;75(12):3665-3674.
- Lakbar I, De Waele JJ, Tabah A, Einav S, Martin-Loeches I, Leone M. Antimicrobial De-Escalation in the ICU: From Recommendations to Level of Evidence. Adv Ther. 2020 Jul;37(7):3083-3096.
- Lin J, Zhou M, Chen J, Zhang L, Lu M, Liu Z. De-escalation from Echinocandins to Azole Treatment in Critically Ill Patients with Candidemia. International journal of infectious diseases. Int J Infect Dis. 2022 Aug;121:69-74.
- Bailly S, Leroy O, Montravers P, et al. Antifungal de-escalation was not associated with adverse outcome in critically ill patients treated for invasive candidiasis: post hoc analyses of the AmarCAND2 study data. Intensive care Med. 2015 Nov;41(11):1931-1940.
- Seddon MM, Bookstaver PB, Justo JA, et al. Role of Early De-escalation of Antimicrobial Therapy on Risk of Clostridioides difficile Infection Following Enterobacteriaceae Bloodstream Infections. Clin Infect Dis. 2019 Jul;69(3):414-420.
- Lew KY, Ng TM, Tan M, et al. Safety and clinical outcomes of carbapenem de-escalation as part of an antimicrobial stewardship programme in an ESBL-endemic setting. J Antimicrobial Chemother. 2015 Apr;70(4):1219-1225.
- Tagashira Y, Horiuchi M, Tokuda Y, Heist BS, Higuchi M, Honda H. Antimicrobial stewardship for carbapenem use at a Japanese tertiary care center: An interrupted time series analysis on the impact of infectious disease consultation, prospective audit, and feedback. Am J Infect Control. 2016 Jun;44(6):708-710.
- Honda H, Murakami S, Tagashira Y, et al. Efficacy of a Postprescription Review of Broad-Spectrum Antimicrobial Agents With Feedback: A 4-Year Experience of Antimicrobial Stewardship at a Tertiary Care Center. Open Forum Infect Dis. 2018 Nov;5(12):ofy314.
- Akazawa T, Kusama Y, Fukuda H, et al. Eight-Year Experience of Antimicrobial Stewardship Program and the Trend of Carbapenem Use at a Tertiary Acute-Care Hospital in Japan-The Impact of Postprescription Review and Feedback. Open Forum Infect Dis. 2019 Sep;6(10):ofz389.
- Morgan DJ, Coffey KC. Shorter Courses of Antibiotics for Urinary Tract Infection in Men. JAMA. 2021 Jul;326(4):309-310.
- Antimicrobial Resistance Collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. Lancet. 2022 Feb;399(10325):629-655.
- Ramirez J, et al. Antibiotics as Major Disruptors of Gut Microbiota. Front Cell Infect Microbiol. 2020 Nov;10:572912.
- Esaiassen E, et al. Antibiotic exposure in neonates and early adverse outcomes: a systematic review and meta-analysis. J Antimicrob Chemother. 2017 Jul;72(7):1858-1870,
- Lee RA, et al. Appropriate Use of Short-Course Antibiotics in Common Infections: Best Practice Advice from the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2021 Jun;174(6):822-827.
- Abbas M et al. Association between treatment duration and mortality or relapse in adult patients with Staphylococcus aureus bacteraemia: a retrospective cohort study. Clin Microbiol Infect, 2020 May;26(5):626-631.
- Lafaurie M. et al. Antimicrobial for 7 or 14 Days for Febrile Urinary Tract Infection in Men: A Multicenter Noninferiority Double-Blind, Placebo-Controlled, Randomized Clinical Trial. Clin Infect Dis. 2023 Jun;76(12):2154-2162.
- Bernard L. et al. Antibiotic Therapy for 6 or 12 Weeks for Prosthetic Joint Infection. N Engl J Med. 2021 May;384(21):1991-2001.
- Sehgal I. et al. Efficacy of 12-months oral itraconazole versus 6-months oral itraconazole to prevent relapses of chronic pulmonary aspergillosis: an open-label, randomised controlled trial in India, Lancet Infect Dis. 2022 Jul;22(7):1052-1061.
- Corey GR. et al. Short-course therapy for bloodstream infections in immunocompetent adults. Int J Antimicrob Agents. 2009;34(4):S47-51.
- Vento S. et al. Lung infections after cancer chemotherapy. Lancet Oncol. 2008 Oct;9(10):982-992.
- Rolston KVI. Infections in Cancer Patients with Solid Tumors: A Review. Infect Dis Ther. 2017 Mar;6(1):69-83.
- Geerlings ES. Clinical Presentations and Epidemiology of Urinary Tract Infections. Microbiol Spectr. 2016 Oct;4(5)
- Lipsky AB. et al. Treatment of bacterial prostatitis, Clin Infect Dis. 2010 Jun;50(12):1641-1652.
- Kalil CA. et al. Management of Adults With Hospital-acquired and Ventilator-associated Pneumonia: 2016 Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the American Thoracic Society. Clin Infect Dis. 2016 Sep;63(5):e61-111.
- Bouglé A. et al. Comparison of 8 versus 15 days of antibiotic therapy for Pseudomonas aeruginosa ventilator-associated pneumonia in adults: a randomized, controlled, open-label trial. Intensive Care Med. 2022 Jul;48(7):841-849.
- Pappas PG. et al. Clinical Practice Guideline for the Management of Candidiasis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2016 Feb;62(4):e1-50.
- Baddour LM. et al. Infective Endocarditis in Adults: Diagnosis, Antimicrobial Therapy, and Management of Complications: A Scientific Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association. Circulation. 2015 Oct;132(15):1435-1486.
- Klompas M. Set a short course but follow the patient’s course for ventilator-associated pneumonia. Chest. 2013 Dec;144(6):1745-1747.
- Cosgrove ES et al. Management of methicillin-resistant Staphylococcus aureus bacteremia, Clin Infect Dis. 2008 Jun;46(5):S386-393.
- Liu C. et al. Clinical practice guidelines by the infectious diseases society of america for the treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in adults and children. Clin Infect Dis. 2011 Feb;52(3):e18-55.
- Yahav D et al. Seven Versus 14 Days of Antibiotic Therapy for Uncomplicated Gram-negative Bacteremia: A Noninferiority Randomized Controlled Trial. Clin Infect Dis. 2019 Sep;69(7):1091-1098.
- Dach VE. et al. Effect of C-Reactive Protein-Guided Antibiotic Treatment Duration, 7-Day Treatment, or 14-Day Treatment on 30-Day Clinical Failure Rate in Patients With Uncomplicated Gram-Negative Bacteremia: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2020 Jun;323(21):2160-2169.
- Molina J. et al. Seven-versus 14-day course of antibiotics for the treatment of bloodstream infections by Enterobacterales: a randomized, controlled trial. Clin Microbiol Infect. 2022 Apr;28(4):550-557.
- Turjeman A. et al. Duration of antibiotic treatment for Gram-negative bacteremia – Systematic review and individual participant data (IPD) meta-analysis. EClinicalMedicine. 2022 Dec;55:101750.
- Heil LE, et al. Optimizing the Management of Uncomplicated Gram-Negative Bloodstream Infections: Consensus Guidance Using a Modified Delphi Process. Open Forum Infect Dis. 2021 Oct;8(10):ofab434.
- Japanese Respiratory Society. Strategies for non-responders. Respirology. 2009 Nov;14 Suppl 2:S41-3.
- Macfarlane JT. et al. Comparative radiographic features of community acquired Legionnaires' disease, pneumococcal pneumonia, mycoplasma pneumonia, and psittacosis. Thorax. 1984 Jan;39(1):28-33.
- Pappas PG. et al. Invasive candidiasis. Nat Rev Dis Primers. 2018 May;4:18026.
- Ioanas M. et al. Causes and predictors of nonresponse to treatment of intensive care unit-acquired pneumonia. Crit Care Med. 2004 Apr;32(4):938-945.
- Raff AB, Kroshinsky D. Cellulitis: A Review. JAMA. 2016 Jul;316(3):325-337.
- Nathwani D, Lawson W, Dryden M. et al, Implementing criteria-based early switch/early discharge programmes: a European perspective. Clin Microbiol Infect. 2015 Sep; 21 Suppl 2: S47-55.
- ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP FROM PRINCIPLES TO PRACTICE 2018 British Society for Antimicrobial Chemotherapy
- 野本英俊,忽那賢志,早川佳代子,大曲貴夫, 国立国際医療研究センター病院総合感染症科・国際感染症センター. 経口抗菌薬へのスイッチを再考する. KANSEN Journal No.73(2019.7.29)
- Sevinç F. et al. Early switch from intravenous to oral antibiotics: guidelines and implementation in a large teaching hospital. J Antimicrob Chemother. 1999 Apr;43(4):601-606.
- Cyriac JM, James E, Switch over from intravenous to oral therapy: A concise overview. J Pharmacol Pharmacother. 2014 Apr; 5(2): 83-87.
- 抗菌薬適正使用生涯教育テキスト 第3版
- 日本化学療法学会 抗菌薬TDM臨床実践ガイドライン2022
- Nilsson-Ehle I. et al. Pharmacokinetics of clavulanic acid, given in combination with amoxycillin, in volunteers. J Antimicrob Chemother. 1985 Oct;16(4):491-498.
- Baghban A, Juthani-Mehta M. Antimicrobial Use at the End of Life. Infec Dis Clin North Am. 2017 Dec(4):639-647.
- Barlam TF. et al. Implementing an Antibiotic Stewardship Program: Guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the Society for Healthcare Epidemiology of America. Clin Infect Dis. 2016 May;62(10): e51-77